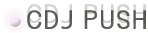奇跡の高峰であると同時に、未知の高みでもある。ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタはヴァイオリニストにとって、いやピアニストにとってもいつでも魅力的な存在であるのだろう。それをあらためて教えてくれたふたりが三浦文彰(vn)と清水和音(p)である。すでに全曲の録音もリリースされているが、この2月と3月に東京と大阪で最後となる〈清水和音×三浦文彰 ベートーヴェン ヴァイオリン・ソナタ全曲演奏会Ⅲ〉を行なうふたりに、ベートーヴェンのつきせぬ魅力について語っていただいた。
――清水さんと三浦さん。じつは世代がかなり違っていて、どうやって出会ったのだろうと気になっていたのですが。
三浦文彰「きっかけはコロナ禍ですね。その時期にとあるオーケストラの公演が中止になり、別の形でのガラ・コンサートが開催されて、そこで一緒に演奏する機会があったのですが、食事も一緒にして、何か一緒にやりましょうよ、という話になったのです」
清水和音「最初にラヴェルの〈ツィガーヌ〉を弾いたのだけど、合わせても一瞬もズレない」
――「ツィガーヌ」で?
清水「そう。一瞬も。それとお互いの呼吸感もわかりやすいし、余計なものも挟まらないので。ただ、テンポ感だけはそれぞれの感覚があるから、ちょっと合わせないとダメなところもあるのだけれど、違和感はなかったね」
――それが最初に出たブラームスのヴァイオリン・ソナタ3曲の録音に繋がったと。
三浦「そうです。2023年1月の録音で、録音した場所は今回のベートーヴェンも同じ(東京・稲城市立iプラザ)です」
――継いで、今回のベートーヴェンということになるのですが、ベートーヴェンという作曲家はそれぞれの演奏家で相当にイメージの違いがありそうな気がするので、合わせるまでに時間がかかったと思うのですが。
三浦「それがそうではなく、最初からスムーズでした。僕たちのリハーサルは、だからあっと言う間に終わりますよ。サラッと一緒に弾いて終わり、みたいな」
清水「僕たちは楽譜どおり(笑)だし、以前より楽譜どおりになってきたかもしれないですよ」
――ホントですか? ちょっと信じられないけれど。
清水「作曲家というのは譜面に全部書けたから“天才”だと。楽譜に表現できた人が天才として残っていると思っているし、それを先生から教わったからね」
――ただ、ベートーヴェンの手書きはとても汚くて、読みづらいから、その解読がいまだに続いていますよね。
清水「それも要素としてあるだろうけれど、細かい点を気にしすぎて、改訂する人が前の改訂者と違うことをしたいという積み重ねが混乱させていますよね」
――三浦さんは指揮者としてもベートーヴェンを振っていますが。
清水「これが驚いた。『運命』でこんなにすごい演奏があるのかって。指揮者として本格的に活動するなら、ヴァイオリンやめてもらわないと(笑)」
三浦「いや、指揮もヴァイオリンもやめないですよ(笑)」

Photo by Yuji Hori
――おふたりの録音で言うと、途中でヴァイオリンの楽器が替わっていますよね。それもストラディヴァリウスからグァルネリ・デル・ジェスへ。
三浦「たまたま楽器が替わる時期だったので。第1、5、8番はストラドで録音して、残りはデル・ジェスで弾きました」
清水「あらためて自分で録音を聴いてみると、デル・ジェスのほうがとても良いと感じましたね。相当明るい音に聴こえる。エネルギー感が違いますね。ただ、それはあくまでも弾き手の問題だと思う」
三浦「それはそうだけど(笑)」
——作品の順番で言うと、演奏が面白いと感じたのは「第2番 イ長調」でした。
三浦「あの曲は、最初にヴァイオリンのテーマが“タラッ、タラッ、タラッ”と下がっていくのですが、そこにも意外な難しさがあります。ヴァイオリンもピアノもシンプルながら、それぞれの楽器で工夫をしなければいけないところがあるのです」

三浦文彰 Photo by Yuji Hori
清水「でも第2番が面白いって言ってくれるのはうれしいですね。あの曲はどうしても埋もれてしまいますよね。フィナーレも大好きなのだけど、多くの人がベートーヴェンに求めるイメージとは違うのだろうなと思います」
――たしかにそれは言えますね。
清水「ベートーヴェンにはいろいろな面があって、まだまだ発見されていない面もあると思うけど、この全曲録音が出来上がったときに、ふたりで“ベートーヴェンは男だ”って喜んだ(笑)」
――おとこ、ですか?
清水「そう。クラシック音楽の世界で性別を気にすることはあまりないのだけれど、男性的要素で出来上がっているのはベートーヴェンのみだと。それ以外はないと思う」
三浦「男らしさっていう点で圧倒的な作曲家だとは思います」
清水「昔からの男」
三浦「(笑)トラディショナルな“おとこ”ね」
――清水さんはベートーヴェンのピアノ・ソナタ全曲録音もされていたわけで、ちょっとマニアックな質問となりますが、ピアノ・ソナタを書いているときとヴァイオリン・ソナタを書いているときのベートーヴェンのピアノの使い方の違い、というのは何か感じますか?
清水「それはとくにないですね。ただ、つねにピアノに対する不満はあったのだろうなとは感じます。後期に行くに従って、当時の楽器ではベートーヴェンの意図する音は出なかっただろうと思います。現代のスタインウェイのフルコンサートでも足りないぐらいの部分がありますから。つねに“はみ出して”いますよね。それがベートーヴェンの特徴かもしれない」

清水和音 Photo by Yuji Hori
三浦「ふーん。なるほど。ヴァイオリニストにとっても難しくは書いたと思うのだけれど、歴史的に見るとベートーヴェンの後にパガニーニとかが登場してくるので、そこまで技巧的な面での難しさは追求していなかったと思います。重音もほぼないし」
清水「そうであるなら〈クロイツェル(ヴァイオリン・ソナタ 第9番)〉の冒頭はなぜ、あんなに難しいことになってるのかな。G-dur(ト長調)なら簡単なのに、なんでA-dur(イ長調)で書いたのだろう、っていつも思うけどね。あえて、その難しさを冒頭に置いた可能性もあるよね」
――「クロイツェル」はA-dur以外には考えられないけれど(笑)。
清水「あのテンションの高さはあきらかにA-durでしか出ないですよね。でも第2楽章になると……」
三浦「ちょっと退屈する? でも、ヴァイオリニストにとってはぜんぜんそんなことはなく、第2楽章(変奏曲)もけっこう難しく、かつやり甲斐のある楽章ですよ。じつは第2楽章のピアノも難しいと思っているのですよ。ピツィカートの変奏の部分なんか、ピアノがゴツゴツして聴こえることが多いのだけれど、清水さんの演奏はそれを感じさせないで、滑らかに鳴っているところがすごいです」
清水「簡単な話、あそこは難しい(笑)。ベートーヴェンの持っているプリミティヴなゴツゴツ感も持っていないといけないし、ピアニズムとしては美しくなければならないのでね」
――ベートーヴェンはだからやり甲斐がある?
三浦「ベートーヴェンは本当にやり甲斐がありますよ」
清水「ようやくわかってきた、この歳で、という感じです」
――2月23日には東京・サントリーホールで、3月16日には大阪・ザ・シンフォニーホールで「全曲演奏会Ⅲ」が開催されます。しかも最後の第8~10番で「クロイツェル」も入っています。楽しみですが、その後のプロジェクトは?
三浦「シューベルトの〈幻想曲〉や、もっと近代の作品も一緒に演奏したいですね」
清水「プロコフィエフの第1番はやりたいですね」
――演奏会も録音も期待しています。
取材・文/片桐卓也
(C)ONGAKUSHUPPANSHA Co.,Ltd.