1976年9月28日、スティーヴィー・ワンダーの大傑作アルバム『キー・オブ・ライフ(The Songs In The Key Of Life)』がアメリカでリリースされた。アナログLP2枚組では収まりきらず、7inchシングルにも4曲を収めたこの超大作は、アルバム・チャート首位を獲得したのみならず、1977年の〈グラミー賞〉では“最優秀アルバム賞”をはじめ7部門を獲得。名実ともにスティーヴィーのキャリアを代表する作品となった。
そして、2014年11月6日のニューヨーク、マディソン・スクエア・ガーデンでのコンサートを皮切りに、『キー・オブ・ライフ』全曲を完全に再現する一大ツアーが始まった、これまで北米だけで3度行われたこのツアーでは、大編成のバンドによるアルバムの完全再現が試みられ、その圧倒的な完成度が各地で大きな感動を呼び起こしてきたのだが、じつはこのツアー・バンドのレギュラー・ギタリストとして、ひとりの日本人ギタリストが参加しているのはご存じだろうか?そのギタリストは、LAを拠点に音楽活動を行っている中村陽平氏。チャカ・カーン、シーラE.などのバック・バンド参加を経て、オーディションで大役を勝ち得たという。そんな大抜擢を受けるくらいだから、少年時代から陽の当たる道を歩んできたのかと思いきや、中村さんの音楽人生は決して平坦なものではなかった。はたしてその音楽的なシンデレラ・ストーリーはどのように切り拓かれていったのか。そして、いまだ日本では実現しないままになっている『キー・オブ・ライフ』ツアーの舞台裏についてなど、なかなか聞く機会のない貴重な話を聞いた。
――スティーヴィー・ワンダーの現在のバックバンドに2人いるギタリストのひとりが中村さんで、2014年から世界各地で行われてきた『キー・オブ・ライフ』全曲再現ライヴにも当然、参加されていて。すごいことですよね。日本でもあのライヴ見てみたいと思ってる人は相当います。
「北米ではすでに3回『キー・オブ・ライフ』ツアーをやっています。“北米ではもう終わり”とスティーヴィー自身も言っているので、もしかしたらこれからヨーロッパやアジアでもこのツアーをするかもしれないですけど、なにしろ普通のコンサートに比べて倍以上のメンバーになる大掛かりなプロジェクトなので、今のところはまだわからないですね」
――今年の9月28日が、アメリカで『キー・オブ・ライフ』が発売されて、ちょうど40周年の節目でもあるんですよね。そんなアニバーサリー・イヤーでもあるので、今じっさいにあのアルバムの曲を演奏している中村さんにその経験についてお聞きしたいです。中村さんが渡米して音楽活動を始めて、どうやってスティーヴィーのバンドに加入するに至ったのか、その音楽人生の軌跡からおうかがいできたらと思ってます。中村さんは1978年生まれなので、思春期の音楽体験は1990年代のど真ん中ですよね。
「そうですね。でも、高校時代にギターを習っていた先生がブルースが好きな方で、“ギターやるならブルースを聴け!”と。そこから入っていったら、ロックも深いルーツのところや、ジャズのほうまで聴く範囲が広がっていったので、ブルースはいいきっかけでしたね」
――“おなじ高校の人たちに比べて自分はギターがうまいかも?”みたいな自覚はなかったんですか?
「いや、バンドも文化祭でやるくらいだったし、本当に周りにギターを弾いてる人がそんなにいなかったんですよ。でも、最終的に“もっとちゃんとギターをやろう”と決心したのは、高3になって進路を考え始めたときでした。僕は普通の大学に行くより、音楽の専門学校でもうちょっとギターをやりたいと思ったんです。それを両親に話したら、“後悔しないように自分の責任でやりなさい”って、結構寛大に受け止めてくれて、西葛西にあった東京コミュニケーション・アート(※現在は音楽部門が分離し、東京スクール・オブ・ミュージックと改称)という学校に一年通いました。そこから、その学校と提携していたロサンゼルスにあるLAMA(※Los Angeles Music Academy)との留学プログラムで、渡米したんです。LAMAはまだ新しい音楽学校で、当時はギタリストのフランク・ギャンバレが学長をやっていました」
――その時点では、中村さんが音楽的に志向していたのは、どういうことだったんですか?
「ギターの先生の影響もあったんですけど、ラリー・カールトンやリー・リトナー、ロベン・フォード、スティーヴ・ルカサー、マイケル・ランドウ、ポール・ジャクソンJr.とかでしたね。どちらかというと裏方で、自分たちのプロジェクトもやっているけど、LAでスタジオ・ミュージシャンとして活動していた人たちをよく聴いてました。LAMAでは、そういう人たちのリズム・プレイやバッキングの基礎を真似して学んだりしてました」
――中村さんは、譜面に頼らない“耳コピ”が得意だそうですが。
「高校のときのギターの先生がそういう概念を教えてくれたんです。“ブルースを聴いてコピーしろ”と言われて。聴いたやつのキーを見つけて、アルバム流しながらリアルタイムで弾いていくというのが自分のギターの鍵になったかもしれないです。結果的に、アメリカに渡った今でも耳が役立ってます。たとえば、僕が今やる仕事の99%は譜面を使うことはないんです。リハーサルとかで多少時間はかかるかもしれないけど、最終的にはみんな耳で覚えていきます。そのほうが、曲を全部覚える能力がフル活用されるから」
――自分の出番だけを譜面でやるより、曲全体を音の流れとして自分と同調させていくような。
「そうですね。耳で覚えるのが一番残ります。ウェス・モンゴメリーも全部耳コピだったんですよね。彼は譜面どころか、コードも読めなかった。それでも耳であれほどの演奏をしていたんです。今、僕が一緒に演奏しているすごいミュージシャンでも、音楽学校に行ってない人も多いし、譜面が読めない人は普通にいます。あと、ゴスペルを通ってきてる人が多いですね。ゴスペルには、ポップスやジャズに近いコード進行もあるんですけど、フレーズのアイデアだったり、コードのヴォイシング、音のチョイスが独特で、そこを教わった体験も大きかったですね」
――実際に教会で演奏したり?
「そうですね。今は定期的にはやってないですけど、時期によっては毎週教会に行って演奏するときもあります。ゴスペルって音楽的にも発想が自由だし、若いミュージシャンやシンガーですごい人もいっぱいいます。10代くらいの人たちから学ぶこともすごく多いですね。“こんなコードに行っちゃっていいんだ!”みたいな驚きも、彼らかしてみれば“かっこよければ、それでいい”なんです」
――素朴な疑問なんですけど、どうやって教会の演奏に入れてもらうんですか?
「LAMAには一年行って、そのあと帰国したんですけど、それからボストンのバークリー音楽院に奨学金制度で入学したんです。バークリーを卒業してからはしばらくボストンにいて、もう一度LAに戻ってきたのが、僕が30歳になった年でした。そのときはLAMA時代の知り合いもいないし、音楽的なツテもなかったので、最初は地元のいろんなところに行って平日の夜のジャム・セッションとかに飛び入りしたりして、気に入ってくれる人がいたら電話番号を教えて、みたいなことをやっているうちに、“ちょっと今週、ギタリストが足りないんでうちのチャーチに来てくれないか?”と呼ばれたりして。そこがきっかけで、彼らがやっている教会以外の仕事にもつながって、さらにまた違う教会からも声がかかったりして」
――バークリーでの経験が糧になっている部分もありますか?
「バークリーではジャズの音楽理論を理詰めで学んだので、コードの動きとか曲を把握する上では、今でもすごく役に立ってます。でも、本当の意味で音楽を学んでいるなと感じるようになったのは、LAに戻ってきてからですね。学んだ理論を消化して、さらにゴスペルの人たちと演奏することでそれを打ち砕かれる経験もして、もっと耳で音やスタイルを選ぶということをそこからまた勉強したんです」
――バークリーを卒業されたとはいえ、その後にボストンでは結構、厳しい時期も過ごされてますよね。
「ウェディング・バンドでの演奏とか、ですかね(笑)。厳しいというか、あれはあれでいい勉強でした。ただ、毎週おなじレパートリーをオリジナルに近く弾くという指示があって、自分のクリエイティヴィティを求められる状況ではなかったですけど」
――日本に帰って腕を試そうという気にはならなかった?
「思ったこともありました。ボストンに骨を埋めるわけにもいかないし。でも、もともとLAMAからアメリカ生活を始めたし、LAのミュージシャンが好きだし、日本に帰る前に一度LAに戻ってみようと思ったんです。そこで自分がどこまでいけるかチャンレンジしよう、ダメだったら日本に帰ろう、と」
――そのLAでの最大の出会いが、チャカ・カーンのバンドでベースを弾いていたアンドリュー・グーシェ。
「そうですね。あの人以上に自分のキャリアを直接的に変えた人はいないです。じつは彼とはおなじ教会で演奏したことはないんですけど、彼が当時、ジャム・セッションのホスト・バンドを率いてて、僕はそのバンドにたまたま飛び入りしただけなんですけど、すごく気に入ってくれたんです。そこから、ジャム・バンドで一緒に演奏することになり、しばらくしたらチャカのバンドにも抜擢してくれて」
――それが2011年。ちょっとした男性版シンデレラ・ストーリーですね。
「僕は特になんのキャリアもないし、日本人だし、ジャム・セッションに来ただけなのに、僕を信頼して、自分の大きな仕事であるチャカのバンドでのギターをまかせてくれた。やっぱりそこで“これをまかせる。頼んだぞ!”って言ってもらえたのは、すごく大きいですね。そのプレッシャーが自分をさらに成長させてくれた部分でもあるので」
――チャカ・カーンのバンドでの仕事は、それこそいきなりの大舞台ですよね。
「でも、初めての参加のときはリハもなかったんですよ。急にギタリストの穴があいちゃって、週の頭にアンドリューから“今週の土曜日空いてるか?”って電話がかかってきたんです。“空いてるよ”って返事したら、“うちらでその日、プリンスのオープニングやるから”って。なんの話かよくわからなかったんですけど、チャカ・カーンのショーだということでした。でも彼らは別のショーでLAにはいなくて、リハをやる時間がない。だから“曲目とCDを渡すからそれを覚えておいて!”と言われて、3、4日で覚えたんです」
――まさに耳コピ。
「そうです。当日、サウンドチェックで軽く合わせたくらいで、後は本番」
――その夜はプリンスのオープニングでチャカが出たわけですよね?LAの一番ホットな場所にいきなり放り込まれた心境はどうでした?
「いきなりそういう仕事が入ってくるというのも、アメリカのふところの大きさだという気がするんです。特に音楽の分野に関しては、LAはチャンスがいっぱい転がってる街だという認識はしていたんですけど、じっさいに自分の身にそういうことが起こって、実感しました」
――ただし、そこでちゃんとベストのパフォーマンスをしないと、次に呼ばれるかはわからない。
「そうですね。そこは結果を残さないと次に続かないので、ひとつひとつ真剣にやっていかないと。それこそ街の小さなクラブでやるときでも、LAの場合は誰が見てるかわからないので。客席にすごく有名なシンガーやミュージシャンがいたりすることもザラですからね。毎回きっちりできることをやらないと信用してもらえない。とはいえ、基本的には、みんな楽しくやってますよ。音楽を楽しむという姿勢が、僕が受けた影響としては一番大きいかなという気がします」
――なるほどね。ではそろそろスティーヴィーとの仕事について、いろいろ聞きたいと思います。
「チャカのバックをやってから、それほどトントン拍子というわけではなかったんです。いろいろ単発でバックをやっているうちに、2013年にスティーヴィーのオーディションを受ける話が来て、“今度一回弾きに来て”という話になったんです。LAにある大きなリハーサル・スタジオに呼ばれました。そこにはスティーヴィーがいて、ライヴとおなじセッティングでメンバーたちもいて、そこで言われた曲をやる、というオーディションでした」
――その場でどの曲にも対応できないといけない。
「そうなんですけど、スティーヴィーは曲数がすごいし、コード進行も複雑なんですよ。しかも“これをやって”と言われた曲も、誰もが知ってるような有名曲じゃなくて、結構マニアックなアルバム曲だったりする。まあ、そこはオーディションなので、あえてそういう曲をリクエストしたのかもしれないですけど」
――差し支えなければ、そのとき弾いた曲を教えてください。
「〈センド・ワン・ユア・ラヴ〉、それから〈ルッキン・フォー・アナザー・ピュア・ラヴ〉。ジェフ・ベックがギター・ソロを弾いてる曲です。あとは、〈ハイアー・グラウンド〉だったかな。コルトレーンの〈ジャイアント・ステップス〉をやるように言われてた人もいましたね。スティーヴィーはあの曲が大好きなんです」
――それを曲名聞いただけで合わせていかないといけないわけですか。
「〈センド・ワン・ユア・ラヴ〉とか、コード進行がめちゃめちゃ難しいんですよ。スティーヴィーの独特のコード感で転調もあるし、曲そのものをきっちりコピーしないと覚えられないような曲なんです。まさかあれが来るとは思わなかったですね」
――よくやれましたね。
「まず“15分与えるから、それまでに曲を覚えて”って、時間をもらえるんです。でも、よりによって僕が一番目だったんですよ。とりあえず車に戻って、YouTubeに誰かが上げていたライヴ・ヴァージョンをチェックしました。それを聴いて、“とりあえずこのコードかな”っていう感じで探って、なんとか演奏したというのは覚えてます」
――中村さん自身としては、合格の手応えはありました?
「ぶっちゃけ、もうダメだと思ってました。“明日からまたがんばろう”くらいの気持ちで帰ったんです。でも、一週間くらいしたら、そのときの音楽ディレクターから電話がかかってきたんです。“もう一回、きみともうひとりをオーディションするから”って言われて、今度はニューヨークまで連れていかれました。そのときは、サウンドチェックのときに弾くように言われて。そこからまたしばらくしたら、“香港にライヴで行くから、ちょっとギターで来てほしい”というオファーが来たんです」
――すごいですね。LA、NY、そして香港。
「15分から20分くらいの短いセットで、一回こっきりでしたけど本番でした。その年が明けて、スティーヴィーがちょっとしたゲスト・パフォーマンスで、また15分くらいの短い出番のショーがあったんですけど、そのときもギターの仕事をもらって」
――短い出番で最終オーディションをしているような感じですね。
「スティーヴィーって、本当にごまかしが利かない人なんですよ。ギターでも、ホーン、コーラスでも、自分が欲しい音がないと、“そこは違う!”って言うんです。事前にギターパートの入ったライヴ音源を渡されて、それを覚えていっても、“そこはこっちのほうがいいからこうしよう”ってリハーサルで彼が変更して、僕もそれを覚える。その場で臨機応変に対応する必要があるんです。鍵盤でフレーズを弾いてくれることもありますけど、歌で指示が出ることもあるので、それこそ耳コピで覚えて、そっちのほうをやるんです」
――正式なツアー・サポートとしての依頼はどのように来ました?
「香港の仕事をやってから半年くらい経ってからですね。その間も、ちょこちょこと単発で短いパフォーマンスの仕事はあったんですけど、ヨーロッパ・ツアーのときに正式に呼ばれて、初めてフルでスティーヴィーのショーに参加しました」
――それは『キー・オブ・ライフ』再現ツアー?
「いや、そのときはまだ普通のショーでした。でも、普通のショーのほうが逆に大変なんです。セットリストがないので」
――え?ないんですか?
「はい。〈迷信〉とか、だいたい抑えておくべき曲は全部自分でも練習しておくんですけど、他はなにをやるか、音楽ディレクターですら、わからないんです。“とりあえず聴いて、ついて行け。わかんなかったら、弾くな”みたいな(笑)。スティーヴィーがイントロを弾き始めたら、みんな付いていかないといけないんです。あとは、曲のキーがたまに違うこともあるし、転調のタイミングや曲の構成もスティーヴィーがアドリブで変えるときもあるので大変です」
――“聴いて、やるしかない”。すごいですね。それをスティーヴィーほどの知名度と規模でやってるわけだから。
「たとえば〈オーバージョイド〉だったら、1stコーラスがあって、2ndコーラスがあったらそこで転調なんですけど、ショーによっては2ndコーラスをはしょっていきなり転調したりすることもある。それはもう誰にも予想がつかないので、1秒未満くらいのタイミングで判断するしかないんです。スティーヴィーが歌ってるフレーズを聴いてて、“あ、これは転調に行く前のフレーズだ”ってわかったら対応する、みたいな(笑)。おなじ曲をやるにしても気が抜けないし、緊迫感がある。とにかく、そのヨーロッパ・ツアーは僕にとってはいいチャレンジでしたね」
――バンドのレギュラー・ギタリストになるにあたっては、最高の体験だと思います。
「ツアーは12、3ヶ所で、最高に楽しかったですね。スティーヴィー自身が、最高に音楽を愛してる人なんですよ。サウンド・チェックやリハーサルには常にいますし、何もしてないときでも楽器には常に触ってる。みんなもスティーヴィーが欲しいものを汲み取って応えようという気持ちがあるし、その言動には常に気を配ってるけど、ピリピリしてるような空気ではないんですよ。音楽自体もただのラブソングではなく、“争いごとか人種差別をなくそう”というメッセージを込めているので、そういうおおらかな人柄は日常にも出ているという気がします」
――そうなんですね。では、ヨーロッパ・ツアーを終えてアメリカに戻り、いよいよ2013年から大掛かりな『キー・オブ・ライフ』再現ツアーが始まります。
「メインのバンド・メンバーだけで22、23人です。それに加えて、曲によってはゴスペル・クワイアやストリングス・オーケストラが必要なので、それはツアーに行った現地で調達したりして、そういう人たちを全部合わせたら40人以上です」
――すごい……。
「そもそものツアーのコンセプトが、このアルバムに近いというか、アルバムを聴いて育った人たちが目をつぶって聴いたら、本当にレコードの世界に引き込まれるくらいの感じでやろうとしてるので」
――スティーヴィーはレコーディングでは多重録音をよく行ってますし、『キー・オブ・ライフ』にもそういう曲は結構あります。その再現はどういうふうにやっているんですか?
「それを全部カヴァーできる人数のキーボードがいるんです。普段のショーでもスティーヴィー以外にキーボードが2人いるんですけど、『キー・オブ・ライフ』ツアーに関しては、グレッグ・フィリンゲインズというキーボーディストが音楽ディレクターを務めて、もとの曲でスティーヴィーがシンセ・ベースで演奏した曲は、グレッグがシンセ・ベースで再現してるんです。3回目の北米ツアーにはグレッグが参加できなかったんですけど、それまでにディレクションは全部彼が決めているので、彼のパートは録音しておいて、それに合わせて僕らも演奏しました」
――あと、ギタリストとしては〈負傷(コントゥーション)〉という超絶技巧のジャズ・ファンク曲がありますよね。
「あれはなかなか大変です(笑)。チック・コリアにスティーヴィーがインスパイアされて作った曲だそうですけど、常に練習してないと指がついてこないんです。頭で理解してるだけじゃなく、いつも体に入れておかないと。あの曲はメインのフレーズがギターですし、あれを弾くのは本当にチャレンジですね」
――他になにか、自分で弾いていて、『キー・オブ・ライフ』の中で印象的な曲はありますか?
「うーん。たとえば〈サターン〉ですね。あの曲では僕はアコースティック・ギターを弾く役目なんです。シンプルな8ビートの曲で、アコギのパート自体はすごく単純なんですけど、コード進行はトリッキーで、メッセージもすごくある曲。スティーヴィーが込めたメッセージを考えながら弾くと、毎回気持ちがすごく入ります。あと、〈ブラック・マン〉も弾いてて楽しいですね。〈ブラック・マン〉とかではツイン・ドラムになって、僕ともうひとりのギタリストがそのドラム2台に挟まれるセッティングになるんですよ。2人の強烈ドラマーに挟まれて弾いてると、すごくテンションがあがります」
――セットリストがないいつものツアーとはまた違って、曲順が決まってるからこそ山場が次々と来るのがわかるという意味での緊張感ですね。
「ギターやベースが入ってない曲のときは、僕らも弾かないで見てるだけの場面があるんですよ。聴いてるだけですけど、それはそれでまた楽しくて。〈イフ・イッツ・マジック〉では、レコードに入っていたハープの音(※ドロシー・アシュビーによる演奏)をそのまま使ってスティーヴィーが歌うんですけど、それはもう見惚れちゃいますね」
――スティーヴィーと一緒に音楽をやれる時間が永遠に続いてほしい、って話を聞いてるだけでも思います。
「そうですね。とりあえず僕は、スティーヴィーにはできる限りついていきたいです。まあ、それとは別に自分のキャリアというものもあるので、他にも一緒にできる人がいたら常にオープンでやっていきたいとは思ってます」
――たとえば、スティーヴィー以外なら、誰のサポートをしてみたいですか?
「アース(・ウィンド&ファイヤー)ですね。モーリス・ホワイトは亡くなってしまいましたけど、バンド自体は活動してますしね。アースもギタリストは2人いますけど、今のツアーでは、そのひとりはもともとスティーヴィーのギターをやっていた人なんですよ。僕はファンクも好きだし、アースは曲も素晴らしいし、あの人たちと一緒にステージにあがれたら最高に素晴らしいだろうなって思いますね。プリンスもね……、やりたかったですね」
――シーラE.とは一緒にやったことがあるわけですからね。チャカ・カーンもプリンスのオープニングだったわけだし、もしかしたらなにかやれるチャンスはあったのかもしれない。
「いや、じつは話はあったんですよ。なぜならプリンスはアンドリューをえらく気に入ったみたいで、チャカの仕事が終わったらすぐに連絡があったそうなんです。それでアンドリューはそこから何年か、プリンスのベーシストをやりましたよね。その時期にアンドリューから電話がかかってきて、“おまえ、ホロウ・ボディ(※セミアコースティック)のギター持ってるか?”って聞かれたんです。“一応ちょっとしたのは持ってるけど、どうして?”って聞き返したら、“いや、プリンスはテレキャスターを弾いてるから、もうひとりホロウ・ボディのギタリストが必要なんだ”って話で。そんなんだったら絶対ちゃんとしたのを買う!と思ったんですけど、その時点ではまだ本決まりじゃなくて、そのうち本当にやるようなら連絡をくれるということだったんです。まあ、結局それは実現しなかったんですけどね」
――あー、残念。
「今となってはしかたない話なんですけど、こういう話があるのも僕がLAにいるからなんですよ。チャンスはいっぱい転がってるし、そのチャンスが日本やアメリカの他の都市とは比べものにならないくらいデカいので、夢がいっぱいあるんです。NYに住んでる人たちはLAを田舎だってバカにしますけどね(笑)。でも、僕はもう東京も苦手になっちゃったくらいで、LAのレイドバックしてて、広さのある感じが好きなんで。LAが合ってたんでしょうね」
――これからも活躍をされることを期待してます。ぜひ、スティーヴィーのバンドでも来日を!
取材・文 / 松永良平(2016年6月)
最新インタビュー・特集
(2026/02/18掲載)
(2025/12/26掲載)
(2025/12/26掲載)
(2025/11/05掲載)
(2025/10/31掲載)
(2025/10/29掲載)





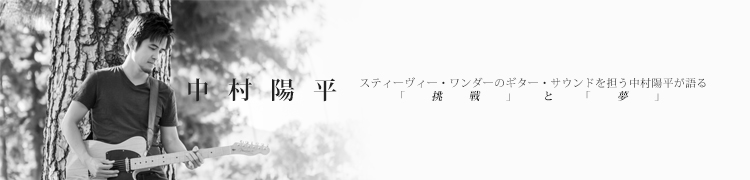






![[インタビュー]<br />精子役で声優デビュー(映画『スペルマゲドン 精なる大冒険』) ニシダ(ラランド) [インタビュー]<br />精子役で声優デビュー(映画『スペルマゲドン 精なる大冒険』) ニシダ(ラランド)](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347057214.jpg)
![[インタビュー]<br />「YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜 ― Tokyo 3 Nights 世界への第一章」から始まる世界への新たな道 YOSHIKI [インタビュー]<br />「YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜 ― Tokyo 3 Nights 世界への第一章」から始まる世界への新たな道 YOSHIKI](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z351006069.jpg)
![[インタビュー]<br />十影とULTRA-VYBEによるマイク・パフォーマンス・プロジェクト『ULTRA SMASH』誕生 [インタビュー]<br />十影とULTRA-VYBEによるマイク・パフォーマンス・プロジェクト『ULTRA SMASH』誕生](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347056275.jpg)
![[インタビュー]<br />「ヤバスギルスキル」30周年。我リヤのニュー・アルバム完成!! ラッパ我リヤ [インタビュー]<br />「ヤバスギルスキル」30周年。我リヤのニュー・アルバム完成!! ラッパ我リヤ](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347055974.jpg)
![[インタビュー]<br />『WBS』のテーマ曲などでおなじみの作曲家 初めての自身名義のアルバムを発表 浅川真洋 [インタビュー]<br />『WBS』のテーマ曲などでおなじみの作曲家 初めての自身名義のアルバムを発表 浅川真洋](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z351005806.jpg)
![[インタビュー]<br />ポプシ30周年!マイペースに活動を続ける彼らが2ヵ月連続7インチを発表 Swinging Popsicle [インタビュー]<br />ポプシ30周年!マイペースに活動を続ける彼らが2ヵ月連続7インチを発表 Swinging Popsicle](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z351005871.jpg)
![[インタビュー]<br />佐藤理とゴンドウトモヒコの新ユニットが、聴覚と視覚を刺激するアルバムを発表 LIG [インタビュー]<br />佐藤理とゴンドウトモヒコの新ユニットが、聴覚と視覚を刺激するアルバムを発表 LIG](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347054553.jpg)
![[インタビュー]<br />デビュー20周年 再始動を告げる新作EP 音速ライン [インタビュー]<br />デビュー20周年 再始動を告げる新作EP 音速ライン](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347054474.jpg)
![[インタビュー]<br />私は私にできることを歌にしていく ゆっきゅんのニューEP [インタビュー]<br />私は私にできることを歌にしていく ゆっきゅんのニューEP](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z351005576.jpg)
![[インタビュー]<br />来日公演を目前に控え、孤高のソウル・シンガーが発表する17年ぶりの新作『PRAYER』 リアム・オ・メンリィ [インタビュー]<br />来日公演を目前に控え、孤高のソウル・シンガーが発表する17年ぶりの新作『PRAYER』 リアム・オ・メンリィ](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z351005547.jpg)
![[インタビュー]<br />今春のカルテットでのツアーを録音した『FRAGMENTS - CONCERT HALL LIVE 2025』を発表 松井秀太郎 [インタビュー]<br />今春のカルテットでのツアーを録音した『FRAGMENTS - CONCERT HALL LIVE 2025』を発表 松井秀太郎](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347054178.jpg)


