注目タイトル Pick Up
公演から1週間で配信されたウィーン・フィルのニューイヤー・コンサート文/長谷川教通
2019年のウィーン・フィルによるニューイヤー・コンサートが96kHz/24bitのハイレゾ音源で聴ける。なんとコンサートから1週間というスピード配信だ。CDやBlu-rayといったディスク・メディアではマスタリングからディスクの製造、ジャケットや解説書の製作&印刷、プラケースへの封入……と、発売するまでにはそれなりの手間がかかるし、製品を配送する時間も必要だ。そうした手間や時間をスキップしてしまうのがネット配信の強み。元日にテレビで観た映像の記憶を想い浮かべながらハイレゾで聴けるなんて、なんて新鮮で幸せな気分。
2019年の指揮はドレスデン・シュターツカペレの主席指揮者クリスティアン・ティーレマンだ。いまや押しも押されぬドイツ音楽界の巨匠が、気心知れたウィーン・フィルからどんな音楽を引き出すか大注目だったが、華麗さや優雅さばかりを印象付ける演奏とは一味違うワルツ。“おー、さすがティーレマン!”といった面白さ。低音セクションをしっかりと鳴らし、リズムやテンポの揺らし方などウィーン訛りというより、あくまでティーレマン流。ずしっと腰の座った正統派の「美しく青きドナウ」は素晴らしいし、「天体の音楽」も最高の演奏だ。ポルカやマーチもたくさんプログラムされており、こちらも軽量級のお祭り気分とは違って、いかにも生真面目な楷書体の演奏で、しかも筆致は太い。「ラデツキー行進曲」ではお決まりの手拍子を、聴衆に向かって大きな身振りで指揮するサービスぶり。まさにホール全体をコントロールしたティーレマン。ニューイヤー初登場の5曲を含め、聴き応え十分なコンサートだ。音質も良いので、少しボリュームを上げて響きを浴びるような感覚を愉しんでほしい。
リッカルド・ムーティ指揮シカゴ響によるライヴ。これぞイタリアン・スピリット! ヴェルディの「ナブッコ」序曲でスピーカーから飛んでくるサウンドのスリリングなこと。イタオペ・ファンにはこのワクワクする高揚感がたまらない。ムーティの情熱的な指揮……といっても勢いだけで突進するタイプではなく、整然と音を組み立てる冷徹さ、その統率力が彼の魅力。合唱が入ってきても一糸乱れぬ演奏の凄さ。ヴェルディの熱血サウンドの次にはプッチーニの「マノン・レスコー」とマスカーニの「カヴァレリア・ルスティカーナ」から有名な間奏曲が続く。美しいけれど情に溺れてしまうことのない弦合奏の巧さ。この一本筋の通ったところがいかにもムーティ節。カラヤンも得意にしていて究極の耽美さを聴かせてくれるが、まったくアプローチが違う。そこが面白い。あなたはどちらが好みですか?
そしてボーイトの「メフィストーフェレ」のプロローグ。シカゴ響の壮大な合奏力が炸裂する。世界中の歌劇場から引っ張りだこのリッカルド・ザネッラートのバスも聴きもの。“Salve Regina!”ではオケと合唱が渾然となってシカゴ・オーケストラ・ホールが揺れるかと思えるほどの響きで迫ってくる。2017年6月のライヴ収録だが、このダイナミック・レンジはハイレゾでなければ再現できないだろう。
冬の夜……そうだバッハの「音楽の捧げもの」を聴こう。1747年のこと、プロイセン王フリードリヒ2世の宮廷を訪ねたバッハは、王からハ短調のテーマを与えられ、その場で3声のフーガを即興で演奏した。さらに6声のフーガを求められたが、さすがに即興では難しく、2ヵ月後に完成させた6声のフーガを含む曲集を献呈したとされる。楽譜にはラテン語で“Regis Iussu Cantio Et Reliqua Canonica Arte Resoluta”とあって、その意味は“カノン様式で解決した王の主題による楽曲と付属曲”となり、ラテン語の頭文字をとってみると、“RICERCARe”。なんと高度な遊び心だろうか。全曲にわたって王のテーマが用いられ、フーガ、カノン、トリオソナタで構成された16作品。しかもカノンは“謎解き”の形式……えっ、謎って? と突っ込まれそう。つまり3声とか4声のカノンなのだが書かれているのは単旋律で、そこに記号が付けられており、演奏者はそれを解決することを求められるというもの。“まあ、解決してみなはれ”とバッハから謎かけされているというわけだ。これぞ晩年のバッハが仕組んだ究極のポリフォニー音楽。演奏楽器の指定も作品の順序も謎! まるで現代音楽の作曲家が実験しているような作品なのだ。
「音楽の捧げもの」には、日本でのバロック音楽ブームの火付け役となったカール・ミュンヒンガー/シュトゥットガルト室内管をはじめ、ピリオド奏法以前から現代まで数多くの名演奏があるが、2016年8月、オランダ・ハーグの旧カトリック教会で収録された鈴木雅明とバッハ・コレギウム・ジャパン(BCJ)のメンバーによる演奏は、長年のバッハ研究と演奏経験の蓄積から生み出された最良の成果と言っていいだろう。
多くの録音が「3声のリチェルカーレ」を冒頭にもってくるが、BCJはまず6曲のカノンからスタートさせる。最初のカノンは鈴木雅明のチェンバロ。繊細を極めた音色が空間を震わせるような音色に耳を奪われる。寺神戸亮のヴァイオリン、菅きよみのフルート、エマニュエル・バルサのチェロ、さらにヴァイオリンとヴィオラを受け持つ山口幸恵も加わり、すばらしい演奏が展開されている。王のテーマが形や色を変化させながら次々と現れる。“これって、現代のミニマル・ミュージックの先駆けかも”と感じさせる。奏者の息遣いが聴こえるような録音の良さもあって、まるでバッハの仕掛けたポリフォニーの迷宮に入り込んでしまったかのようだ。
バイエルン放送管弦楽団の自主レーベル“BR-Klassik”からリリースされたアルバム。早熟の天才メンデルゾーンが12、13歳の頃に書いた作品が収録されている。メンデルスゾーン家はハンブルクの裕福な家庭で、毎週サロン演奏会が催されており、そこで披露するために作曲されたのだろうと言われている。ヴァイオリン協奏曲ホ短調は彼の代表作としてあまりに有名だが、1822年13歳で作曲されたニ短調のほうは、1951年にヴァイオリニストのユーディ・メニューインによって発見されるまで長い間その存在が知られることはなかった。ヴァイオリンのソロと弦楽合奏による作品で、イタリアの合奏協奏曲を思わせるような快活で美しい音楽だ。
一方の弦楽のための交響曲も、おそらくのサロン演奏会のために生み出された作品だろう。1821年から1823年にかけて作曲され、13曲が存在する。このアルバムでは前半の6曲が収録されている。交響曲の習作とされるが、いやいや初夏の日差しを浴びて輝く木々の緑や青々とした草原を吹き抜ける風の爽快さ……そんな溌剌とした旋律はほかに代え難い魅力がある。
2001年からバイエルン放管のコンサート・マスターを務めるグアテマラ生まれのヘンリー・ラウダレスがソロと指揮を担う。2006年から2018年にかけてセッション録音された音源だが、意図的な高域の強調などもなく、響きの豊かさと切れ味を巧みに両立させた素直な録り方で、弦楽合奏ならではの醍醐味が味わえる。
2018年夏のバイロイト音楽祭。プラシド・ドミンゴ指揮する「ワルキューレ」でソリスト・デビューしたメゾ・ソプラノ金子美香の初アルバムだ。OMFレーベルから96kHz/24bitでハイレゾ配信された。彼女がバイロイトで感じたこと。それは観客がワーグナーを心から楽しんでいること。土地に根ざした音楽の力、言葉の力と、そこに流れる“血”のようなものの大切さ。日本に戻ったとき、自分も日本人の“血”を感じさせる音楽表現を求めたい。それが日本の歌曲集に結実したのだ。といっても“日本の郷愁”といったノスタルジックなアプローチではなく、山田耕筰や中田喜直などに加え、武満徹や三善晃、木下牧子など、14人もの作曲家を取り上げて大正から昭和、現代に至る日本歌曲の変遷と魅力を再認識したいという声楽家らしい視点が光る。詩の作者も多彩で、北原白秋や三木露風、江間章子といった定番に加え、萩原朔太郎や金子みすず、岸田衿子、やなせたかしの詩も選ばれている。どこまでも日本語を大切に表現したいという想い。言葉をていねいに発音しながら、素直でしなやかな歌唱がとても快い。飛躍する音型もポルタメントなどほとんど使うことなくスーッと音程が移行する。これが歌謡曲ふうに崩したりベタついた歌い方になるといっきに俗っぽくなってしまうが、彼女の歌はメゾらしく落ち着いた声質で情感豊か。しかも子音がノイズっぽくならない。ただし、たっぷりと倍音が乗ってくるのでスピーカーには手強いソースではある。ぜひトライしてほしい。
“グルーヴ・マスター”屋敷豪太が京都で作り上げたハイブリッド・ポップ文/國枝志郎
80年代初頭にレゲエ・バンド、MUTE BEATへの参加を皮切りに、1986年には中西俊夫率いるMELONに合流、ヨーロッパ公演やアルバムのロンドン録音などを経て渡英、Soul II Soulのプログラミングを担当していわゆる“グラウンド・ビート”のオリジネイターとして名を馳せ、91年にはUKで大ヒットを記録していたバンド、シンプリー・レッドにドラマーとして加入、ワールド・ツアーも行なってバンド人気を支え……とさらっと書いてしまうのがためらわれるほど、アメイジングな活動をワールドワイドに繰り広げてきたのが屋敷豪太その人である。ドラマーというだけではくくれない、さまざまな楽器を操るマルチプレイヤーとして世界中のトップ・アーティストからオファーを受ける存在だったが、10年前に日本に戻ってきて、現在は京都在住なのだとか。2011年にリリースされた前作『In The Mood For Hawaii』(ハイレゾあり。48kHz/24bit)は、ハワイに魅せられた彼がギターをつま弾いた緩いワールド・ミュージック的な要素を色濃く感じさせるインストゥルメンタル・アルバムであったが、この新作『The Far Eastern Circus』は、フィジカルなドラマー、そして優秀なリズム・プログラマーとして、そう、グルーヴ・マスター的な存在としての屋敷豪太を存分に楽しめるアルバムとなっていることがまずはなによりうれしいのである。アルバムは45分と、CD以降のアルバム収録時間がどんどん長くなっていく時代においては意外なほど短いのだが、通して聴くと短いという感じはまったくない。多彩なゲスト・アーティスト(ギターのCharやMondo Grossoの大沢伸一、くるりのベーシスト佐藤征史やディジュリドゥのGOMA、作詞はYMOの歌詞を書いていたクリス・モズデル!)が参加しているこのアルバムは、京都という純日本的な土地(スタジオも京都なのだ)で生み出されたワールドワイドな感覚を持つハイブリッドなポップ・ミュージック。多彩なリズムとベース、そしてなによりも屋敷豪太自身の味わい深い“うた”をぜひハイレゾ(96kHz/24bit)で。
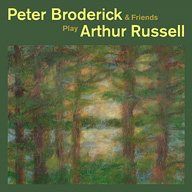
アーサー・ラッセル。アメリカのアイオワ州生まれ。80年代にニューヨークを拠点とし、アコースティックとエレクトリックの両方の視点からジャズ、クラシック、ミニマルな現代音楽、フォーク、ニューウェイヴ、ディスコといった種類の違う音楽を横断、またはつなぎ合わせながら紹介し、現代のあらゆる音楽シーンに足跡を残した希有な音楽家である。1951年に生まれ、92年にエイズの合併症で亡くなったが、その死を『ニューヨーク・タイムズ』は“クラシックとポピュラー音楽を融合させたことで知られるチェリスト/シンガー/作曲家”のそれとして報じたのだった。そんなアーサー・ラッセルの影響を口にするアーティストは引きも切らないのだが、そんな中でも、今回取り上げるアルバムのメイン・アーティストであるピーター・ブロデリックはまさに現代におけるアーサー・ラッセルの正統的な後継者と言っていい。87年生まれのブロデリックは、おもに“ポスト・クラシカル”に属するアーティストとして知られているが、彼の音楽は“ポスト・クラシカル”ということばから想起されるピアノやシンセ、ストリングスなどによるドローンめいたアンビエント音響をベースとしつつも、そこにフォークやインディ・ロックのエレメントをまぶしたもので、ソロやコラボレーション、さらには映画やダンスのための数多くのスコアの提供など、精力的に幅広い活動を繰り広げてきたのだが、デビューから10年を数え、満を持してアーサー・ラッセルの音楽を取り上げたブロデリックの意気やよしという感じで感慨深いものがありすぎる。レコーディングはブロデリックが生まれ、ラッセルの家族が今も住むメイン州で行なわれ、アートワークはラッセルの生涯最後のパートナーだったトム・リーによるもの、そしてラッセルの“未発表曲”(!)のカヴァーが2曲、冒頭と最後に置かれるというスペシャルさ! いまだアーサー・ラッセルの音源のハイレゾ化はならずだが、ブロデリックにとっても初のハイレゾ(44.1kHz/24bit)となるこの音源が多くの人に聴かれてくれたらいつかは……という希望を聴き手に持たせてくれる素晴らしい作品だ。

nouonと書いて“ノウオン”と読む。NO音(無音)、onでもあり、onでもない不可分な領域のことを指しているらしい。脳音? 能音? いや、いろいろな想像をたくましくさせる音楽であることは間違いないのだ。ジャズをベースにしているが、けっしてそれにとどまることのない幅広さを持ったこのユニットは、ヴィブラフォンの山田あずさを中心として日本、アメリカ、イギリスのプレイヤーで構成され、2015年にアルバム『KUU』でデビューした。その後2016年3月にハイレゾマスター、オノ セイゲン(Saidera Mastering)のエンジニアリングによってDSDレコーディングされ、その音源がその年の終わりにハイレゾ(96kHz/24bitおよびDSD5.6)配信されハイレゾ・マニアの注目を集めたものである。このライヴまでの編成は山田あずさ(vib)、ケヴィン・マキュー(key)、ヒュー・ロイド(コントラバスcl)、山本淳平(ds)の4人。通常吹奏楽や管弦楽で用いられるクラリネット(ソプラノcl)より2オクターヴ低い音を出すコントラバス・クラリネットがユニットのボトムを担っていたのがとにかく特徴的だった。しかしその後ロイドが脱退。かわって参加した加藤一平はベーシストではなくギタリストというので新生nouonはどんな音になるのか……と期待していたところに登場したこのスタジオ第2作である。ライヴ盤とこの新作両方に収められた「Pigeon」でその編成の違いがあきらかになるのだが、そのどちらも素晴らしい。あえて言うなら、やはりエフェクターを使えるぶん、ギターの音色の多彩さはやはり武器になるな、という印象はある。今回のアルバムもデビュー作と同じecho and cloud studioでレコーディングされているが、特筆すべきはマスタリングである。ここでもまたハイレゾ・マスター、オノ セイゲンがマスタリングを手掛けているが、彼がオペレートしたのは配信(96kHz/24bitおよびDSD11.2)のほうのみで、CDのマスタリングは同じサイデラの、これまた最近頭角を現しつつあるエンジニア、Tommy Tomitaなのである。なんというぜいたくさ! もちろん今はDSD11.2で聴いているけど、これはCDのほうも気になってしまうなあ……。
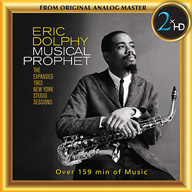
2019年初頭のジャズ・シーンを揺るがすリリースがハイレゾで! ジャズの名盤としてかならず名前があがる『Out To Lunch』(1964年)で知られるアルト・サックス/バス・クラリネット/フルート奏者、エリック・ドルフィーが、『Out To Lunch』の前にあたる1963年に録音した2作品(ジミ・ヘンドリックス死後に粗悪なコンピレーションを多数リリースして悪名高いアラン・ダグラスのプロデュースによる『Conversations』と『Iron Man』)と、同時期の未発表曲を、これまでに多数のジャズ・ジャイアンツの未発表音源を世に送り出してきたゼブ・フェルドマンが編集およびマスタリングを施して159分におよぶ大がかりなセットとして世に送り出したのである。アラン・ダグラス(彼はたしかにジミ・ヘンドリックスの仕事で悪名高いが、いっぽうでビル・エヴァンスとジム・ホールによる名盤『Undercurrent』のプロデュースといった素晴らしい仕事も多数ある)がプロデュースした『Conversations』『Iron Man』は、レーベルがインディであったことも手伝い、音質的にも褒められたものではなかったが、新たにここで素晴らしいリマスタリングが施されて、見違えるような音響に生まれ変わっているのが、CDでも手に取るようにわかるだろう。しかもCDに付く100ページにもおよぶブックレットがまた非常に充実してるときているので、これはCDを買いたくなる種類のブツであることも確かなのだ。しかし、である。このフレッシュな、まるで生まれたての音楽のように聞こえるドルフィーの音楽群を前にして、CDの16bit音響で満足していていいのか? いや、ここはぜひCDも購入してブックレットを熟読しつつ、ハイレゾ(96kHz&192kHz/24bitおよびDSD2.8&5.6)というハイスペックなサウンドにトライしていただきたいと思うのである。傑作『Out To Lunch』に至るエリック・ドルフィーの音楽的軌跡が、DSDの超弩級音響で描き出される至福を感じていただきたい。

まさかの山口美央子、35年ぶりの新作が登場である。80年代に3枚のオリジナル・アルバムと1枚のベスト・アルバムを発表、その後はコンポーザーとしてJ-Popアーティストへの曲提供を行なってきた山口はデビュー当時からシンセサイザーを効果的に生かした音作りの作品を発表し、“シンセの歌姫”とも言われていたのだった。『夢飛行』(80年)、『Nirvana』(81年)、『月姫』(83年)という3枚のオリジナル・アルバムは、和のテイストを感じさせるシンセ・ポップとして高く評価され、その人気は日本だけではなく,世界中に広まっていったのである。この3枚のアルバムが長いこと入手困難であったことで、世界中からリイシューのオファーが引きも切らない状況になり、2017年末にこれらのアルバムに深く関わっていたシンセ・マニュピレーターの松武秀樹のレーベルpinewaveから一挙に紙ジャケット仕様でリイシューされてにわかに山口美央子再評価の熱が高まったのがついこないだのことのように思い出されるが、それが結局こうして35年ぶりのアルバム制作につながったのは、ほんとうに僥倖と言えるだろう。今回のアルバムは山口と松武だけで作られたもので、山口のヴォーカルとサンプリング以外はほぼすべてシンセサイザーで作られているという。土屋昌巳のプロデュースで作られたサード・アルバムにして大名作『月姫』の続編として作られたこの『トキサカシマ』は、“さかしま”という言葉からも想起されるような妖しくも美しいファンタジーの世界を描く音世界に聴き手を誘う。「精霊の森」で始まり、最後は「精霊の森Prologue」で終わるという構成、そう、ラストがPrologueということは、つまりはこの音楽が円環であること(つまり永遠に終わらない)を意味するのか、またすぐに新たな便りが届けられるということなのか、いろいろなとらえ方ができるかもしれない。それにしてもシンセの美しい音色と山口の透明なヴォーカルを、ハイレゾ(96kHz/24bit)で味わえる喜びは大きい。過去の3作もぜひハイレゾ化してもらいたいところだ。

 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。