高音質放送i-dio HQ SELECTIONのランキング紹介番組『「NOW」supported by e-onkyo music』(毎日 22:00〜23:00)にて、この連載で取り上げたアルバムから國枝さんが選んだ1曲を放送します。今月の放送は8月6日(火)の「JAZZ NOW」から。
注目タイトル Pick Up
強靱な意志と感情のほとばしり、ザンデルリンク渾身のショスタコーヴィチ交響曲全集が完結文/長谷川教通
注目すべきベートーヴェン交響曲全集だ。この2組、演奏の方向性は違うものの、ピリオド演奏全盛の時代をくぐり抜け、そのエッセンスを巧みに消化してあらたな演奏スタイルを築いた現代の名演だと言える。どちらも全曲ダウンロードで2,500円というリーズナブルなプライスも魅力だ。1組目はヘルベルト・ブロムシュテットがライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団を振ったライヴで、2014年から2017年にかけて収録されている。彼にとっては2度目の全集録音になる。ブロムシュテットは1927年アメリカ生まれのスウェーデン人。90歳にしてこの演奏! と驚くばかりだ。ゲヴァントハウス管ならではの厚みのある響きを生かしながら、キビキビとオケをドライブする。大袈裟な演出はなく、個性的であろうとするより献身的に音楽に奉仕する姿勢。多くのオケや聴衆から尊敬され親しまれるブロムシュテットの人柄がにじみ出るような演奏は、まさに現代のスタンダードと評価していいのではないだろうか。1970年代後半に録音した全集と比べても、新録音のほうがむしろ軽快で、若々しささえ感じさせる。人に老いあり、仕事に老いなし。
もう1組は、アダム・フィッシャーが首席指揮者をつとめるデンマーク室内管弦楽団による演奏で、2016年から2019年にかけてセッション録音されたもの。これは面白い……なんて言ったらひんしゅくを買うかもしれないが、いやーすごい! アダム・フィッシャーは1949年ハンガリーのブダペスト生まれ。ヨーロッパではオペラ指揮者として知られており、バイロイトやミラノ・スカラ座やパリ・オペラ座でも活躍している。ちなみに弟のイヴァンも有名な指揮者。アダムは、1987〜2001年に録音したCD33枚組のハイドン交響曲全集という大仕事で注目され、続いてCD12枚のモーツァルト(2006〜2013年)が大評判。ヨーロッパのメジャーなオケからもオファーが殺到しているという。そしてベートーヴェンだ。デンマーク室内管はモダン楽器のオケだが、演奏はかぎりなくピリオド・スタイルに近い。といっても、並みのピリオド・スタイルとは訳が違う。テンポの揺らし方が独特で、アタックをかけながら音楽に勢いを与えたかと思うと、穏やかなテンポで叙情的に旋律を奏でたり、ダイナミックレンジの幅も大きく、彼が繰り出す表現には個性的なアイディアが満載されている。そう書くと奇抜で過激な演奏だと思われてしまうかもしれないが、いやいや奇抜なんかじゃない。彼の体内には伝統的な解釈がしっかりと根付いており、それをピリオド・スタイルというツールを駆使して新しく甦らせているのだ。第9番の第4楽章でアルトのパートをカウンター・テノールが歌っても、アダム・フィッシャー流と納得させられてしまう。じつに刺激的で爽快なベートーヴェンだ。
「春」の演奏がスタートする前に、小川のせせらぎと野鳥の鳴き声が聞こえてくる。そうか、それぞれの季節の前に自然音を入れているのか。これはクラシック音楽やジャズはもちろん、自然から湧き出す音の風景をサラウンド収録してきたUNAMAS録音の面目躍如。「夏」には竹富島の海岸に打ち寄せる涼やかな波の音、「秋」には大地を揺るがすような雷鳴と驟雨、「冬」には林を吹き抜ける寒々とした風の音。これまでも似たような「四季」はあったが、これほどリアルに録った自然音を入れた「四季」は初めてだ。
演奏は弦楽五重奏にパイプオルガンという編成の楽譜を用い、パイプオルガンのパートをコントラバスで演奏する。UNAMASのアンサンブルでは中心となってきた東京交響楽団のメンバー、竹田詩織がヴァイオリン・ソロ、田尻順が第1ヴァイオリン、コントラバスを北村一平が担当する。これに第2ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロが加わった6人編成。録音会場は軽井沢の大賀ホールだ。
UNAMASの大賀ホール・プロジェクトでは、その第1弾として2013年に「四季」を取り上げ、斬新な演奏スタイルと録音で話題を呼んだが、今回は大賀ホール・プロジェクトの集大成として再び「四季」を録った。それが「ViVa The Four Seasons」だ。その意気込みは演奏に現れており、竹田詩織のソロがいい。モダン・スタイルの演奏なのだが、ピリオド・スタイルを十分意識しており、大胆でありながら緻密なソロ。アレグロ楽章は活気あるリズムと強弱のコントラスが鮮やか。ラルゴやアダージョ楽章では適度にヴィブラートをかけながら伸びやかに歌っている。
録音はUNAMASならではのリアルな音色とクリアな音像感が際立っている。2chで聴くのもいいが、やはりマルチchが圧巻。今回も奏者はステージ上で円形に立ち、聴き手は円の中央で聴くようなイメージ。前方センターにソロと第2ヴァイオリンの音像が立ち、左に第1ヴァイオリン、右にヴィオラ、背後の左からチェロ、右からコントラバスが低音部を支える。それぞれの音像は明瞭だがけっして刺々しくはならない。各楽器の質感の良さはこれまでのベストだろう。響きの成分はステージ最前面に上方に向けたマイクで録っている。アンサンブルに囲まれる感覚はとても愉しいし、録音メディアでなければ味わえないものだと思う。録音という行為が、いかに作品の表現において、重要な役割を持っているかを再認識させられる。ぜひマルチchの環境で聴いてほしい。
ミヒャエル・ザンデルリンク渾身のショスタコーヴィチ交響曲全集が完結した。彼が生まれた1967年の東ベルリン。東西を分断する壁の存在は堅固だった。旧ソ連はブレジネフの時代。スターリン亡き後、徐々に集団指導体制と文化政策の自由化が進むかと思われたのもつかの間、ブレジネフにより時代は逆戻りしはじめ、1968年のプラハの春での軍による制圧など、共産体制維持のための強権的な支配が強くなっていった。20数年後にベルリンの壁が崩壊するなんて考えることもできなかっただろう。
有名な指揮者である父クルト・ザンデルリンクは生前からショスタコーヴィチとの深い親交があり、ショスタコーヴィチの作品を積極的に演奏していた。そして、よく楽譜を家に持ち帰っていたという。またリハーサルでは、楽譜に仕込まれたさまざまな暗号を読み解き、そこに込められた真の意味を伝えようとしていた。それは体制への批判にも繋がりかねず、反体制として密告されるなど身の危険を伴っていただろう。そんな父の背中を見て成長したミヒャエルにとって、ショスタコーヴィチはきわめて親密な存在であり、それゆえにほかの指揮者とは一線を画する独自の視点をもっていて不思議はない。
彼はベルリンのハンス・アイラー音楽大学でチェロを学び、1987年バルセロナのマリア・カナルス国際コンクールで優勝。室内楽やオーケストラ奏者、ソリストとしても活動し、その後2001年にベルリン室内管を指揮する。ドイツ弦楽フィルやベルリン室内管などを経てドレスデン・フィルの首席指揮者に就いたのが2011年。それからオケのレベルを急速に高め、いまや黄金時代。チェロ奏者らしく、弦楽セクションの表情づけがすごい。第4番の冒頭、まるで大きく呼吸するような弦合奏、第8番の第1楽章は身を引き裂かれるほど痛切な慟哭だ。第7番の第3楽章のヴァイオリンが哀しいほど美しい。それはファシズムや戦争への抵抗と哀しみ、共産主義体制下での息苦しさや孤独、そうした空気のもとで生きてきた人々の息づかいではないだろうか。第1楽章で小太鼓のリズムを背景に管楽器が次々と旋律をつないでいくときの木管楽器の表情は息がつまるほど生々しい。その後の暴力的な大音量の連続も、とてもオケを鼓舞している指揮者の姿には感じられない。その激しさの影にある哀しみに涙しながらタクトを振っているのではないか。15曲の交響曲を貫く強靱な意志と感情のほとばしり、すさまじい表現力に圧倒されてしまう。
クララ・シューマンが13歳で書き始めたというピアノ協奏曲。ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管をバックにピアノを奏でるのはイサタ・カネー=メイソンだ。2018年5月19日ロイヤル・ウェディングでの音楽セレモニーでチェロを弾き、一躍世界中にその名を知られるようになったシェク・カネー=メイソンの姉だ。彼女もBBCヤング・ミュージシャン・コンクール・ピアノ部門のファイナリスト(2014年)となり、王立音楽アカデミーに学んでいる。イサタにとって憧れの存在であるクララ・シューマンは19世紀に活躍した天才ピアニスト。その演奏は同世代のメンデルスゾーンやショパンからも絶賛され、ヨーロッパ中を回って演奏会を行なっていた。また幼少の頃から作曲でも才能を発揮させていたのだが、リストのようにクララの独創性や才能を評価する声もあったものの、当時の音楽界では女性が作曲することに対する偏見が強く、作品も正当には評価してもらえなかった。実際、クララは30代半ばごろに作曲を止めてしまう。
2019年はクララの生誕200周年という記念の年。22歳のイサタがデビュー・アルバムに選んだのはクララ・シューマンだった。このアルバムに収録された作品はクララが10代から20代に作曲した感受性豊かでみずみずしい音楽ばかり。作品7のピアノ協奏曲に作品11と22の「3つのロマンス」、作品14の「スケルツォ」、それに夫ロベルトの歌曲を編曲した「献呈」「月夜」の2曲を挟んでピアノ・ソナタ ト短調というプログラムだ。イサタの音色には芯があってブリリアント。情緒過多な表情づけもなく、むしろストレートな表現がいい。それでいて旋律の隙間からこぼれ落ちる蒼っぽい叙情性が聴くものを惹きつける。20歳でロベルトと結婚し、ピアノに作曲、さらに子育てと、ハードスケジュールをこなしながらも才能を枯渇させることのなかった若き日のクララの姿に想いをはせる。そう、クララ・シューマンには作曲技術とか完成度とか、そんな枠に閉じ込めることのできない感受性の発露があって、それこそが魅力なのだ……と気がつくに違いない。
ジネット・ヌヴーって誰? 若い音楽ファンならそう言うかもしれない。オールドファンにとっても彼女はレジェンドなのだ。1919年生まれ。フランスのヴァイオリニストだ。15歳で出場したヴィエニャフスキ国際ヴァイオリン・コンクール(1935年、ワルシャワ)で優勝。このときの2位が当時26歳のダヴィッド・オイストラフだった。彼女の才能がいかに傑出していたかを物語っている。おそらく誰もが20世紀を代表するヴァイオリニストになるだろうと期待していた。
第2次大戦中は演奏活動を中断していたが、戦後はふたたびステージに戻り、ピアノを担当する兄ジャンとともにフランスからイギリス、ヨーロッパ各地、南北アメリカやオーストラリアにも演奏旅行を行なっている。ところが1949年、パリでの演奏会を終えた1週間後、アメリカへ向かう途中、兄とともに搭乗していた飛行機がポルトガル近くの大西洋上のサンミゲル島山中に墜落してしまう。乗員と乗客の全員が死亡。遺体で発見されたヌヴーは愛器ストラディヴァリウスを両腕に抱え込むようにしていたと伝えられている。あまりにも衝撃的な事故。わずが30歳の生涯を閉じてしまったヌヴーの活動期間は短いものだったが、その演奏は永遠に音楽ファンの心に刻まれることになったのだった。
このアルバムは、2019年のヌヴー生誕100年と没後70年を記念して旧EMIのアーカイヴに保存されているマスターからリマスターされたもの。1938年と1939年、ベルリンで録音した小品とR.シュトラウスのヴァイオリン・ソナタ(トラック21〜30)、1945年にワルター・ジェスキント指揮フィルハーモニア管弦楽団とシベリウスのヴァイオリン協奏曲(トラック1〜3)、1946年にイサイ・ドブロウェン指揮フィルハーモニア管とブラームスのヴァイオリン協奏曲(トラック4〜6)、1946、1948年に兄ジャン・ヌヴーのピアノで小品とドビュッシーのヴァイオリン・ソナタ(トラック7〜20)。いずれもロンドンのアビイ・ロード・スタジオで収録されている。
第2次大戦を挟んだSPレコード時代の録音であり、レトロな音質であることは仕方がないとしても、いま最上の状態で聴けるヌヴーの音楽であることは間違いない。何より戦前の貴重な録音が聴けること、彼女が得意としていたシベリウスやブラームスの協奏曲を収録してくれていたことが嬉しい。聴き手の心の奥底まで浸透するような情念の濃密さ。ブラームスの第2楽章の深々とした弓づかいはもう天才の技としかいいようがない。
Miyu Hosoi『Orb』は、声のみで制作された天国的な音響工作文/國枝志郎

ある日ハイレゾ配信サイトをいつものようにつらつらながめていて目に留まったジャケット。アイドルグループ、あヴぁんだんど(avandoned)の元メンバーで、ついさきごろ脱退した小鳥こたおちゃんじゃないか。いつの間にソロ出したんだ! ……ところがそのジャケットをクリックしてみると、こたおちゃんの名前はそこにはなく、かわりにアーティスト名としてクレジットされていたのはBoris。ヘヴィ・ロック、ストーナー・ロック、ドローン……その音楽性の振れ幅は幅広く、1992年の結成以来、日本だけではなく海外での評価も高いユニットとして30年近く活動を続けてきたBorisの新作だったのか。しかしBorisという名前から想起されるイメージとあまりにも異なるこのジャケットはいったい? とレーベルを見てみると……TRASH-UP!!RECORDSですと!? TRASH-UP!!……アイドルのマネージメントやアルバムリリースを行なっている事務所であり、あヴぁんだんどももともとここの所属アーティストだった。それにしても、このEP。まずこれが〈TRASH-UP!!〉設立10周年記念企画の第1弾としてリリースされたものであること、Borisより結成は1年先輩のCOALTAR OF THE DEEPERSのNARASAKI率いるSADESPER RECORDによるプロデュース楽曲「どうしてもあなたがゆるせない」で始まること、2011年にBorisのエイベックスからのアルバムをプロデュースしたURBAN DANCEの成田忍がまたもプロデュースを手がけたDEEPERSのカヴァー「To The Beach」や、DEEPERSやBorisも影響を受けたと公言する日本のバンド、D-DAYのカヴァー「Peaches」も収録され、またリリース・イベントにはD-DAYのヴォーカリスト川喜多美子もゲスト参加……これはアルバムではなくてあくまでもEPなのに、ちょっと情報量が多すぎてなかなか消化しきれないところではあるんだが、それにしてもここで聴けるBorisのポップさよ! 悪くない! BorisはTRASH-UP!!のアイドル勢(SAKA-SAMA、元THERE THERE THERESのカイ、同じく元THERE THERE THERESの朝倉みずほの新ユニットATOMIC MINISTRYなど)との対バンもありそうなので、新たなファンを獲得することもありそうでなによりだけれど、なんといってもこのシングルがハイレゾ(48kHz/24bit)でリリースされたことは、これまでのBorisのファンのこだわりも大いに刺激しそうな気配。このあとにアルバムも続くという情報もあって、もう期待しかないです。
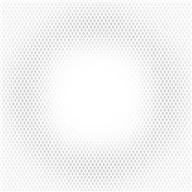
トラック1の「CHANT(聖歌)」(作曲はドラマーの俊英・石若駿!)を再生してみよう。天使的な女声が響きはじめると、あたりのムードが一変するのを聴き手は体験するに違いない。本作は細井美裕というヴォイス・アーティストによるファースト・アルバムである。このアルバムの特徴、それはこの美しい響きを聴かせる6曲すべてが細井自身の声のみで制作されているということ。それだけではなく、たとえば「CHANT」は、エフェクターとしてリヴァーブを使用せず残響のみで制作したのだそうだが、とにかく没入感がハンパないといおうか、どこから響いてくるのかわからなくなるような恐るべき音響工作なのだ。続く5曲も、声のみという制限された響きながら、それぞれ質感や空間性を変えて、天国的というだけではあらわしきれない世界を描き出す。これはボキャブラリー不足という誹りを恐れることなく天国的という言葉を使うしかない音楽なのではないだろうか。その天国性が極まるのはラスト・トラックの「Lenna」(作曲:上水樽力)である。冒頭からシンセサイザーのアルペジエイターのような分散和音が鳴るが、当然これもすべて細井のヴォーカルである。この曲はもともと画像処理の論文などで使用されるテストイメージの“Lenna”(『PLAYBOY』誌1972年11月号に掲載された女性ヌード写真の一部。画像圧縮アルゴリズムのサンプルに使用されている画像データ)のイメージから22.2chのマルチチャンネルフォーマットのために作曲、制作されたデータをヘッドフォンリスニング用にHPLエンコードして2ch再生できるようにしたもの。ヘッドフォンで聴くとハイレゾ22.2chサラウンドが脳内を駆け巡り、見たことのない心象風景が聴き手の中に広がるのである。音楽としても極限の“美”を追求した作品であると同時に、「マルチチャンネルの制作および視聴環境に対する提案と実践をうながすための(実用的な)作品」であるということも重要だ。そしてこの特異な音響工作には、エンジニアである葛西敏彦が重要な役割を果たしていると僕は捉えている。葛西は蓮沼執太、高木正勝、スカート、岡田拓郎(森は生きている)、D.A.N.などを手がける、現代日本の音楽シーンにおける最重要エンジニアのひとりであり、この音質も重要なハイレゾ(96kHz/24bit)アルバムにはうってつけのエンジニアだ。ちなみにこの「Lenna」の22.2chヴァージョンを使ったサウンド・インスタレーションは東京・初台のNTTインターコミュニケーション・センター(ICC)と、山口情報芸術センター(YCAM)で行なわれているとのこと。このハイレゾを聴いて興味を持たれた方は、ぜひ22,2ch音響を現場で体験してみてください。


細井美裕のアルバムから続けてこの“現代音楽”の作品集を聴いてみてほしい。日本のソニーミュージックとロンドンのMinabelの共同制作で近年連続的にリリースされているロンドン在住の日本人作曲家、藤倉大の作品集、その最新作(Minabelは藤倉自身によって運営されているセルフ・レーベル)に収録された10曲のうち、最初の3曲と最後の1曲は“人間の声”による作品であるのだが、通して聴くと器楽だけのトラックが間に6曲も含まれているにもかかわらずこのアルバムは全体が“声”のアルバムだなという思いを強くするからなのだ。ソプラノ歌手の小林沙羅の無伴奏ソロで、ほぼずっと「きいてきいてきいてきいて……」と繰り返すだけの曲「ki i te」のオープニングはショッキングとすら言える作品と思えるが、衝撃はそれでは終わらない。続く「ざわざわ」は、今をときめく指揮者、山田和樹指揮する東京混声合唱団による4部合唱で、ひたすら「ざわざわざわざわ……」と繰り返していくだけ。続編である「さわさわ」も同じ(こちらはマリンバがオブリガード的に挿入されるが)。この2曲はいわゆる日本語の「オノマトペ」(擬音語、擬声語)をもとに作られた曲で、ひたすらそのオノマトペを繰り返していく曲なのだが、このアルバムは(これまでのソニー/Minabelのアルバムはすべてそうなのだが)、作曲家である藤倉大が、すべてのトラックのミックスとマスタリング(ときにはレコーディングまで)を自分自身で行なっている。つまり、作曲家自身が理想とする響きが獲得されているということなのである。ライヴやセッション・テイクをもとに、ときにはリヴァーブを足してみたり、タイミングをほんの少しいじってみたり……それによって、たとえば「ざわざわ」では、「ざわざわ」というオノマトペが16分音符単位で重なり合い、ずれていくことで新たな聴こえ方を獲得したり、ということが起こってくるわけだ。もしかしたらこういう行為は(たとえそれを行なっているのが作曲家本人だとしても)ある種の潔癖主義者からは糾弾されるものかもしれないが、その響きの斬新さに。聴いていていつのまにか“ハマる”リスナーも多いはずだ。ソロ楽器としてはめずらしいチューバやコントラバス、ヴァルブを半分だけ押して息を吹き込むことで得も言われぬ響きを出すホルン、クラリネットや弦楽四重奏といったクラシカルな楽器も、楽器というよりひとつの“声”として一貫した響き(しかしそれはとてもカラフル!)を聴かせるこのアルバム、やはりこの繊細な響きはハイレゾ(DSD2.8および96kHz/24bit)でこそ楽しみたい。

ニュー・マスターズってなに? って絶対なるよね……もう少しわかりやすい名前つければもっと多くの人の目に触れるんじゃね? って思うのは野暮でしょうか……。そんなおせっかいな気持ちも少々ありつつ、これは素晴らしい作品であることは間違いないのでここに紹介したいと思う。ニュー・マスターズはトランペットのキーヨン・ハロルド(ディアンジェロやビヨンセなど数多くのアーティストのライヴや録音に参加し、『The Mugician』というソロ・アルバムも制作)、ギターのギラッド・ヘクセルマン(イスラエル出身で現在はニューヨークで活躍する)、ドラムスのエリック・ハーランド(ジョシュア・レッドマンやアーロン・パークスらとのジェイムス・ファームや自身のグループ、ボイジャーで活動)、キーボードのサリヴァン・フォートナー(ロイ・ハーグローヴのバンドのピアニストでもあった)、ベースのパーニス・アール・トラヴィス(ロバート・グラスパーとの活動で知られる)、アルト・サックスのイマニュエル・ウィルキンス(ジェイソン・モラン、グレッチェン・パーラトといった今のジャズメンからレイラ・ハサウェイ、ソランジュらとも共演)という6人をメンバーとするユニット。この名前を見れば今のジャズを熱く眺めている人なら燃えないはずはないと思うけど、このユニットが取り上げるのがジャズのナンバーではなく、ドレイク、ウィークエンド、ジュース・ザ・ワールド、ケンドリック・ラマー&シザ、チャイルディッシュ・ガンビーノ、カーディ・Bらによる全米でヒットしたナンバー(6曲中、4曲がグラミーノミネート曲!)のカヴァーであることがポイントだ。しっかりしたメロディを持つこれらのヒット・ソングを、即興に優れたジャズ・ミュージシャンが最高の演奏で新たに生まれ変わらせるというコンセプトは、かつてワーナー・ブラザーズ・レコードで先鋭的なジャズの制作にかかわってきたマット・ピアソンが創案したもの。ベテランのアイディアと若き音楽家のタッグによるジャズの“再創造(ReWorks)”は、そのメンバーのセレクトから曲選びまで、きわめてロジカルに考えられた結果といえるだろう。これをハイレゾ(96kHz/24bit)で聴くという行為、ストリーミング時代にあって最高の演奏を最高の音質で聴くという行為こそ、今後の音楽の創造性をさらに高みに押し上げるものだと断言したい。続編も楽しみだ。


1962年に録音された22歳のハービー・ハンコック、初リーダー作にして至高の名作。ドナルド・バードに見いだされ、その紹介で知り合ったブルーノート・レーベルのアルフレッド・ライオンが彼の才能に惚れ込み、この若き才能にリーダー・アルバム録音の機会を与えたのはもうおなじみの話。ハービーのピアノ、フレディ・ハバードのトランペット、デクスター・ゴードンのテナー・サックス、ブッチ・ウォーレンのベース、ビリー・ヒギンズのドラムスというクインテット編成によるこのアルバムは、やはりなんといってもモンゴ・サンタマリアがヒットさせたハービー作の「ウォーターメロン・マン」を冒頭に持ってきたことで、後世に長く聞き続けられるような名作になったと言えるが(いや、ほかの曲も名曲ぞろいではありますが)、それはハイレゾ時代になっても変わらないようで、この『Takin’Off』というアルバムの高音質配信は、じつに3種類のスペックで出ているのである。96kHz/24bitは基本として、さらに上位スペックとなる192kHz/24bitには通常のflacファイルと、コンパクトな容量となるMQAというふたつの選択肢を用意、そしてさらに高品質なDSF2.8MHzというスペックのものがここ数ヵ月で相次いで市場に登場。正直なところ、バラバラ出さずに一度にまとめて出してくれたらと思わずにはいられないし、このすべてのスペックを集めるのは経済的にもなかなかしんどいものがあるだろう。しかし、それぞれのスペックの特色がまたどれも異なる装いを持つことも事実ではあり、たとえばCDでもリマスターされて音が変わるというのは多くの人が経験していることだからおわかりだと思うが、その変化を楽しむのもこうした名盤の場合はありではなかろうか。個人的にはやはりDSF2.8MHzの自然な空気感が素晴らしいと思うが、24bit音源における張りのあるフレディ・ハバードのトランペットの音に捨てがたい魅力があるのも確かである。あいまいですみません(笑)。でもほんと、これは楽しめる変化だ。「ウォーターメロン・マン」だけでも複数ダウンロードして楽しむのもありではないでしょうか。ちなみに同じくらい名盤であるハービーの『処女航海(Maiden Voyage)』なんて、今見たらハイレゾ5種類出ていました。DSF2.8MHzと192kHz/24bitが2種類。96kHz/24bitも2種類。悩みはつきませんな(苦笑)。

 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。