注目タイトル Pick Up
原摩利彦の新作に聞く、静謐さの中に秘められた“情熱”文/國枝志郎
ジェイムズ・ジョイスの小説と同じタイトルを持つデビュー・シングル「若い芸術家の肖像」をして“静かな狂気”をはらむと評されたjanとnaomiによるデュオ・ユニット。フォーキーなテイストとモダンな響きをあわせ持つふたりの音楽は、たしかに危うさも秘めてとても魅力的だ。2018年のファースト・アルバム『Fracture』から2年ぶりとなる今回の新作はぜいたくにも2枚同時発売で、お互いにヴォーカリストとして参加しつつも、1枚はjanのプロデュースによる電子音が飛び交うシューゲイザー・エレクトロな感触の『Neutrino』、もう1枚はnaomiプロデュースによる幻想的な『YES』。ベースにはいつものjan and naomiの哲学を感じさせつつも、装いはかなり違っている。家に閉じこもるような気分のときにはエレクトリック・ピアノやオルガンの響きが穏やかなムードを醸し出す『YES』をメインに聴きたいと思うけれど、対照的に外を向いていきたくなるようなときには『Neutrino』をチョイスしたいと思う……のだが、じつはハイレゾとして配信されているのはnaomiプロデュースの『YES』のみなのである。2枚とも同じレーベルからのリリースなので、アーティストの意向なのかなとも思うけれど、ちょっと残念ではある。jan and naomiのこれまでのディスコグラフィでは、2枚のシングル(「若い芸術家の肖像」「jan, naomi are」)はハイレゾ配信ありだが、Leeloo and Alexandra名義の同名EPおよびファースト・アルバム『Fracture』は16bitのみの配信だった。とはいいつつ、静謐で豊かなスペースを感じさせる『YES』の音楽をハイレゾ(96kHz/24bit)で楽しめるのは幸せなことであることは間違いない。ハイトーン・ヴォイスが漂うように歌う9曲目「Beaut」のコーダにフェイドインしてくるスクラッチ・ノイズでミックスされるわずか40秒足らずのラスト・トラック「□」は、『Neutrino』という異世界へのプレリュードのようにも聴こえたり。

これはまたハイレゾ的にも大注目な作品が登場してきた。前回の当欄で紹介したキース・ジャレットの『サンベア・コンサート』の録音を手がけた菅野沖彦が1971年からスタートさせたオーディオ・ラボ・レコードからリリースされた多くのレコードの中でも、1977年に発売されたこの『ザ・ダイアログ』は、歴史的な高音質録音として当時から多くの音楽マニア、オーディオマニアに注目されたアルバムだった。オーディオ・ラボ・レコードがなくなった後も、SACDとして発売されたり、シングルレイヤー / ダイレクトカットという超弩級仕様のSACD(価格も超弩級でディスク1枚で2万円!)が発売されたりもしており、クラシックやジャズの録音で素晴らしい仕事をしていた菅野沖彦の仕事のなかでも、この作品はとくに現在に至るまで忘れがたい作品と言い切りたい。日本を代表するベテラン・ドラマー、猪俣猛のドラムスにベース(荒川康男)、パーカッション(有賀誠門)、ヴィブラフォン(増田一郎)、フルート(横田年昭)、ギター(横内章次)、テナーサックス(西条孝之助)、トロンボーン(向井滋春)という7種類の楽器が1曲ずつ計7曲、それぞれ即興的に“ダイアログ(対話)”するというシンプルな作品なので、オーディオ的にも非常に興味深い作品だ。バスドラムのズシっとした低音、ハイハットのクリアな金属音、タムのエッジーなサウンド、そしてそれらと対話するように鳴るゲスト陣のスーパーテクニック……もともとはアナログLPで発売されたものだが、やはりCDだとちょっと厳しかったものの、SACDとなったときにはそうそう、これこれ! と納得のいくサウンドになっていたと思っていた。しかし、である。今回のハイレゾ化にあたってはなんとPCM192kHz&96kHz/24bit(WAVおよびflac)、DSD11.2MHz&2.8MHz/1bitという夢のようなバラエティ豊かなスペックでの配信が実現。しかもオリジナル・アナログ・テープからDSDとPCMで別個にマスタリングされたというから、これはとりあえず全種類聴くしかないでしょう。個人的にはやはりDSD11.2MHzのサウンドに痺れてます。

コロナ禍による自宅勤務の日々が増えた人はかなり多いことだろう。そんなとき何を聴くか。元気すぎるロックやJ-POPを聴くのもちょっとなと思ったりするし、かといってズブズブのダークなドローン・ミュージックにハマるのも危険な気がするし……。そんなときこそピタッとハマること間違いなしという一枚が岡田拓郎とduennのセカンド・アルバム『都市計画(Urban Planning)』だ。
岡田が率いていたバンド「森は生きている」は、2013年にファースト・アルバムを出したが、その2年後に突然の解散を発表。以後岡田はソロとなり、2017年にはソロ・アルバム『ノスタルジア』を発表している。もともと音楽性の幅広さはバンド時代から凄まじいものがあった。「森は生きている」のオフィシャル・サイトには、影響を受けたバンド名がずらりと並んでいて壮観なので気になったらぜひ一度見てほしい。ソロはギター・ベースのフォーキーなバンド・サウンドではあるのだけど、ポストロックでドローン・ベースなムードもあって、一筋縄ではいかない作品だった(ちなみにこれもハイレゾ配信されているのでぜひチェックを)。だが、じつはこのソロの前の2016年に、福岡在住の音楽家、duennとの共作アルバム『Mujo』を、アンビエント・アーティストChihei HatakeyamaのレーベルWhite Paddy Mountainからリリースしていた(ハイレゾ配信もあり)。こちらは40分1曲のメディテーション・サウンドで、それまでの岡田を知る者にしてみればちょっと驚きの方向性ではあったのだが、それから約4年後にリリースされたこの顔合わせによるセカンド・アルバム『都市計画(Urban Planning)』は、前作とは打って変わって1分台の小品16曲(トータルタイム25分!)による小さなアルバムとなった。ベースは前作とも共通するアンビエント・タイプなのだが、重苦しさが支配的だった前作と比べると、なんと軽やかなことか。しかも、ここには豊かなメロディがある(duenn曰く、初めてメロディを意識して作ったらしい)。YouTubeにはこのアルバムの3時間に及ぶ拡大敷延ヴァージョンがアップされているが、この作品はやはり高品位なハイレゾ(96kHz/24bit)でゆったりとリピートしながら楽しみたい。ちなみに岡田のヴォーカルが楽しめるミニ・アルバム『Morining Sun』もハイレゾ配信中なので、あわせて楽しんでいただきたい。

これはなんとロマンティックな電子音響だろう! 90年代から活躍する音楽プロデューサー / コンポーザー、CMJKと、エレクトロニクスに抜群の親和性を持つ稀有なヴォーカリスト、ピコリンによる1991年結成のユニット、Cutemen による2年半ぶりの新譜は2020ならぬ『2121』。そう、“いま”ではない。ここで描き出されるのは“100年後にあるかもしれない10 の未来の物語”だ。2016年の再始動アルバム『Humanity』、間髪を入れず2017年に発売された『Exhibition Of Love & Desire』に続く再始動第3弾に当たるこのアルバムが発売となった2020年5月。かつてならSFとしか思われなかった情景がいまや日常となってしまい、まさに“事実は小説よりも奇なり”な日々になっているが、そこに投下されたこの“未来の物語”は、どの曲も眩いばかりのオプティミスティックなヴィジョンに彩られている。たとえばデペッシュ・モードが近年、アルバムでは以前に比べてよりダークな方向にシフトしているのと対照的に、CutemenのサウンドはCMJKが作り出すどこまでもポジティヴでオーガニックな響きと、生気にあふれたピコリンのヴォーカルで聴くものを“キラキラしてあるはずだった未来”へと誘う。もちろん、そこにあるのはむやみやたらな明るさだけではない。かつてデリック・メイやアンダーグラウンド・レジスタンスたちが没落する都市デトロイトでひたすら未来や無限の宇宙にイメージを膨らませていくことで暗い現実からエスケープ(この言葉はけっして悪い意味ではないのだ)してより良い“いつか”を見つけ出したように、Cutemenの音楽もまた、それを聴く人々を“いつかやってくるであろうポジティヴな未来”へとダイヴさせるのだ。こんな素敵な音楽を、これまでよりも高品質で最高にオーガニックなハイレゾ・サウンド(96kHz/24bit)で聴ける僕たちは幸せである。未来はそう、ここにあるのだ。

2020年の初めに、当欄としては初めて原摩利彦のサウンドトラック・アルバム『Mood Hall』を取り上げたが、これまたコロナ禍の真っ最中の6月にリリースされた彼のオリジナル・アルバム『PASSION』の圧倒的に素晴らしいサウンドを聴いて、これまで彼の音楽を当欄で取り上げてこなかったことをあらためて激しく後悔すると同時に、原の代表的な一枚になること間違いなしのこの『PASSION』をハイレゾで楽しめることを幸せに思う日々を過ごしている。幸いなことに、この『PASSION』は好評で、これまでにないほどいろいろなメディアでの露出を目にするようになった。ポスト・クラシカルから現代アート、舞台芸術、映像の世界まで幅広い分野で活躍し、坂本龍一、高谷史郎(ダムタイプ)、野田秀樹らとのコラボレーションなどで注目を集める京都在住の作曲家 / ピアニスト、原摩利彦の、オリジナル・アルバムとしてはピアノ・アルバム『Landscape in Portrait』(2017年)に続くものだが、とにかく今回のアルバムはピアノのサウンドそのものが前作とあきらかに違うのだ。前作に比べて、今回のピアノはとてもダイレクトにスピーカーから飛び出してくる感じがある。ダイレクト、ではあるのだが、不思議なことにその音はとても空間性を持っているのだ。うーん、何が違うのだろうと資料を見ていてハッと気がついた。今回のこのピアノの録音は、エンジニアのzAkが手がけているのか……。RCサクセションやフィッシュマンズ、Buffalo Daughterなどの独特の空間性を生かしたサウンドメイクで知られるエンジニア、zAkのスタジオで録られたというピアノの音は、まさしくこのアルバムのキーポイントだ。それは間違いないのだが、それに絡むフィールドレコーディングのサウンドや和楽器、エキゾチックなサントゥールの響きをこの作品に忍び込ませた原本人によるミックスはさらに驚異的と言わざるを得ない素晴らしさだ。前作(44.1kHz/24bit)も素晴らしかったけれど、さらにスペックアップしたこのハイレゾ(96kHz/24bit)音響が、静謐さの中に秘められた原の“情熱”を見事に聴き手に伝えるのだ。
カウフマンが新たな表現方法を導きだした「オテロ」の決定盤文/長谷川教通
ヴェルディの「オテロ」といえば、テノール歌手なら誰だって憧れる役柄かもしれないが、強靱で英雄にふさわしく輝かしい声を備え、さらに嫉妬にさいなまれて身を滅ぼしていく人間の弱さと感情表現ができる歌手なんて、そうそう出現するはずもない。「マリオ・デル=モナコが最高! それに対抗できるのは、やっぱりプラシド・ドミンゴかな」と多くの音楽ファンが言う。でもデル=モナコは50〜60年代、ドミンゴだってピークはすぎた。ならば現代のオテロ歌手は誰? ずばりヨナス・カウフマンだろう。
いまやワーグナーからイタリア・オペラ、マーラーやシューベルトなど、まさに引っ張りだこのスーパースターだが、ついにカウフマンの「オテロ」が96kHz/24bitでハイレゾ配信された。オケはアントニオ・パッパーノ指揮するサンタ・チェチーリア国立アカデミー管弦楽団&合唱団。2019年の6月から7月にかけて2週間をかけてのセッション録音だ。まず冒頭で炸裂する金管楽器に度肝を抜かれる。これを再生するツイーターの実力が問われる。おまけにドスンと風圧を感じるほどの低音域。猛烈なダイナミックレンジだ。合唱のバランスや歌手の位置関係も周到に計算されている。そこへオテロの第一声! その場の空気を切り裂くようにカウフマンの強靱な“Esultate!(喜べ!)”が響き渡る。この声でオテロ歌いの力量がわかろうというものだ。カウフマンはすばらしい。輝かしいだけでなく、いくぶん重みのある声に陰りも宿る。このシーンに至るまでのパッパーノの追い込みも巧みだ。キプロス島総督の勝利の帰還を迎えるオケと合唱。録音の鮮烈さもあって、血湧き肉躍る迫力……これぞイタオペ!
オテロが難役と言われる理由は、英雄的であると同時にイアーゴの奸計に嵌まって、嫉妬のあまりに身を滅ぼしていく人間の愚かさ、弱さや怒りをどう表現するかが問われるからだ。デル=モナコはあくまで威厳を保ちながらも内面の苦悩に苛まれる表現を聴かせたし、ドミンゴはより人間的で生々しい演技で魅せた。第3幕のモノローグ。カウフマンは、妻の裏切りに迷い苦しみながら、哀しくて寂しくて……そんな孤独な心情を切々と神に訴えつつ、やがて怒りへと変化していく過程を、あえて抑えた表現で描き出しみせた。デル=モナコが作ったスタイルをドミンゴが人間的な感情表現に変化させ、カウフマンが新たな表現方法を導きだしたのだ。歌手、オケ、合唱、録音などすべての要素で最高と評価されるべき決定盤の登場だ。

1977年9月、ロンドンでのセッション録音。アナログ録音がもっとも成熟した時代の名作だ。カルメンはスペインの名花とうたわれたテレサ・ベルガンサ。ドン・ホセは当時30代半ばのプラシド・ドミンゴ。指揮するクラウディオ・アバドも40代半ばで、ミラノ・スカラ座やロンドン響とも良好な関係を築き、彼のキャリアの中でももっとも溌剌としていた時期とも評される。「カルメン」といえば、マリア・カラス / プレートル盤、レオンタイン・プライス / カラヤン盤があまりに有名だ。これまでカルメンのイメージからすれば、清純さや愛らしさよりも奔放で妖艶で危険な薫りを漂わせた女性像が定番のようになってきたし、最近人気の高いエリーナ・ガランチャもそうしたカルメン像からは外れていないと思う。ところが1977年のアバド盤ではテレサ・ベルガンサが歌っているのだ。当時のオペラ・ファンなら“えっ?”と意外に感じたに違いない。ロッシーニやモーツァルトを得意としていたベルガンサのカルメンってどうなの? と。ところが録音された演奏はすばらしかった。序曲からオケは軽快で流麗。やや明るめの響きが快い。ベルガンサは奔放さや妖艶さの際立つカルメンではなく、チャーミングな女性の一面を見せて、それがとても斬新だ。「ハバネラ」を聴いた瞬間、魔性とは一線を画する溌剌とした表現に、目からじゃなくて耳からウロコ! ドン・ホセは若々しい声のドミンゴが聴き応え十分。カルメンの魅力に抗しきれずにズルズルと裏の世界へと引きずり込まれていく軟弱男を巧みに演じている。だって、ミカエラっていう素敵な女性がいるというのに、魔性に目がくらんでしまうんだから……。このミカエラを歌うのがイレアナ・コトルバス。絶品! なんというぜいたくなキャスティングだろうか。シェリル・ミルンズの男っぽいエスカミーリョ。それぞれの個性が絡み合い、オケとコーラスが一体となったすばらしいアンサンブルで物語が展開する。クライマックスにいたっても、ことさらに過剰でドラマティックな仕上げを意図するより、あくまで音楽的な完成度を求めたアバドの指揮には感服するしかない。録音もすばらしいし、アナログ・マスターの状態も良好だったようで、192kHz/24bitの能力が最大限に生かされたサウンドを愉しむことができる。
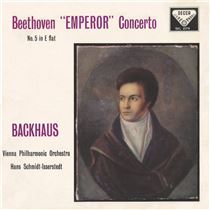
ヴィルヘルム・バックハウスとハンス・シュミット=イッセルシュテット、ウィーン・フィルによる名演だ。いや、そんなことなど今さら言うまでもないだろう。1958、1959年の録音だが、よくぞ録っておいてくれました。バックハウスは1969年7月5日に亡くなる1週間前までステージで演奏し続けたほど、晩年になってもテクニックはしっかりしていた。バックハウスの演奏はテンポを動かさず、感情的な表現も抑えていて、ぶっきらぼうに聴こえるという声もあるが、そんなことはない。微妙にテンポが揺れていて、それが音楽の推進力を生み出していたり、あるいは滋味豊かな表情を作り出したり、硬質な見かけの中に温かみを宿していたり、強靱さの奥に深い心情が感じとれたり、こんなピアニストはほかにはいないし、ベートーヴェン演奏の規範を示したという意味でも偉大な芸術家だと言える。
問題は音質だ。バックハウスが天に召されてから50年。彼の遺した録音が次々とリマスターされている。その音質がどうなのかが気になる。ベートーヴェンのピアノ協奏曲全集は、これまでもLPはもちろんCDでも何度となくリリースされている。それなら……と比較試聴してみる。今回のハイレゾ音源は44.1kHz/24bitだが、「えっ? CDだって44.1kHz/16bitだし、同じサンプリング周波数なんだからそれほど違うはずないでしょ」と言われそう。まず、以前リリースされていたCDをキャプチャーしたwavデータと今回のflacデータを、同じUSB-DACを通して聴いてみた。結果はハイレゾ音源の圧勝。中域から低域にかけての伸びと質感がかなり違う。高音域に関しても雑味感が抑えられ、アンサンブルの見通しがスッキリ。このトーンバランスはどっちが正解なんだろう? と、1963年のLPを盤を取り出して第5番「皇帝」を再生してみると、いやいや驚きだ。ハイレゾ音源とLPのトーンバランスがほぼ同じではないか。これは嬉しい。もちろん解像度は圧倒的にハイレゾ音源に軍配が上がる。内声部のきめ細かな分解や中音域の生々しい質感など、LPの音はベールを何枚か通して聴いているような感触だが、それでもトーンバランスは「これでいい!」と納得させられる。バックハウスの真髄を聴きとるためにも最新のリマスターの意味は大きいと感じさせられる。
ジャン=マリー・ルクレールは1697年フランスのリヨンに生まれ、18世紀のフランスで活躍したヴァイオリンの巨匠。フランコ=ベルギー楽派の創始者と言われることもあるが、このあたりは諸説あってたしかなことは言えないものの、後のフランス・ヴァイオリンの奏法に大きな影響を与えたことは間違いない。現代のヴァイオリン奏法はインターナショナル化し正確無比な技術が求められるけれど、そのような中でもフランコ=ベルギー楽派だけは独自のスタイルと音色を継承しているように思う。イザイやエネスコ、ヴュータンなどの大家や、戦後ではアルトゥール・グリュミオーやオーギュスタン・デュメイが代表格と言えるだろうか。
前置きはそれぐらいにして、ルクレールのヴァイオリン協奏曲を聴こう。作品7と作品10からそれぞれ4曲で、演奏はラ・チェトラ・バロックオーケストラ・バーゼル。スイスのバーゼルといえば古楽専門の音楽大学、バーゼル・スコラカントルムで有名だが、この録音でリーダーとして指揮とソロを担当するレイラ・シャイエーク(以前はシャイエと表記していたが、シャイエーク読む方が正しいようだ)もスコラカントルムで大御所キアラ・バンキーニの薫陶を受け、現在は教授を務めている。新世代のバロック・ヴァイオリンを牽引する名手の一人だ。演奏する楽器はアンドレア・グァルネリによる1675年製のバロック・ヴァイオリンだ。彼女の演奏はほんとにしなやかだ。弓の返しがスムーズで、美しい音色が切れ目なく連なっていく。中でもルクレールの最高傑作と言われる作品10-6のト短調ソナタ。イタリアのコレッリに連なる爽快な技巧とフランスらしい優雅で洗練された音楽のなかに見え隠れするルクレールならではの魅力ある表現が聴きものだ。日本では演奏される機会が少ないのが残念だが、これはすばらしいアルバムなので、ぜひ手元に置いてほしいと思う。

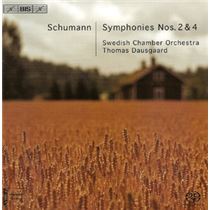
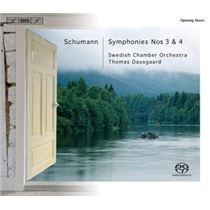
ハイレゾの配信サイトを探っていると「あれっ、こんな録音見落としていたかもしれない」と気がつくことがある。今回はトーマス・ダウスゴーの指揮した作品だ。ダウスゴーはデンマークのベテランだが、なぜか日本での評価がそれほど高くない。しかし2019年に宮田大のチェロでエルガーのチェロ協奏曲を振った録音のすばらしさ。この指揮者を見直した音楽ファンも多いのではないだろうか。そのダウスゴーがスウェーデン室内管弦楽団の首席指揮者だった頃に同楽団を振った録音がBISレーベルからハイレゾ配信されている。2000年代前半の収録であり44.1kHz/24bitなのだが、さすが音質で定評のあるBIS録音。小編成ならではの楽器の明瞭な配置と多彩な動きが手に取るように聴こえてくる。プログラムはベートーヴェンやシューベルト、ドヴォルザークなど多彩だが、中でも注目すべきはシューマンの交響曲。第1番から第4番に第4番のオリジナル・ヴァージョン、「ツヴィカウ交響曲」の第1楽章、それにあまり聴く機会のない序曲なども演奏されている。シューマンの交響曲では楽器が重なっていることが多い(同じ旋律を複数の楽器が演奏する)とか、同時に鳴っている楽器が多くて響きが混濁するといった指摘……つまり管弦楽法が下手だと言われる。そうかな? たしかに、これまでの巨匠たちの演奏を聴くと分厚い響きを何とか整理し、アクセントを工夫したりして音楽から深みと躍動感を引き出そうとしてきたように思うが、最近ではオケの編成をコンパクトにして、その結果たとえ響きが薄くなろうとも内声部を明確に聴かせることで、シューマンの管弦楽法の良さを見直そうとする指揮者も出てきている。それはピリオド・スタイルの台頭が背景にあるだろうと思うが、ダウスゴーの解釈もまさにその典型的なもの。まずシューマンではヴァイオリン両翼配置は必須。そしてヴィオラなど内声部は和音の一部ではなく、それぞれのパートが旋律を奏でているので、その出入りをコントロールして響きのコントラストをスッキリさせる。テンポを速めに設定し、しかもアタックには適切な変化をつけて躍動感を出す。喩えてみるなら、大河のようなスケール感ではなく中流域の面白さ! 淀みがあったり、幾重にも渦が巻いていたり、岩に当たる流れの変化が多彩で、流れの緩急で表情を変えるなど、そんなシューマン独特の面白さを聴きたい! そう思って第3番「ライン」の第2楽章を聴くと、いままでのつまらない音楽だなーなんていう先入観が一変する。ダウスゴーはいい。伸縮自在の弦と木管楽器の掛け合い、第1番「春」のブラスの鄙びた感じなど「これがシューマンか」と聴き入ってしまう。響きは薄くなるとはいえ、低弦を十分に鳴らし、録音でもシッカリととらえられていて勢いもある。ぜひ音楽ファンのライブラリーに加えてほしい。第4番などはちょっと手を加えすぎで、むしろオリジナル・ヴァージョンの方がシューマンらしいかもしれない。

 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。