ラッパ我リヤが、通算10枚目となるアルバム『不屈の男達の物語〜The Story Of Indomitable Men〜』をリリースした。30年以上にわたり日本語ラップシーンをサバイブし続けてきた彼らは、時代や流行とときにシンクロし、ときに抗いながら、ブレのない押韻と数々のパンチラインという、ストロングスタイルを貫いてきた。その一貫した姿勢こそが、ほかの誰にも代替できない確固たるオリジナリティとなり、ラッパ我リヤの存在意義をシーンに深く刻み込んでいる。
そして、その“不屈”の精神が濃密に封じ込められた本作は、Mr.Qが語るように、過去の蓄積と現在のリアリティが結びついた「ニュー・クラシック」としてリスナーのもとに届けられるはずだ。今回は、ULTRA SHIBUYAにて行なわれた公開インタビューの模様を再構築し、テキストとしてお届けする。
――まず、ニューアルバム『不屈の男達の物語〜The Story Of Indomitable Men〜』という今回のタイトルは、どのように名付けられたのでしょうか?
山田マン「我リヤのアルバムには〈イントロ〉と〈アウトロ〉に加えて、〈中トロ〉があるんですが、今回もその〈中トロ〉を制作していたときに、格闘技番組にあるようなナレーションを取り入れたいなというアイディアが浮かんで」
――観客を煽るようなメッセージというか。
山田マン「そこで“これは不屈の男たちの物語である”という言葉を閃いて、それをタイトルにも引き継いだ感じです」
――「不屈」は我リヤがずっと提示しているテーマだと思いますし、それがタイトルになるのは必然性も感じました。
Mr.Q「デフォルトがそこなんだと思います。諦めないというか。イケメンじゃないのにずっとモテてきたのは、その諦めない気持ちゆえなんじゃないかな(笑)。まあ、気持ちとしてはプロレスラーが必殺技を繰り出すようなノリですよね。このオリジナルな技でもう一回盛り上がって、という。その意味でも、今回は“我リヤのマスターキー”みたいな部分を、あえて狙って打ち出しています。“変わらないよね”と言われることも多いけど、“変わらない”のもじつは結構大変なこと。今回でいえば、90'sフレイバーのような部分は、あえて入れている。その意味でも“ニュークラシック”ということは意識していました」

――制作的にはいつ頃から?
山田マン「今年たっぷり使って制作した。最初は“介護をしている人に対する応援歌を作りたいね”というアイディアから、〈ダイヤ〉を作ったんですよ。それを単曲で配信しようかなと思っていたんだけど、Qが“アルバムでみんなに届けたほうが我リヤらしい”というアイディアを出して、そこからしっかり10枚目のアルバムとして形にしようと思ったんだ」
――「ダイヤ」はお話にあった通り、介護や仲間との死別といった、我リヤ世代にとって非常にリアルなテーマが描かれています。
Mr.Q「介護はもちろん、同級生や仲間が相次いで亡くなったり、そういうことが現実として立て続けに起こる年齢で」
山田マン「ずっと“ヤバスギルスキル”とか言っていた俺たちが、いまの年齢になって世の中に言えることは何だろう、というのが制作のきっかけですね。家族の介護というのは、まったく自分たちの世代にとっては当たり前の話。実際、Qも親父さんを介護しているし、トシも両親と生活するために地元に戻ったりしている」
Mr.Q「ヘルパーの方の多大なる協力には、本当に感謝の気持ちがありますね。それを曲にも落とし込もうと」
山田マン「もっと遡れば、『MASTERPIECE』(2009年)以降しばらくアルバムを出していなかった時期は、僕自身が介護や見送りといった個人的な事情が重なって、音楽に純粋に気持ちが向かなかったり、創作意欲が減退してしまっていた。介護というのは、それくらいヘヴィなことなんです。そこでメンバーにも迷惑をかけてしまった。そして、そういったヘヴィな環境や心境は、なるべく人に見せないように頑張ってきたんですが、いま思えば、もっと正直に周りに言えばよかったのかなとも思います」
――吐き出せなかった理由は何だったのでしょうか。心配をかけたくなかった、ラッパーとして言うべきことではないと思ったなど、さまざまな要素があったと思いますが。
山田マン「そのすべてかもしれないですね。やっぱり“玄関を出たら山田マンとして生活すべき”と思っていたんですよ。だけど、その時期は実生活を引きずってしまって、明るくバカなことが言えなくなっていた。でも、そういう環境を経験した自分たちだからこそ、言えることがあるんじゃないか、というのがこの曲を作ったきっかけです」
DJ TOSHI「自分たちのような年齢になると、より深く感じられることもあるし、ベテランだからこそ発信できることも、届けられるなら届けたい。ヒップホップ自体の幅も、そこで広げることができると思うんです。もし、内容的に少しヘヴィすぎると感じたら飛ばしてくれてもいいけど、それでも一度は聴いてほしい」
山田マン「この歳までやっている理由がここにあるし、それを表現しないと自分たちが作品を作る意味が薄れてしまうと思うんです。若い子たちが歌えないようなことでも、俺たちだったらラップにできるし、曲として発表できるから」


――今作は、ラップ、トラック、スクラッチと、作品のすべてを3人のみで制作されていますね。
山田マン「ジャケットのアートワークも、今回はQに頼んで。Qの母ちゃんが画家だったんですよ。『前代未聞』のアートワークに使っている絵が、まさにそれで。それもあったので、“Q、ちょっとジャケットやってみてよ”って(笑)」
――ジャケットは20年ほど前の、走馬党のフルメンバーが描かれていたイラストを再構築したものがベースになっています。
Mr.Q「KIIROSANBAN氏が描いて当時Tシャツにもなったイラストが原画ですね。それを自分が手描きでクリエイトさせていただきましたね。今回は“走馬党の残党”というリリックもあるし、ラッパ我リヤのアルバムなので、3人にクローズアップして。さらに、そこにメッセージやタイトルを手書きで加えてクリエイトしたんです。手書きの部分も、たとえばChatGPTのようなAIに読み込ませて書き直してもらえば、綺麗に表現してもらえると思う。でもそれをやったら、今回のジャケットの感触は出ないと思うんですよね」
山田マン「そうやって、自分たちの感覚をあらためて形にしたことに意味があるのかなって。その経験によって、韻とは何なのか、デザインとは何なのか、お客さんとは何なのか、ということが、10枚目にして全部わかったようなアルバムですね」
――自分たちを再確認するような作品になった、と。
山田マン「コンピレーション『悪名』に収録された〈ヤバスギルスキル〉でデビューしたのが1995年。1996年の『続・悪名』に収録された〈せんれい〉が我リヤの第2弾だったんですが、じつは同じ日にレコーディングしているんですよ。8時間スタジオを押さえてもらって、4時間で〈ヤバスギルスキル〉、残りの4時間で〈せんれい〉を録った。〈せんれい〉はDJ KENSEI(Indopepsychics)のプロデュースだったんですが、その後、アルバム『SUPER HARD』(1998年)を作るときに、KENSEIくんに“アルバムを作るなら、なるべく自分たちで作ったほうがいいよ”と言われたことをひさびさに思い出して。それで今回は、その原点的な部分に戻って、我リヤの3人だけでアルバム全体を作ろうと思った。〈ヤバスギルスキル12〉にフィーチャリングが入っていないのも、ルーツに戻るというイメージでしたね」
――確かに「part.2」でのSKIPPを皮切りに、走馬党のメンバーやILL-BOSSTINO、MC仁義、韻踏合組合など、前作の「ヤバスギルスキル11(feat. R-指定, KZ & KBD)」に至るまで、「ヤバスギルスキル」シリーズは、基本的に客演を迎える構成でした。
山田マン「その意味でも、30年ぶりにまた3人でやってみようと思った結果だよね」
Mr.Q「フィーチャリングを招くと、ほかのパワーが入るから、わかりやすくはなるんですよね。でも今回は、2人のヴォーカルと一人のターンテーブルで、全部伝えていくということをやりたかった」
DJ TOSHI「3人で作ることで、より作品に集中できたと思う。自分たちのパワーを、どこにどう落とし込むかだけを考えればいいというか」
――よりピュアな方向に向かったというか。
DJ TOSHI「まさにそうですね」

――「イントロ」には「よくぞここまで」というナレーションが入りますが、10枚もアルバムを出すというのは、並大抵のことではないと思います。
DJ TOSHI「続けてきた中で、自然に10枚目にたどり着いたという感覚です。最初からこうなるとは思っていなかったし、ここが目標だったわけでもない。ただ、流れの中で積み重ねてきたら、結果として10枚目になっていた」
山田マン「〈ヤバスギルスキル〉のときに、これからアルバムを10枚出すなんて、想像もしていなかった。でも、止めるつもりもまったくなかった。コロナ禍でライヴができなかった時期や、計画通りに進まない時期もあったけど、それでもラッパ我リヤを止めるという選択肢は、これっぽっちもなかったです。それよりも、“次はどんな作品を出してやろう”“どんなでかいことをやってやろう”“どう食い込んでやろう”ということを、ずっと考えてきた」
Mr.Q「枚数で言えば、もっと出していてもよかったかもしれないですけどね。活動の期間が空いた時期もあるし」
山田マン「『ラッパ我リヤ伝説』(2000年)を出していた頃は、年に1枚くらいのペースでリリースしていたんです。でも、当時のレーベルの人から“そんなに出していたら飽きられますよ”と言われたことがあって。それで、そんなものかな、と思って出し控えた時期があった。でも、もっとそこで戦えばよかったなっていまなら思う。人生で唯一、後悔していることがあるとしたら、その意見を取り入れてしまったことです」
――あの時期は、リアルスタイラといった別ユニットや、Qさん、山田マンさんのソロや客演もかなり多かったですよね。だから、そのペースでも出し控えていたんだ、という印象があります。
山田マン「もっとバンバン出しておけばよかった。昔、何かのインタビューで“怖いことはありますか?”と聞かれて、“別に怖いことなんかない”と答えたことがあったんだけど、じつは“音楽を嫌いになったらどうしよう”という恐怖は、ずっとあったんですよ。音楽を聴きたくなくなったらどうしよう、作れなくなったらどうしようという不安。でも、我リヤとして10枚もアルバムを出しても、まだ音楽が好きでいられる。だから、大丈夫かなって思えましたね」

――アルバムの2曲目は「群雄割拠」です。このテーマを形にした理由は?
Mr.Q「それぞれの武将が、“ここからここは俺の領地だろ!”“うちは何万石じゃい!”と争っていたように、ヒップホップも“ここはうちのクルーが”“あそこは何万枚売った”って張り合っていた時代が、90年代から00年代にはあったんです。戦国時代は、その群雄割拠の中で日本という国が成り立っていったと思うし、ヒップホップシーンも、“お前はすげえな”“俺たちはこれができる”という切磋琢磨の中で、日本のヒップホップが形作られていったと思う」
――そこに相似形がある、と。
Mr.Q「そういう構図を、あらためて表現したいと思ったときに、このフレーズが浮かんできたんです。いまもシーンがバラバラかと言えば、けっしてそうではなくて、自分の砦、自分の城を持った連中が、群雄割拠してシーンを形成している。そこは昔から変わらないと思うんです。だから、“ひとつのまとまりである”ということを、どう表現するかを考えた。若い連中も俺たちにラブをくれるし、俺たちだって尊敬しているアーティストはベテランでも若くてもいる。そういう関係性も〈群雄割拠〉のメッセージには込められていますね」
――今回は公開インタビューということで、客席からも質問を募っています。まずは「〈ヤバスギルスキル12〉のMVの撮影地を教えてください」という質問です。
Mr.Q「理容師のコンテスト『東京BARBERS トリコロールナイト』というイベントがあって、そこにラッパ我リヤもライヴで参加させてもらったり、“東京BARBERS feat. ラッパ我リヤ”として〈All Generation〉という曲を作ったりしてきた流れがあるんです。その延長で、渋谷HARLEMで開催された『東京BARBERS トリコロールナイト』で〈ヤバスギルスキル12〉を披露したときの映像と、ストリートでの撮影を組み合わせて、監督のYANZAに最高に格好よく仕上げてもらいました」
――「今回のアルバムでお気に入りのパンチラインは?」。
Mr.Q:「〈群雄割拠〉で出てくる“高山とドン・フライ”ですね」
――2002年の『PRIDE.21』での、高山善廣とドン・フライの一戦ですね。
Mr.Q「あのノーガードで、お互いに拳を打ち合う試合は、とにかく強烈な印象が残っているし、盛り上がりもとてつもなかった。その意味で、“いま観てもすげえと思わせるエンタテインメント”の比喩として、あのイメージをリリックに落とし込みたかった。〈ダイヤ〉の“向こうに旅立った風見鶏”という一節も、自分ではパンチラインだと思っています。あとは、山田マンの“ミスター女子プロ しのぶ神取”」
山田マン「あれは晩酌中に浮かんできた(笑)。前後は、そのワードを中心にリリックを組み立てていったんですよ。思いついちゃったら、もうしょうがないですよね」
――続いての質問です。「QさんがMCバトルに出続ける理由は何ですか?」。インタビュー前日にも、サイプレス上野さん主催のバトル『ENTA da STAGE』に出場されていましたね。QさんはB-BOY PARKのMCバトルから出場されているので、キャリアとしてはシーン最長クラスだと思います。
Mr.Q「『フリースタイルダンジョン』にも出させてもらったけど、じつはまだ一度も冠を取ってないんですよ。だから、いい加減俺に勝たせろ、俺をチャンプにさせろ、という気持ちです。どんなバトルに出ても、基本的には俺が一番年上。だけど、そこで負けるととんでもなく悔しいし、本当にムカつく。それだけ燃えるし、気合も入る。昨日もMEGA-Gには勝ってリベンジできたんだけど、黄猿には負けた」
――黄猿さんは、キャリアも含めてMCバトルの猛者ですね。
Mr.Q「でも、ボコボコにされたわけじゃなくて、前半は俺が優勢だったのに、後半でひっくり返されたんです。最後まで殺しきれなかった自分の甘さにも腹が立つし、やっぱりこれは、冠を取るまではやめられねえなって。イメージともしても『ENTA da STAGE』で勝って、年始の『KING OF KINGS』の本戦で優勝して300万をもらう予定だったんです。それくらい本気でやっている。MCバトルって、めちゃくちゃ緊張するし、汗もかくし、負けたら本当にムカつく。でも、だからこそ、納得いくまで絶対にやめない。それに、ライミングの重要性や、リスナーの耳を鍛えてきた礎を作ってきたのは、俺たちだと思っている。だからこそ、そこで称号を取らない限り、絶対に終われないんです」

――続いての質問です。「山田マンさんはギターを弾かれますが、ほかにも楽器は演奏されますか?」
山田マン「楽器は、ギターとピアノとベースですね。吹く楽器は、全然ダメです(笑)」
――「〈ヤバスギルスキル〉は“毎日働くフリーアルバイター/ムカつくとすぐ切れるストリートファイター”というリリックで始まりますが、これは30年前の生活を反映していますか?」という質問です。
Mr.Q「もう、めちゃくちゃリアルだったよね」
山田マン「毎日バイトして、ムカついたら喧嘩して、っていう。それ以上でも、それ以下でもない(笑)」
――“空いた口がふさがらない”ですね(笑)。
Mr.Q「さっきの楽器の話ともつながるけど、当時、山田マンはMac(マッキントッシュ)の仕事をしていたんだよね。だから、レコーディングの現場にもMacを持ち込んでいた」
――かなり早い時期ですよね。
Mr.Q「早い早い」
山田マン「ハウスやテクノのビートメーカーが、パソコンの画面上にシーケンスを表示して、それをコピー&ペーストして制作しているのを見て、衝撃を受けたんですよ。それを、いち早く取り入れた感じです」
――最後の質問です。「現在の日本語ラップを取り巻く環境を、どう見ていますか?」
Mr.Q「CDやレコードがなくても、スマートフォンひとつで何百万、何千万という楽曲が聴ける時代ですよね。それでもライヴ・シーンには人が集まって、その規模はどんどん大きくなっている。ヒップホップも同じで、〈ヤバスギルスキル11〉を一緒に作ったR-指定は、Creepy Nutsで東京ドームを埋めて、海外でもライヴをしている。ZORNだって、インディでアリーナを埋めている。そういうシーンの発達や業界の変化の中で、じゃあ次はどう攻めるかというのは、みんなそれぞれ知恵を絞っていると思う。その中で俺たちも、“あと何本、火柱を立てて死ねるんだ?”って考えている。そのための新しい必殺技が、今回のアルバムにはあると思っています」
DJ TOSHI「ヒップホップが、ユースカルチャーの真ん中にある時代ですよね。だから、若いラッパーの言葉は若い人に刺さるし、自分も昔はそうだった。その一方で、いまの自分たちの言葉は、子育てが一段落したり、生活に余裕ができて、もう一度音楽に向き合えるようになった人たちにも、聴いてほしいと思っています」
山田マン「自分は54歳だけど、誰よりもヒップホップビギナーだと思っているし、常に新しいものを作りたいと思っている。若いとか年寄りとかじゃなくて、“いまの生のヒップホップ”を形にしたい」
Mr.Q「俺の意見としては、世代間の壁すら破壊したいと思ってる。“いよいよ壁はなくなるぞ”と〈Deep Impact〉で歌ったけど、その気持ちはより深くなってる。フレッシュな作品が出て、新しいガジェットが生まれて、これまでとは違う情報を知って、それでいろんなアートフォームが新しく生まれてきている。だから、俺らの楽曲は同世代にだけ刺さればいいんじゃなくて、20代や10代にもぶっ刺したいと思ってる。その意味では、その世代の壁を壊す方法はなにか、というのを2026、2027を見据えて考えているし、その方法を模索してる。頭の中なんてそんなに変わらないんだよ。20歳のときとじつはそこまで変わってない。でも、時代が変わっていく中で、そこに対応して、さらに追い越していくぐらいを考えないと、リスナーを引っ張り上げることはできないし、自分自身が走り続けられない。そこで格好いい先輩にならないといけないと思うんだよね。そういう意味では格好いいことをやり続けて、新しいデリバリーを生んで、もっと進化系の姿を見せないといけない。そして、それができる自信がある」
――原点回帰でありながら、その先も見据えている、と。
Mr.Q「それじゃなきゃ、面白くないでしょ。プレッシャーではあるけど、自分たちのアートをちゃんと出せば、できると思っている。今回のアルバムを聴いて、“古い”と思う人がいたら、その答えはこれから出すから、少し待っていてほしいですね」
取材・文/高木“JET”晋一郎
撮影/YANZA
撮影/YANZA
最新インタビュー・特集
(2025/12/26掲載)
(2025/12/26掲載)
(2025/11/05掲載)
(2025/10/31掲載)
(2025/10/29掲載)





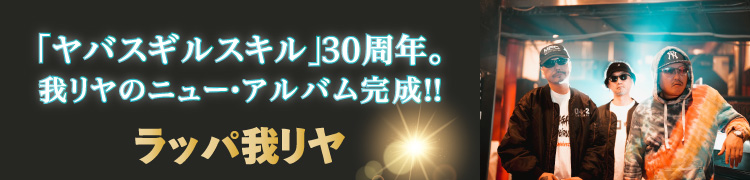


![[インタビュー]<br />「YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜 ― Tokyo 3 Nights 世界への第一章」から始まる世界への新たな道 YOSHIKI [インタビュー]<br />「YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜 ― Tokyo 3 Nights 世界への第一章」から始まる世界への新たな道 YOSHIKI](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z351006069.jpg)
![[インタビュー]<br />十影とULTRA-VYBEによるマイク・パフォーマンス・プロジェクト『ULTRA SMASH』誕生 [インタビュー]<br />十影とULTRA-VYBEによるマイク・パフォーマンス・プロジェクト『ULTRA SMASH』誕生](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347056275.jpg)
![[インタビュー]<br />「ヤバスギルスキル」30周年。我リヤのニュー・アルバム完成!! ラッパ我リヤ [インタビュー]<br />「ヤバスギルスキル」30周年。我リヤのニュー・アルバム完成!! ラッパ我リヤ](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347055974.jpg)
![[インタビュー]<br />『WBS』のテーマ曲などでおなじみの作曲家 初めての自身名義のアルバムを発表 浅川真洋 [インタビュー]<br />『WBS』のテーマ曲などでおなじみの作曲家 初めての自身名義のアルバムを発表 浅川真洋](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z351005806.jpg)
![[インタビュー]<br />ポプシ30周年!マイペースに活動を続ける彼らが2ヵ月連続7インチを発表 Swinging Popsicle [インタビュー]<br />ポプシ30周年!マイペースに活動を続ける彼らが2ヵ月連続7インチを発表 Swinging Popsicle](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z351005871.jpg)
![[インタビュー]<br />佐藤理とゴンドウトモヒコの新ユニットが、聴覚と視覚を刺激するアルバムを発表 LIG [インタビュー]<br />佐藤理とゴンドウトモヒコの新ユニットが、聴覚と視覚を刺激するアルバムを発表 LIG](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347054553.jpg)
![[インタビュー]<br />デビュー20周年 再始動を告げる新作EP 音速ライン [インタビュー]<br />デビュー20周年 再始動を告げる新作EP 音速ライン](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347054474.jpg)
![[インタビュー]<br />私は私にできることを歌にしていく ゆっきゅんのニューEP [インタビュー]<br />私は私にできることを歌にしていく ゆっきゅんのニューEP](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z351005576.jpg)
![[インタビュー]<br />来日公演を目前に控え、孤高のソウル・シンガーが発表する17年ぶりの新作『PRAYER』 リアム・オ・メンリィ [インタビュー]<br />来日公演を目前に控え、孤高のソウル・シンガーが発表する17年ぶりの新作『PRAYER』 リアム・オ・メンリィ](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z351005547.jpg)
![[インタビュー]<br />今春のカルテットでのツアーを録音した『FRAGMENTS - CONCERT HALL LIVE 2025』を発表 松井秀太郎 [インタビュー]<br />今春のカルテットでのツアーを録音した『FRAGMENTS - CONCERT HALL LIVE 2025』を発表 松井秀太郎](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347054178.jpg)
![[インタビュー]<br />友成空の大ヒット曲「鬼ノ宴」が湖池屋とコラポレーション クセになる辛さの「ピュアポテト 鬼ノ宴」誕生 [インタビュー]<br />友成空の大ヒット曲「鬼ノ宴」が湖池屋とコラポレーション クセになる辛さの「ピュアポテト 鬼ノ宴」誕生](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z351005417.jpg)


