2019/03/20掲載
いまはなき異色のレーベル「ショーボート」の、後期に生まれた代表作ということになるのだろう。『上海バンスキング』。1979年の初演以来、ロングランしていた自由劇場による音楽劇、そのオリジナル・キャスト・アルバムは、いわゆる“小劇場”ブームの象徴であると同時に、“役者が演奏までこなした”点において、当時としては希少な成功例。今回の取材相手である徳光英和は、トリオ・レコード在籍時このアルバムの制作を手がけた、当時の担当ディレクターだ。劇団としての性格は大きく異なるものの、こちらも大ブレイクする分岐点となった劇団四季のミュージカル〈エビータ〉のアルバム化を担当されてもいる。〈上海バンスキング〉初演から40年、当事者でなければ知り得ない、貴重な制作裏話を語ってもらった。
祝『上海バンスキング』40周年・再発
劇団青年座・樋口康雄
「三文オペラ[+ 2]」
劇団青年座・樋口康雄
「三文オペラ[+ 2]」
――徳光さんがトリオにいらしたのは。
「上海バンスキングが80年ですよね(アルバム・リリースは81年)。僕がトリオに入社したのは、その1年前くらいでした。正確には思い出せないんですが、4年半在籍していたのかな。それまでは徳間音工にいたんです。もともと桐朋学園大学で作曲を専攻していたんですが、作曲のほうには早々に見切りをつけまして(笑)、『レコード芸術』の記事かなにかで、欧米には“レコーディング・ディレクター”という職業があるらしいと知って、卒業後コネをたどって、徳間にもぐり込んだんです。ところが当時の徳間は演歌全盛。カラオケのカセットを作ってました。そうこうするうちに、“トリオに空いてる口があるらしい”と聞きつけて、自分から売り込みに行ったんです。トリオの事務所があった、六本木への憧れもありましたし。僕が入社した時点、ショーボート・レーベル自体は開店休業状態でしたけどね。南 佳孝もいないし、(その後在籍していた)憂歌団もいなくなってた。主要なアーティストは、みんな外に出た後でしたから」
――上海バンスキングの成功を思うと、いい時期にいらしたとも言えるんじゃないですか。
「そうなんです。トリオに入社して1年近く経って、そろそろ仕事しないとまずいなという時期でもあって(笑)。じゃあ何やろうかと思ってた時、上海バンスキングをやってた自由劇場、あれがたまたま近くにあったんですよね」
――六本木通りを西麻布方向に遡っていった、小さなビルの地下でしたね。
「そう。で、トリオで後輩だった宣伝マンが、早稻田で芝居をやってたやつだったんです。鴻上尚史さんの後輩だったのかな。そいつが“最近、西麻布の自由劇場で、毎晩(入場待ちの)客がとぐろを巻いてる。上海バンスキングって芝居がおもしろいらしくて”って。何それ?って訊いたら、“100人も入らない小さい劇場だから、チケット取るのが大変なんですけど、1枚だけ取れた。音楽劇らしいし、観に行ったらどうですか”。僕自身そんなに芝居に興味があったわけじゃないんですが、そいつのツテで、野田秀樹さんが駒場でやってた夢の遊眠社とか、世代的には少し上の唐(十郎)さんご夫妻の紅テントを観に行かせてもらっていた。自由劇場や(上海バンスキングの主演女優だった)吉田日出子さんも、存在だけは存じ上げていたんです。それじゃあってんで、観に行ってみました」
祝『上海バンスキング』40周年・再発
吉田日出子
「上海バンスキング」
吉田日出子
「上海バンスキング」
――トリオから、徒歩圏内ですもんね。
「そしたら、これがべらぼうにおもしろかった。日出子さんの歌もよかったし。変なしがらみもなさそうだし、即、これはやりたいなと。翌日、自由劇場の事務所に電話しちゃったんです。“レコード化したいので、(主宰の)串田和美さんにお会いしたいんですが”。そしたらマネージャーさんが“いま、横におります”。“はいはい、串田です”って、ご本人がいきなり出てきた(笑)。“昨日拝見したんですが、べらぼうにおもしろかったです。あれ、まんまレコード化できると思います。楽曲も揃っているし”みたいな話をしたら、“レコードにしてくれるの? やってくれるんだったら、やって”って。後日、串田さんがエッセイで書いてるのを読んだら、“ソニーとか大手からも話が来たけど、最初に電話をくれたのがトリオだった”って。まあ、トントン拍子でした。トリオって会社自体、当時の“オーディオ御三家”のひとつ。“トリオ、パイオニア、サンスイ”と言われてた時代で、けっこうおカネがあった。ただ、レコード会社としてはしょせん素人。創業者の息子さんがクラシック・マニアだというんで、立ち上げた会社でしたから。怪しい芸能事務所にだまされたりしていたんです。もうちょっと知的な、だまされないような相手はいないかと探していた時期でもあったので、渡りに船ではありました」
祝『上海バンスキング』40周年・再発
吉田日出子
「もっと泣いてよフラッパー」
吉田日出子
「もっと泣いてよフラッパー」
――レコーディング自体、スムーズに行ったんですか。
「演奏は、正直言ってヘタじゃないですか(笑)。当初、(役者たちを)スタジオに放り込んで録音しようかとも思ったんだけど、上海バンスキングのテーマ曲もお書きになった越部信義さん、〈おもちゃのチャチャチャ〉を作曲された巨匠ですけど、あの方が大の芝居好きで音楽監督でもあったので、打ち合わせをしたんです。そしたら“(役者だけでやるのは)けっこうキビしいよ”と。"そもそも譜面が読めないし、テンポもズレる。レコーディングするんだったら、リズム隊はプロを入れるのがいいね”。なので、アルバム版『上海バンスキング』には、プロのピアノとベース、ドラムが入ってる。越部さんが親しくされていた方たちだったんじゃないかな。そこからスタジオでやります? どうします?って話になって、今度は串田さんが“ヘッドフォンつけて演奏するとかヤバいだろ”って。どうしたもんかなと思ってた時、当時あった六本木ピットインのことを思い出した。大きなハコで、6階がCBSソニー六本木スタジオ。ケーブルが店から6階のスタジオまでつながってたから、ジャズ・フュージョン系の人たちが、よくライヴ・レコーディングしてたんです。録った音を、そのままマルチの卓に流し込めるようになっていた」
――山下達郎さんも、その方式でライヴ・レコーディングされてますよね。
「マルチで録れば、日出子さんの歌を直すのもラクだし、それで行こうと。だったら、いっそライヴ仕立てにして、プロモーションを兼ねて評論家の方たちも呼んで……みたいなプランを話してたら、串田さんが乗っちゃってね。“怪しい中国人みたいな役者を、司会用に連れてくる”“ガヤ・ノイズもほしいから、劇団員もサクラで入れて”。たしか2回回したんじゃないかな。ちゃんとおカネも取って」
――ニセ・ライヴのような、ニセでもないような(笑)。
「串田さんいわく、“そもそも上海の怪しいジャズ・クラブが舞台なわけだから、それでいいんだよ”って。演奏面での手直しも、串田さんのクラリネットと吉田さんの歌を、少しだけ直したくらいでした」
――役者のみなさんは、楽器はまったくの素人だったわけですよね。
「まったくの素人。譜面もなんにもなくて、みんな耳コピでした。ドとかシとか口で言いながら練習していた。越部さん、ご自分では譜面を書いてたはずだけど、どうやって教え込んだんだろう。役者陣で今も活躍している人だと、小日向文世がクラリネット吹いてるんですよね。あと笹野高史。彼のトランペットはうまかった。そんなこんなでなんとかアルバムが出来上がって、新聞にもけっこう載って、評論家の方たちも若手を含めて観に来てくれた。舞台自体、いわゆるサブカル系の間で、評判になってたんですよね。当時のことなので、活字にも影響力がありましたから」
祝『上海バンスキング』40周年・再発
吉田日出子
「上海バンスキング」〜オーバー・ザ・ウェイブ 上海バンスキングII
吉田日出子
「上海バンスキング」〜オーバー・ザ・ウェイブ 上海バンスキングII
――結果的に、メディア・ミックスにもなりましたよね。
「あくまでそういう言い方をすれば、ですけど。TVとか映像系とミックスできたわけじゃなくて、やはり活字系。堅いところから柔らかいところまで、サブカル系言論の影響力があった。あれよあれよと言う間に、評判になりました」
――タウン誌の影響力が大きい時代でもありました。
「『ぴあ』とか『シティロード』。あとは『宝島』かな。若い人たちに影響を与える書き手がいた。やってるのは古い楽曲だけど、それが新鮮に映ったというのも大きかったですよね」
――オールド・ファンに訴求したという以上、新しくてかっこいいものとして受け取られた。
「そうそうそう。“これ、何?”みたいな。僕らがレコーディングしたのは、再演だったはずなんです。その再演も客が入り、レコードが出て、相前後して銀座の博品館劇場での1ヶ月公演と、続く地方公演の話が来た。自由劇場としても(上海バンスキングが)けっこう大きなビジネスになりかけてた時期だったんです。トリオ・レコードとしても、ヒット賞出してもいいか、くらいの売り上げになりました」
――ちなみに、当時どれくらい売れたんでしょう。
「2万から3万くらいかな。今にしてみればたいした数字じゃないけど、宣伝費もかかってないし、会社としても喜んでましたね」
――今回、上海バンスキングと並んで、同じ自由劇場絡みの『もっと泣いてよフラッパー』と『上海バンスキングII〜オーバー・ザ・ウェイブ』がリイシューされましたけど、変な話、1枚目が一番音に勢いがある。録音を重ねるごとに、立ち上がりの時のやみくもな勢いは、さすがに後退していったような気がします。
「『もっと泣いてよフラッパー』はアルバムとしては2枚目ですけど、上演は上海バンスキングの前なんですよね。これはもう単純に、上海バンスキングが当たったからやった。こちらはライヴ録りじゃなく、スタジオで3日間くらいに分けて録ってます。おっしゃる通り、みんな、ちょっと慣れてきたんですよ。上海バンスキングの地方公演もあったし、けっこう場数を踏んで、劇団員も一丁前のことを言うようになってきていた(笑)」
――だいぶ“ミュージシャン”な感じに(笑)。
「『オーバー・ザ・ウェイブ』に関して言うと、上海バンスキングの成功があって、誰がたくらんだのか知らないけど、古い客船に乗って、横浜港から上海間を3泊4日くらいで往復する。今言う音楽クルーズのはしりみたいな企画があったんです。これは僕じゃなく、チケットをくれた例の後輩が担当した。本当は船内ライヴを録りたかったんですが、電源だか機材の問題でやれなかったんです。“ずいぶんうまくなってるから、(スタジオでも)やれると思うよ”って、これもスタジオ録音。よくも悪くも、上海バンスキング成功の余波で生まれた2枚ですよね。そもそも音楽が本業の人たちではなかったわけだし。そうこうするうちに、エビータのオリジナルキャスト盤をやらないかという話が、劇団四季から来たんです」
祝『上海バンスキング』40周年・再発
劇団四季
ミュージカル「エビータ」(オリジナル東京キャスト盤)
劇団四季
ミュージカル「エビータ」(オリジナル東京キャスト盤)
――同じ音楽絡みとはいえ、上海バンスキングとはだいぶ趣きが違いますね。
「エビータの初演が82年。当時の劇団四季がどういう状況だったかというと、浅利慶太さんは当然お元気で、参宮橋に事務所と稽古場をかまえていた。それまで僕も、あまり興味はなかったんですよ。浅利さんて、日生劇場で越路吹雪さんのロングラン公演をやってた人でしょ、くらいの認識で、観に行ってもいなかった。ただエビータが画期的だったのは、それこそメディア・ミックスのはしりだったってことなんです。カネボウがスポンサーについて、その名も“エビータ”っていう化粧品ブランドを作って、それとミュージカルの上演をミックスする格好で、朝日新聞に全面広告を出した。道ばたにビルボードを建ててみたり、とにかく展開が派手だったんです。当時、世間的にはまだ無名だった主役の久野綾希子をキャラクターに据えて、まさにエビータ大展開で」
――四季としても、一大プロジェクトだったわけですね。
「のちの〈キャッツ〉を先触れする、四季大展開の最初のモデルケースだった。専有劇場はまだ作ってなくて、日生劇場での公演でしたけど。当時の朝日で、全面ぶち抜き。化粧品ですからTVスポットはばんばん入るというわけで、トリオとしても“イケるかな?”と思って四季の事務所に行ったら、どうも勝手が違って(笑)」
――自由劇場のようにはいかなかったんですね。
「(制作費は)全部トリオで持て、みたいな乱暴なことを言われて、なんだかんだすったもんだしたんですけど、結局その条件を呑んじゃったんです。だから、結局このアルバムは赤字です」
――あら〜。
「売れなかったわけでもないんですけど。収支は……とんとんくらいかな」
――制作費がかかったということですか。
「そうです。フル・オーケストラ使ってますから。ずいぶん後になってから、四季の偉い人に言われましたもん。“あの時はうまくやりましたよ”って」
――トリオとしては、レコーディングのノウハウを提供したに留まったと。
「実はノウハウ自体、当時の四季はすでに持ってたんです。浅利さんが越路吹雪さんの舞台をやっていた縁で、東芝EMI時代、越路さんの担当ディレクターだった渋谷森久さんという人が、四季の音楽監督もずっとなさっていた。器用な人で、自分で指揮棒を振ったりもできたんですよね。羽田健太郎、通称ハネケンを見出したり、とにかく業界では伝説的な人物だったんです。エビータの頃、もう東芝は辞められていたのかな? 渋谷さん相手では、僕みたいな三流では所詮勝負にならない。“いや、(音楽的な仕切りは)渋谷ちゃんがやるから”って。要は、トリオはカネで音源を買い取ればいい、ってことですねと。そこで高い安いはあったんだけど、やっておいたほうがいいということに、結局なった。だから、A&R的な役割ですよね、今のメジャーなレコード会社のシステムに即して言えば。かっこよく言うなら、エクゼクティヴ・プロデューサーかな。おカネを出してるんだから、そう呼ばれてもよかった気はしてるんですけど」
――いずれにせよ、上海バンスキングのように、制作にタッチする余地はなかった。
「エビータ自体、すでに出来上がった作品でしたから。そもそもロンドン・ヴァージョンがヒットしてから持ってきたわけで、オリジナル・レコーディングもユニバーサルから出ていたんです。それを四季が日本語に置き換えて“完コピ”する。まあ、たとえ僕が出て行っても、浅利さんとやったら絶対ノイローゼになってただろうから、よかったとは思うんです。渋谷さんだからこそ、浅利さんの面倒くささを理解しつつ、音楽の総責任者として、うまくやってくださったわけで」
祝『上海バンスキング』40周年・再発
劇団四季
ミュージカル「エビータ」日生劇場ライブ
劇団四季
ミュージカル「エビータ」日生劇場ライブ
――エビータはもう1種、日生劇場でのステージを完全収録した『エビータ・ライヴ盤』が出ています。
「最初に出たオリジナル・キャスト盤に、浅利さんがご不満だったんですよ。1枚目は、公演が始まる前に出てましたから。アルバムを出してから、劇場が開く。その時点でアルバムはヒットしている。そういう順番だったんで」
――ステージの先触れとして、スタジオ録音されたオリジナル・キャスト盤があらかじめ出ていた。
「1枚目は、言わばベスト盤みたいなものですよね。対する2作目は、全曲収録。中継車を日生劇場に持っていって、ミックスは四季のスタジオでやってます。エビータをやってた時、四季の創設メンバーから、“キャッツって知ってる? 四季が専用劇場を作ってやるんだよ”って話を聞かされたんです。“これは大博打なんだ。潰れてもいいからやるって、浅利さんが言ってる”って。キャッツのチケットをさばくために、チケットぴあが生まれたらしいですね。事務所の裏に、いまからみるとおもちゃみたいなコンピュータを並べて女の子を雇って、チケットを売り出した。それくらい大がかりな話だったんです。キャッツのサントラ自体、トリオじゃなく、ポニー・キャニオンに持ってかれちゃったんだけど(笑)」
――皮肉と言えば皮肉ですよね。チケットぴあが全盛になったことで、タウン情報誌はその役割を終えていったわけですから。
「雑誌のぴあ本体は、なくなっちゃった。四季はその後あざみ野に土地を買って、巨大な興業会社兼製作会社になっていきましたよね。東京のキャッツが成功したら、今度はMBSと組んで、大阪に劇場を作る。全国に急拡大していったわけです。舞台は映画と違ってライヴ・パフォーマンスだから、観せないと話にならない。客が来る間は無制限でロングランするというのが、浅利さんのテーマだった」
――そういう意味では、感覚がディズニーランドに近い。
「別に、浅利慶太さんの話をしに来たわけじゃないんだけど(笑)。ある意味、一劇団主宰者の域は超えてましたよね。むしろ実業家に近かった。自由劇場の串田和美さんとは、好対照だと思います。串田さん、巨匠と呼ばれるようになった今でも、相変わらずひょうひょうとされてますから。エビータに話を戻すと、化粧品まで同じ名前にしちゃって、相当な力業ですよね。当時、カネボウと資生堂、どちらかのキャンペーン・ソングになれば、かならず売れる時代でしたから。その片方のカネボウが、こういうタイアップをやるのかと。偶然とはいえ、その一角に関わることができて、おもしろかったですよ、やってる間は」
取材・文 / 真保みゆき(2019年2月)
最新インタビュー・特集
(2025/12/26掲載)
(2025/12/26掲載)
(2025/11/05掲載)
(2025/10/31掲載)
(2025/10/29掲載)
(2025/10/01掲載)











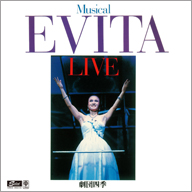

![[インタビュー]<br />十影とULTRA-VYBEによるマイク・パフォーマンス・プロジェクト『ULTRA SMASH』誕生 [インタビュー]<br />十影とULTRA-VYBEによるマイク・パフォーマンス・プロジェクト『ULTRA SMASH』誕生](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347056275.jpg)
![[インタビュー]<br />「ヤバスギルスキル」30周年。我リヤのニュー・アルバム完成!! ラッパ我リヤ [インタビュー]<br />「ヤバスギルスキル」30周年。我リヤのニュー・アルバム完成!! ラッパ我リヤ](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347055974.jpg)
![[インタビュー]<br />『WBS』のテーマ曲などでおなじみの作曲家 初めての自身名義のアルバムを発表 浅川真洋 [インタビュー]<br />『WBS』のテーマ曲などでおなじみの作曲家 初めての自身名義のアルバムを発表 浅川真洋](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z351005806.jpg)
![[インタビュー]<br />ポプシ30周年!マイペースに活動を続ける彼らが2ヵ月連続7インチを発表 Swinging Popsicle [インタビュー]<br />ポプシ30周年!マイペースに活動を続ける彼らが2ヵ月連続7インチを発表 Swinging Popsicle](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z351005871.jpg)
![[インタビュー]<br />佐藤理とゴンドウトモヒコの新ユニットが、聴覚と視覚を刺激するアルバムを発表 LIG [インタビュー]<br />佐藤理とゴンドウトモヒコの新ユニットが、聴覚と視覚を刺激するアルバムを発表 LIG](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347054553.jpg)
![[インタビュー]<br />デビュー20周年 再始動を告げる新作EP 音速ライン [インタビュー]<br />デビュー20周年 再始動を告げる新作EP 音速ライン](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347054474.jpg)
![[インタビュー]<br />私は私にできることを歌にしていく ゆっきゅんのニューEP [インタビュー]<br />私は私にできることを歌にしていく ゆっきゅんのニューEP](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z351005576.jpg)
![[インタビュー]<br />来日公演を目前に控え、孤高のソウル・シンガーが発表する17年ぶりの新作『PRAYER』 リアム・オ・メンリィ [インタビュー]<br />来日公演を目前に控え、孤高のソウル・シンガーが発表する17年ぶりの新作『PRAYER』 リアム・オ・メンリィ](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z351005547.jpg)
![[インタビュー]<br />今春のカルテットでのツアーを録音した『FRAGMENTS - CONCERT HALL LIVE 2025』を発表 松井秀太郎 [インタビュー]<br />今春のカルテットでのツアーを録音した『FRAGMENTS - CONCERT HALL LIVE 2025』を発表 松井秀太郎](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347054178.jpg)
![[インタビュー]<br />友成空の大ヒット曲「鬼ノ宴」が湖池屋とコラポレーション クセになる辛さの「ピュアポテト 鬼ノ宴」誕生 [インタビュー]<br />友成空の大ヒット曲「鬼ノ宴」が湖池屋とコラポレーション クセになる辛さの「ピュアポテト 鬼ノ宴」誕生](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z351005417.jpg)
![[インタビュー]<br />オーケストラとともに過去・現在・未来を紡ぐ活動40周年記念アルバム『RE-BORN』 千住明 [インタビュー]<br />オーケストラとともに過去・現在・未来を紡ぐ活動40周年記念アルバム『RE-BORN』 千住明](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347053672.jpg)


