これまで数多くのテレビ番組やCM、映像作品、舞台などの音楽を手がけてきた作曲家でサウンド・プロデューサーの浅川真洋が個人名義では初のオリジナル・アルバム『Ambience of Life』をリリースした。テレビ番組『WBS(ワールドビジネスサテライト)』のオープニング・テーマ曲「billions of skies」をはじめ、アンビエント中心の透明感にあふれた映像的なサウンドときらめくようなメロディが躍動していく、とても美しくスケール感にあふれたインスト・アルバムだ。すでに約20年のキャリアをもつ彼の蓄積が存分に表れた、集大成的作品ともいえるだろう。彼にこれまでの活動や今回のアルバムについて、たっぷり語ってもらった。
――浅川さんは作曲家、サウンド・プロデューサーとして活動してきたわけですが、もともと作曲家を目指していたのでしょうか。
「作曲家とアーティストの違いをよくわかっていなかったというのがあります。というのも、私が10代の頃好きだったのはクインシー・ジョーンズやデヴィッド・フォスター、ブライアン・イーノ、日本ですと坂本龍一さん。どちらかというと、裏方的なポジションの方々なのですが、メディアにも出ていらして、違いというものを意識してなかったんです」
――小さい頃から作曲をしたいと思っていたのでしょうか。
「幼い頃は、母方の叔父が陶芸家をしていて、遊びに行くと、創作活動みたいなのを一緒にやってくれたりしたんです。家の中にあるいろいろなものの音を鳴らしてセッションしようとか。お鍋の蓋を両手で持って、当て方、強さを変えれば、音が変わる即興演奏というふうなことをやっていて。今思えば、それが作曲活動につながっていった気はします」
――中学の時にはもう作曲をしていたとか。
「姉がピアノを習っていて、姉が習っている横で、それを見ながら私もやっていました。中学の時、クラスの担任が音楽の先生だったんですけど、作曲の授業があって、その先生をびっくりさせようと思って、一生懸命作って出したら怒られたんです。ちょっと高度すぎる、周りに合わせることを覚えなきゃダメだよ、みたいなこと言われて」
――それはすごい。高校時代には、楽器屋の店員さんに言われて、毎日作曲をするということをやっていたそうですね。
「楽器屋のお兄さんに言われてやってましたね。今考えるとその経験が大きかったと思います。曲を作って持っていくと、批評してくれるわけです。大阪人なので、めちゃくちゃきつい言葉でいろいろ言われて(笑)。この人に褒めてもらいたいというか、認めてもらいたいという気持ちが大きくて、作っては持っていくというのが日課になっていました」
――その頃には作曲家としてやっていきたいみたいなものがあったのでしょうか。
「あまりないです(笑)。日々楽しんでやっていただけでした。でも、楽器屋のお兄さんのおかげもあって、コンテストに出すと、軒並み評価が良くて。賞をいただいたり、雑誌に載ったり。なので、認めてもらってる分野で、将来やっていけたらいいなとは漠然と思っていました。それで大阪のアートスクールに在籍していた時に、NHKの方が講演に来られたことがあったのですが、チャンスだと思って、講演の後に、思い切ってデモCDを“聴いてください”とお渡ししました。半年後ぐらいにご連絡をいただいて、“君がイメージしていたような仕事じゃないかもしれないけど、よかったらやってみる?”と、鳥取放送局のお昼の番組の曲を作らせていただきました。それが最初ですね」

――そこからさまざまなテレビ、ラジオ、CM、映像作品、舞台、イベントなどの音楽を手掛けていくわけですけど、浅川さんが作るものはアンビエントからダンサブルなものまで、ジャンルレスで幅広くて多彩ですよね。オーダーの内容の幅も大きいとは思うのですが、それはどうしてだと思いますか。
「まずリスナーとして、音楽だけではなくて、サウンド・アートや音そのものも含めて、いろんなことをおもしろいなと思って聴いてきました。それに、若い頃はクライアントからいろいろなオーダーが来ますので、あれもおもしろいな、これもおもしろいなとやっているうちに自然とそうなっていた感じです」
――たとえばクラシックとか映画音楽とか、特定のジャンルに固執するということがなかったということですか。
「音楽は音楽ですからね。あまり分けて考えたことはないです」
――では逆に、一貫しているものってなんだと思いますか。個人的には浅川さんの作る曲は都会的で品が良くて洗練されたメロディやサウンドが特徴だと思います。
「今おっしゃったような認識を自分で持ったことはなかったので、すごく新鮮です(笑)。美しいもの――美しい情景、美しい景色、美しい瞬間――が好きなので、それを描きたい、形にしたいというのを思ってずっとやってきました。その結果なのかなと思いますね」
――自身の名義とは別に、“JETT.A”名義でも活動しています。こちらはミックスCDやリミックスが中心ですけど、この名義はいつ頃から使っているのでしょうか。
「じつは学生の頃に、その名前で仕事していた時があるんです。映画音楽もやらせてもらったりしていたのですが、やることが幅広くなってきたので、自分の名前でやったほうが自然かなと思うようになりました。それで切り離し出して、ふだんの作曲活動は本名で、リミックスはJETT.A名義にしました」
――JETT.A名義では『映画泥棒』や『シネマティック・ブレイクス』などのミックスCDやリミックスを多く出していますね。
「(作品をリリースしている)ランブリング・レコーズさんと出会ったことがきっかけです。“リミックスって興味ありますか?”と聞かれて“おもしろそうですね”みたいなことから始まりました。おかげさまで続けてきたらこうなっていて、“JETT.A節”とまで言ってくださる方がいました」
――JETT.A名義で2023年に出した『LIFETIME BREAKS』は全曲書き下ろしのオリジナル曲です。そこでオリジナルを出そうと思ったのはどうしてなのでしょうか。
「たくさんのリミックスをやらせていただいて、もうそろそろやりきったかなという感覚もあった中で、新作のお話いただいて。だったらオリジナルをやってみていいですかという話をしました。あえて“JETT.A節”というものに寄せたアルバムを出してみたかったんです」
――派手で、ファンタジックで、エンタテインメントなアルバムですよね。
「そうですね。大阪の若い頃のやんちゃな自分みたいなイメージです(笑)」
――その後、今回の個人名義としては初のオリジナル・アルバム『Ambience of Life』に至るわけですが、約20年間ずっと作曲家として活動してきて、初めて個人名義の作品を作ろうと思ったのはどうしてなのでしょうか。
「コロナ禍で身近な人間がたくさん亡くなったんです。死というものはあまり実感のない、遠いことだと思っていたのが、コロナ禍を経て、自分のこととして捉えるようになりました。そうなると、日々の穏やかな生活がすごく愛おしいものに感じてきて、それを描いておきたい、音楽にしておきたいと思うようになりました」
――これまでのお仕事のほとんどは、依頼があって作っていたと思うんですけど、今回は自分の作品なので自発的に作るわけですよね。これまでとは異なる感覚はありましたか。
「おかげさまでこれくらいの歳になってくると、ご依頼いただくお仕事でも、“浅川さんらしい感じでお願いします”と言われることも多いんです。だから正直、依頼いただく作品と自分の作品では音楽的にそんなに違いはありません。明確に自分の作品として、自分の名前で世の中に出ていくというのが違うぐらいなんです」
――普段のお仕事から、浅川さん自身の表現欲求みたいなものは満たされている感覚があるのでしょうか。
「満たされてはいると思いますが、自分をアピールするというよりは、そのプロジェクト全体がうまくいくのだったら、目立たないほうがいいのかなという感じもありました」
――このアルバムはほぼアンビエントに絞っています。それは自身にとっていちばんしっくりくる音ということなのでしょうか。
「ブライアン・イーノに代表される、いわゆるアンビエント・ミュージックをやろうとしたわけではなくて、日本人である自分がこの穏やかな毎日を描く時にどうしたらいいか、ということの結果なんです。ジャンル的にはいろんなものが入っているとは思うのですが、共通していえるのは、Ambience=雰囲気というか、もっというと“気配”みたいなもの。全体的にそういう気配が香り立つようにまとめられたらと思って、タイトルが『Ambience of Life』なんです。Ambienceには“限られた空間の雰囲気”という意味もあって、人生のいろんなシーンの限られた場面の気配を表現したかったというのもあります」
――アルバム全体として、夜から始まって朝があって夕暮れがあって、最後はまた夜で終わるという、1日の流れを追ったような作品になっています。
「そうですね。でも、いろんな聴き方もできるようになっているんです。アクティブな日なら〈brand new day〜目覚める街〉と〈future ride〜ユメノノリモノ〉と〈biological city〜生物から見た都市〉、リラックスした日なら〈morning star〜境界の星〉と〈velvet sky〜ビロードの空〉と〈zen garden〜閑かの海に木漏れ日〉など、どんな気分でもしっくりくるように作っています。なおかつおっしゃるとおり、このまま聴いても1日の流れのようになっています」
――メロディもサウンドも研磨されていて、音数が少なくシンプルな構造ですよね。そこは意識していたのでしょうか。
「“わびさび”といいますか、音楽的な情報を詰め込みすぎないように意識しました。音と風景、音と映像、音となにかというのを、ちょうどいい情報量になるように。引き算の美学というか、音を減らしていく作業でした」
――「ancient city, afternoon〜古都にて」は、タイトルどおり和のアンビエントっぽいサウンドで、さっき言われていた“日本人の自分”を出した感じでしょうか。
「DNAに刻まれているといいますか、日本的なものはやっぱり好きなんです。ただ、この曲は和楽器を使わずにやっています。カリンバ、パーカッション、フルートなどを使いながら、日本っぽさも感じながらやっています。古代のものって世界的に共通していると思っていて。和楽器を使わず、それでいて日本っぽくて普遍的なものを描きたかったんです」
――ラスト3曲はアルバムのクライマックスになっています。「euphoric utopia〜ユメノミヤコ」は合唱コーラスが讃美歌を思わせますし、そこから「billions of skies」のきらめくようなメロディがピークになっていて、最後の「polaris〜北極星」に至ります。
「〈billions of skies〉は『WBS』さんの曲なので、夜に入れるのがいいなと思ったんですけど、そこに向かって盛り上げていこうと思いました。1曲前の〈euphoric utopia〜ユメノミヤコ〉は〈billions of skies〉の前奏曲みたいなイメージで作りました。最後の〈polaris〜北極星〉は、星空の中で北極星はつねに同じ場所にあって、それを中心に宇宙が回っていて、私たちの道しるべになってくれる存在ですよね。最後はそこに集約していくという形にしたかった。だからとおして聴いていただけると、そういうことかと思ってもらえると思います」
――『WBS(ワールドビジネスサテライト)』のオープニング・テーマ曲である「billions of skies」はこのアルバムの中でも際立っていると思うんですが、やっぱり特別な曲ですか。
「そうですね。たくさんの人たちが見ている空って、ひょっとしたらちょっとずつ違うかもしれないけど、それが集まってこの世界になっている。それでいいと思うし、だからこそこの世界は素晴らしいと思うというのを表現したいと思いました」
――総じていえば、アンビエント作品でありつつ、メロディもサウンドも力強さがありますし、人生におけるさまざまな場面を映像的に表していて、すごく美しくて壮大な作品になっています。浅川さんとしては、もっとも表したかったものとはなんでしょうか。
「人生讃歌というか、この国に生まれてよかったとか、この星に生まれてよかったとか、そういうのを残しておきたかった。こんなこと言っていると、もうすぐ死ぬんじゃないかと思われそうですが(笑)」
――今後はこうしたアーティストとしての活動もしていきたいと思いますか。
「最初に言ったように、アーティスト活動と作曲家活動のなにが違うのか、今でもよくわからなかったりするのですが、こういう形で世の中的に受け入れてもらえるのであれば、やっていきたいなと思っています」
――浅川さんの音楽って聴き手を楽しませる音楽だと思うんですよね。癒しだったりアッパーな気分だったり、聴き手に寄り添うことができる音楽だと思うんですけど、そういう意識は強かったりするのでしょうか。
「せっかく音楽のお仕事をさせていただいているので、ちょっとは世の中の役に立ちたいというのはあります。聴いてくださった方が、少し前向きな気持ちになったり、自分自身を肯定できるようになったり、そういう気持ちになっていただけたらやっぱりうれしいです」
――以前、“森羅万象のすべてを音楽で表したい”と発言をしていましたけど、今でもそう思っていますか。
「思っています。同時に、できないということもわかっています。でも、森羅万象を音にするというテーマがあることによって、自分はずっと存続していけるというか、これからもやっていけるなと思えたんです。このアルバムもそうですし、お仕事のご依頼もそうです」
――できないからこそモチベーションにもなっていると。最後に、今後やってみたいことなどあれば教えてください。
「(出身地の)大阪府箕面市の箕面音楽創造大使を務めさせていただいていて、その流れで地元のエフエムで『サウンド・ミュージアム』という番組をやらせてもらって、1年ぐらい自分の言葉で語ることをやってきました。今までは音で表現してきたのですが、言葉で自分を表現するということがとても新鮮でした。だから今後、エッセイやコラムみたいな言葉を使う表現の機会があれば、挑戦していきたいなと思っています」
取材・文/小山 守
最新インタビュー・特集
(2026/02/18掲載)
(2025/12/26掲載)
(2025/12/26掲載)
(2025/11/05掲載)
(2025/10/31掲載)
(2025/10/29掲載)





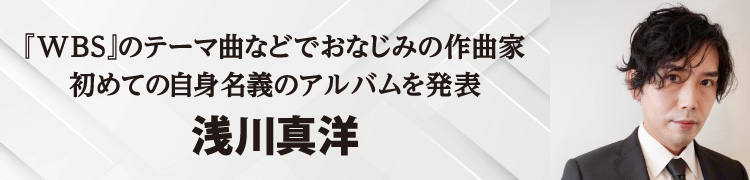



![[インタビュー]<br />精子役で声優デビュー(映画『スペルマゲドン 精なる大冒険』) ニシダ(ラランド) [インタビュー]<br />精子役で声優デビュー(映画『スペルマゲドン 精なる大冒険』) ニシダ(ラランド)](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347057214.jpg)
![[インタビュー]<br />「YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜 ― Tokyo 3 Nights 世界への第一章」から始まる世界への新たな道 YOSHIKI [インタビュー]<br />「YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜 ― Tokyo 3 Nights 世界への第一章」から始まる世界への新たな道 YOSHIKI](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z351006069.jpg)
![[インタビュー]<br />十影とULTRA-VYBEによるマイク・パフォーマンス・プロジェクト『ULTRA SMASH』誕生 [インタビュー]<br />十影とULTRA-VYBEによるマイク・パフォーマンス・プロジェクト『ULTRA SMASH』誕生](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347056275.jpg)
![[インタビュー]<br />「ヤバスギルスキル」30周年。我リヤのニュー・アルバム完成!! ラッパ我リヤ [インタビュー]<br />「ヤバスギルスキル」30周年。我リヤのニュー・アルバム完成!! ラッパ我リヤ](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347055974.jpg)
![[インタビュー]<br />『WBS』のテーマ曲などでおなじみの作曲家 初めての自身名義のアルバムを発表 浅川真洋 [インタビュー]<br />『WBS』のテーマ曲などでおなじみの作曲家 初めての自身名義のアルバムを発表 浅川真洋](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z351005806.jpg)
![[インタビュー]<br />ポプシ30周年!マイペースに活動を続ける彼らが2ヵ月連続7インチを発表 Swinging Popsicle [インタビュー]<br />ポプシ30周年!マイペースに活動を続ける彼らが2ヵ月連続7インチを発表 Swinging Popsicle](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z351005871.jpg)
![[インタビュー]<br />佐藤理とゴンドウトモヒコの新ユニットが、聴覚と視覚を刺激するアルバムを発表 LIG [インタビュー]<br />佐藤理とゴンドウトモヒコの新ユニットが、聴覚と視覚を刺激するアルバムを発表 LIG](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347054553.jpg)
![[インタビュー]<br />デビュー20周年 再始動を告げる新作EP 音速ライン [インタビュー]<br />デビュー20周年 再始動を告げる新作EP 音速ライン](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347054474.jpg)
![[インタビュー]<br />私は私にできることを歌にしていく ゆっきゅんのニューEP [インタビュー]<br />私は私にできることを歌にしていく ゆっきゅんのニューEP](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z351005576.jpg)
![[インタビュー]<br />来日公演を目前に控え、孤高のソウル・シンガーが発表する17年ぶりの新作『PRAYER』 リアム・オ・メンリィ [インタビュー]<br />来日公演を目前に控え、孤高のソウル・シンガーが発表する17年ぶりの新作『PRAYER』 リアム・オ・メンリィ](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z351005547.jpg)
![[インタビュー]<br />今春のカルテットでのツアーを録音した『FRAGMENTS - CONCERT HALL LIVE 2025』を発表 松井秀太郎 [インタビュー]<br />今春のカルテットでのツアーを録音した『FRAGMENTS - CONCERT HALL LIVE 2025』を発表 松井秀太郎](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347054178.jpg)


