『
FRESH』。そう思いきりよく“宣言”した表題通り。およそ1年半ぶりとなるニュー・アルバムでの
高田 漣、なんかキラキラしてます。前作『
ナイトライダーズ・ブルース』が、第59回レコード大賞優秀アルバム賞を受賞。アーティストとして一里塚を築いたことで落ち着きを増すかと思いきや、まりんこと
砂原良徳とコラボした先行シングル曲「GAMES」は、エイティーズ的なチャラさ爆発の打ち込みファンク。ポップ・クリエイターとして、まだまだ油断できない(笑)新境地を聞かせている。一聴、直系の“
大瀧詠一トリビュート”と思わせる「モノクローム・ガール」での、予定調和を次々と裏切っていく展開とか、おもしろいんだからほんと。
「〈GAMES〉は、『ナイトライダーズ・ブルース』をプロモーションしてる頃、すでに出来ていた曲なんです。大阪にプロモーションしに行く電車の中で、事務所の社長と“どうしようか、あの曲”という話をしていたくらいで。その時は、まさか『ナイトライダーズ・ブルース』がレコード大賞をいただけるなんて、思ってもいませんでしたから」
――聞き手としても、間に『ナイトライダーズ・ブルース』があったことで、驚きつつも納得がいくところがありました。
「ですよね。『
コーヒーブルース〜高田渡を歌う〜』の直後がこれだったりしたら、エラいことですよね(笑)。『ナイトライダーズ・ブルース』発表の時点でも、いくらなんでも飛躍し過ぎだろう、ということになって、いったんは引っ込めたんです。当時出したとしても、まりんさんには頼まずに、もっとフィジカルな仕上がりになっていたかもしれない。多少インターバルを置いたからこそ、“ここは思い切って、(いままでと)違うものを提示してみよう”という感じになれた」
「ははは。なるほどなるほど」
――年寄りならではの腑への落ち方ですけど(笑)。
「でも、まりんさんと話してたイメージも、そんな感じでした。詞の内容もあって、
岡村(靖幸)ちゃんとか
プリンスの名前も挙がってたかな。そもそもは、『ナイトライダーズ・ブルース』のライヴをやりながら、もうちょいファンキーな曲があったら、同じアンサンブルでもお客さんがもっと楽しめるんじゃないかと思うようになった。そこがスタートだったんです。なんでかこうなっちゃったけど(笑)。打ち込みにしようというアイディアが出た段階で、まりんさんの名前が出たのはたしかですね。それがよかったんだと思います。もっと早い時期にやってたら、もっとフィジカルな、悪くすると中途半端に重い曲になってたかもしれない」
――80年代って、いわゆる“横ノリ”とはまったく違う、ビートを縦に分割することでファンキーさを出す、そういう時代でもありましたよね。
「〈GAMES〉は、それでもギターを弾きながら作ってたんで、本来なら生身のグルーヴで作ってもおかしくない曲ではあったんです。でも、曲名含め、そのままだとなんだか腑に落ちなかった。僕も、家では打ち込んでますから。ここはあえて自分じゃない人にすべてを託してみようと。楽しかったですよ。自分で作り始めた当初は、もう少しわかりやすくどっしりしていたのが、まりんさんが彼なりのサウンドに寄せていってくれる中で、BPMがどんどん上がっていって」
――いい意味で、チャラくなっていった(笑)。
「僕自身、そこで腑に落ちたっていうか。『FRESH』の中で一番最初に出来た曲だったんですけど、この一手があったおかげで、その他の曲も新たな方向に進むことができた気がしています。こういうサウンドの曲がいきなり出来たせいで、いままでの音作りだと、どうしても食い合わせが悪くなった。『ナイトライダーズ・ブルース』のサウンドにもう少しシンセを加えて……という風に、統合作用が起きていった気がしてます」
――“シブい”音楽人生を歩んでいくと思いきや(笑)。
「ふはははは。いや、僕自身、今回取材でみなさんの感想をうかがって、“あ、みんなオレのこと、そういう風に捉えてたんだ〜”って(笑)。自分としては、別に変わってないつもりなんですけど」
――わたくし的には、ヒップホップ好きだったご自分をカミングアウトしたという点において、前作と今回はつながって聞こえています。
「そうですね。全然そうじゃない要素も入っちゃってるけど(笑)。『FRESH』の中でも、初期に作った曲、〈GAMES〉とか〈ハロー・フジヤマ〉〈はいからはくち〉〈寝モーショナル・レスキュー〉あたりには、『ナイトライダーズ・ブルース』と地続きの感覚が残っているんです。“変化”を意識したのは、〈モノクローム・ガール〉が出来た頃ですね。自分の曲なんだけど、自分でも思ってもみなかったような展開が生まれてしまった」
――「モノクローム・ガール」では、中盤、“ネオンライト横目に 轟くガンボビート”のくだりから、曲としてのドラマが、二転三転します。
「この曲、歌詞は3〜4回変えたんですけど、メロディ的にはそんなに変わった曲でもなかったんです。前作だったらそこで仕舞ってたところが、今回は“もう一声!”って叫ぶ声が自分の中にあって(笑)。ふつう、こういうオープン・チューニングの曲って転調しないけど、ちょっと転調してみよう。それもセカンドライン系ではあまり使わないメジャー・セヴンス系のコードを入れて、洒落たコード進行にしてみるのはどうかって。それに合わせて、歌詞も変えてみたんです。パーツが入れ替わるたびに、曲調も詞も変わっていく、みたいな展開が生まれてきた」
――曲の構造自体エディット的。1曲分の情報量じゃないですよね。言ってみれば“3本立て”みたいな。
「おっしゃる通り、ほんとにエディットしてるみたいな感じでした。DJがマッシュアップする感覚に近いかもしれない」
「あっ、まさに! いままでは、どちらかと言えば韻重視。歌詞のストーリー性までは気にしてなかったんですけど、今回はカット割りというか、映画っぽい感覚で歌詞を書いてましたね。曲を書くにあたって、長年やってきたギターでの弾き語りを封印してもいるんです。Macの前に立って歌詞もコード進行も、あらゆる作業を同時にやってみた。というのも、ギター弾いて曲を作る行為って、長年やってきてどんなに好きでも、飽きがくる時期が訪れる。僕の場合、たぶんそれがいまなんです。自分の手のうちが見え過ぎちゃって、また同じものを作っちゃったって……」
――驚きがなくなる。
「そうなんです。なんとかそれを回避しようと、Macの前でなるべく素の状態からスタートしてみた。ゼロから出発するので、メロディと歌詞が同時に浮かぶんです。裏を返せば、浮かんでくるまでとことんやる。そういう心構えでやっていました。まさにアルバム・タイトル通り。フィジカルに頼り過ぎないように、フレッシュな気持ちのまま作ろうとは、心がけてましたね」
――“手練れの人”にならないように。
「そう! ほんとそうなんです。自分が作る以上、結局はわかってしまうんですけど、その中でも“自分ならこう行く”というのを、なるべく排除していきたかった。
ブライアン・イーノと
デヴィッド・ボウイがダーツで決めたみたいな(笑)、あそこまではできないにしても、そのくらいの気持ちで」
――1枚1枚そうやって変わっていくんだから、おもしろいものですね。
「自分でも不思議です(笑)。こうして取材を受けることで、そっか、こないだ作ったのは、こんなアルバムだったんだ。考えてみると、数年前は『
コーヒーブルース〜高田渡を歌う〜』を作ってたんだ……とか、我ながら追いついていけてない。作ってる最中は、ある種の躁状態なんで、なにも考えてないんですけど」
――説明するために作るわけじゃないですからね。
「今回のような作り方だと特にそうで、出来上がってからも、自分では判断がつかないんですよ。ギター弾いて作ってる時なら、多少は出来た時の喜びを実感できるんですけど、今回は……なんなんでしょう。魂が抜けたような感じ(笑)」
――別の“どこでもドア”が開いちゃった、みたいな。
「まあ、それが楽しくて、意図してそうやって作ってたのも事実なんです。なるべく、いい意味での距離感を保って作っていきたかった」
――“知らなかった自分”を知るためにも。
「『FRESH』のレコーディングと同時進行で、まだ公開されてない映画のサウンドトラックも作っていたんです。
犬童一心監督の中国映画なんですが、なかなか検閲を通らなくて世に出せてない。そのラストシーンにすごいオチがあって、それを補完するために音楽がぐわ〜〜〜っと明るい、ナイアガラ・サウンド調になって終わるんです。ただのインストではあるんだけど、それを作ったことが引き金になって、いままで表立ってなかったそういう音への欲が、徐々に出てきたみたいです。〈モノクローム・ガール〉がそうだし、『FRESH』で一番最後に出来た〈ロックンロール・フューチャー〉もそう。なんかこう、湧き出てきたっていうか」
――いままでにない、カラフルな感じ。ちょっと人工着色された感じもあって。
「そうそう。ほんと、自分でも不思議なんですよね。大瀧さんや
細野(晴臣)さん、ふだんから家でもよく聴いているんだから、(影響が)出てくるのは当たり前。むしろ、なんでいままで自分の作風に出てこなかったんだろう、と思うくらいで」
――私は逆に、大瀧さん、事実上ライヴを辞めちゃったじゃないですか。
「はいはい」
――もし、ライヴ・パフォーマー、それもフルオケがバックとかじゃない、バンドで歌う道を残していたとしたら……みたいな。パラレル・ワールド的なアプローチを感じたりもしました。
「うんうん」
「大瀧さんのアルバム、どれも全部好きなんですけど、自分の中で大きいのは、ファースト・アルバムの時の大瀧さん。はっぴいえんどがまだあって、でもはっぴいえんどにはないカラフルなものを作ってた時期ですよね。自分が音楽をやってるからとかじゃなく、どれくらい影響されてきたか意識しないくらい、ただただ好きでよく聴いてきた。今回、ナイアガラ的な要素が自分の作品に出てきたのには、我ながらびっくりしてもいるんです。ふだん、細野さんのバンドでさんざん演奏していることもあって、周りの人たちからも“漣くんって、そんなに大瀧さんが好きだったんだ”って、驚かれたりもしているし」
――「モノクローム・ガール」は大瀧さんの「ハンドクラッピン・ルンバ」にインスパイアされてる、とご自身で解説されていますが、一方で細野さんの「ポンポン蒸気」みたいでもある。そういう意味で、漣さんは正しくお二人の“子ども”なのではないかと。
「まあ、大瀧さんの最初のソロ・アルバムでは、細野さんがベースを弾いてますからね(笑)。はっぴいえんどに限らず、自分がこれまで聴いてきたものが、前作を機に、奇をてらわず自然に出てくるようになってきた気はしています。曲作りやアレンジも含めて」
――はっぴいえんどの代表曲を正面切ってカヴァーした「はいからはくち」は、ドラムがとにかくかっこいい♡と思いました。
「ありがとうございます。実はこれ、
ビースティ・ボーイズの〈ルート・ダウン〉を自分なりにやろうと思ったところから始まっているんです。(サンプリングされている)
ジミー・スミスの〈ルート・ダウン〉から聴き直して、どこが違うのか研究して、家でイントロのリズム・トラックを組んで、ベースも入れて、一人でにやにやしていた(笑)。聴いているうちに、これに合う曲が他にありそうだなと。試しに〈はいからはくち〉を歌ってみたら、ぴったりはまった。だから、自分にとっては〈ルート・ダウン〉ありきの曲なんですよね」
――一方で、オリジナルの「はいからはくち」を歌ってらした大瀧さんが、『
ロング・バケイション』以降クルーナーに徹したことで、脇に置かざるを得なかったもの。“バンドで歌う”大瀧さんに向けた、漣さんなりのトリビュート的なものを、感じたりもします。
「なんだろう……。そういう、大瀧さんのもうひとつの“声”というのが、自分にとって大きなものなんですよね、きっと」
――もうひとつ、今回のアルバムって、冒頭と後半に、女声の“ご案内”が入ってるじゃないですか。1曲目の「寝モーショナル・レスキュー」って曲名もそうですが、なんて言うか、アホだなと(笑)。
「はははは」
――それってある種の含羞、“照れ”なのか、あるいは本当にアホなのか(笑)。ご本人に訊くこと自体、失礼にもほどがあるんですけど。
「4年ほど前、
高田 渡トリビュート・ライヴで全国を回った時、ただ音楽をやるだけではない、父独特の落語のような“噺”を曲間に差し挟むことの効用を、実感したことがあったんです。大体、父の歌ばかり何十曲も延々と聴かされてたら、どんなに好きな人でも疲弊してくるんですよ(笑)。合間におもしろ噺を挟んでいかないと、観ているほうもやってるほうもツラくなる。その中で培った“体力”のようなものが、『ナイトライダーズ・ブルース』のツアーの時も、活かされるようになって。今回レコーディングしている時も、そういう要素をちりばめたいなという意識が、なんとなくですがありました。それも、どうせなら何かの引用。大瀧さんの〈ハンドクラッピン・ルンバ〉に出てくる“2番は1番とちょっと違う!”って掛け声だったり、YMOの歌詞の一節だったり。子どもの頃、大瀧さんや細野さんの音楽を聴いていた時には、“なんでここにお笑いを入れるんだろう?ないほうが、もっとかっこいいのに”と思っていたんでけど(笑)。いざ自分が大人になってオヤジ化が進んでくると、やっぱりダジャレが増えてきた(爆笑)。ただ、近年の細野さんのライヴもそうですけど、真剣に音楽をやるのと同じくらい、ユーモアをもってその音楽に接することって大事だなと。いま、細野さんと共演することを通じて、身をもってそれを見せていただいているというか。ひょっとしたら、音楽的なこと以上に影響を受けているかもしれない。そう思ったりしてます」
――音楽には、使いようによっては最強のプロパガンダの道具になり得る。そういう側面がありますよね。ナチス・ドイツはその最悪の例。細野さんには、音楽が持つそうした側面に対する“畏れ”があるんじゃないかと思うんです。盛り上がり過ぎることの怖さっていうか。
「それこそ今回の『
HOCHONO HOUSE』にしても、『
HOSONO HOUSE』(が持つ歴史的な重み)を、なんとかやわらげようとされている。細野さんなりに、バランスを取ってらっしゃるんだと思います。はっぴいえんどにしてもそうだし、大瀧さんのソロにしてもそう。『
スネークマン・ショー』とか、父のアルバムもそうですよね。そこは逆に、オヤジだからこそできることじゃないかな、という気がしています。はっぴいえんどにしても、何がおもしろいかって、あんなにくそ真面目なバンドのようでいて、実はムダに笑いの要素が強い(笑)。以前、NHKの番組で『
風街ろまん』のトラックを全曲聴いて解説する企画に参加したんですが、その時資料として聴かせてもらった未公開のトラックの中に、すごいのがあったんですよ。大瀧さんが一人でおちゃらけていて、よくまあみんな、笑わずに演奏してるな、みたいな(笑)。でも、ほんとはそれが核心だったのかもしれない。バンドとしての“体温”、空気感みたいなものを、再確認したんです。いまの自分のモードも、そこに直結してるのかもしれないですね」
――大瀧さんの場合、そこを追求し過ぎて、長らく不遇をかこったわけですから。
「そうそう。『レッツ・オンド・アゲイン』とか、ほんとに売れなくて、ミュージシャン廃業まで考えたそうですから」
――細野さんのほうが、そう思うと、ユーモアという点では一貫しているというか。
「細野さんのほうが、いい意味でシャイなんですよね。笑いの要素を入れることにかけてもシャイだから、いい塩梅のところで止めるけど、大瀧さんは笑いを入れるとなったら……」
――突き詰め過ぎちゃう(笑)。
「そこがまた、大瀧さんの魅力でもあるんです。より研究家気質というか。いまとなってみると、そういうものを残してくれたってこと自体、僕らにとってすごい財産なんですよね。そこを聴くことによって、学ぶことやインスパイアされることがたくさんある」
――2019年は、漣さんご自身のライヴとともに、細野さんとの共演ツアーが控えています。
「細野さん、アメリカ公演も決まったみたいですから」
――先だっての台湾公演も、成功裡に終わったそうですね。
「台湾、今年も行きましたけど、去年初めて細野晴臣名義で海外公演をして、熱狂的に受け入れられた。細野さん自身、ものすごく驚いたみたいなんです。と同時に、自分がやってきた音楽に、自信が持てた瞬間だったと思うんですよね。僕らバンド・メンバーもそこは同じで、自分たちがやってるサウンドが、世界に通用するかもしれないと、すごく大きな自信になった。昨年、ロンドンとブライトンで演奏した時にもそれは続いていて、今回の『FRESH』を作った時にも、その流れが続いていたんです。僕だけじゃなく、メンバーみんなが、自信を持ってキラキラしていた。サウンドの力強さに、それが影響している気もします」
――ツアーでの経験が、スタジオでの演奏をも後押ししてくれた。
「そうなんです」
――海外の観客って、どんな風に反応しているんですか。
「それが、日本とまったく変わらないんです。日本でも若いお客さんが増えているんですが、ロンドンとかはさすがにYMOのファン中心だろうと思っていた。でも、そういう方もいる一方で、ステージを終えた細野さんが煙草を吸いに外に出てたら、スケボー抱えたお兄ちゃんが寄ってきて、“サイコーだったよ!”って(笑)」
――いい話ですね。
「みんな、それがうれしかったんですよね。いまの音楽として、ちゃんと認識されてるということが。今度のアメリカ公演がどうなるか、まだわからないですけど、でもベルウッドやURCの音源がアメリカで人気になったりしているのを見てると、それこそ細野さんが50年かけて培ってきたものが、遠いアメリカやイギリスで評価されるようになってきたんだな、と思う。メインストリームではないにしてもコアに続けてきたものが、こうやって報われることってすごくうれしいし、自分がやっている音楽に対する自信にもなるんですよね」
取材・文 / 真保みゆき(2019年3月)
FRESH&REFRESH 2019 -梅雨のレン祭り-
6月16日(日)
大阪 千日前 ユニバース
出演: 高田 漣(vo, g) / 伊藤大地(ds) / 伊賀 航(b) / 野村卓史(key) / ハタヤテツヤ(key)
開場 16:15 / 開場 17:00
全自由 4,500円(税込 / 整理番号付 / 別途ドリンク代)
※小学生以下無料 / 整理番号順入場 / 入場時に学生証提示で1,000円キャッシュバック
※お問い合わせ: 清水音泉 06-6357-3666
6月23日(日)
東京 鶯谷 東京キネマ倶楽部
出演: 高田 漣(vo, g) / 伊藤大地(ds) / 伊賀 航(b) / 野村卓史(key) / ハタヤテツヤ(key)
開場 16:15 / 開場 17:00
指定席 4,800円 / 立見 3,800円(税込 / 整理番号付 / 別途ドリンク代)
※6歳以下1名まで入場無料・座席が必要な場合は要チケット / 整理番号順入場 / 入場時に学生証提示で1,000円キャッシュバック
※お問い合わせ: ホットスタッフ・プロモーション 03-5720-9999

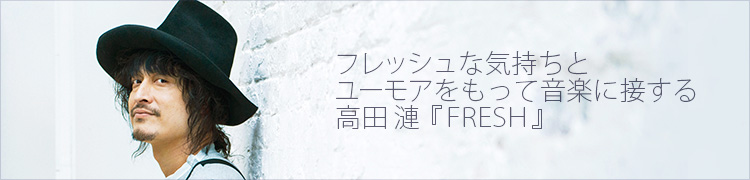

 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。