テーマは“自分にしかできない音楽”――。粗品が完成させたセカンド・フル・アルバム『佐々木直人』は、まさにそのテーマを体現する傑作ロック・アルバム。自身の本名をタイトルに冠したことも頷ける、粗品という“存在”が聴き手にぶつかってくるような野心的かつオリジナリティにあふれる一作だ。本当にこの男は、お笑いにおいても、音楽においても、天才だ。アルバム制作について、ライヴについて、そして、表現と救いの関係について、本人にたくさん語ってもらった。
――まず、アルバム『佐々木直人』はどのようなコンセプトを基に制作がスタートしたのでしょうか?
「“自分にしかできない音楽”というコンセプトで作った12曲です。ファースト・アルバム(『星彩と大義のアリア』)の時は、リスナーに寄り添うようなものを目指して作りました。そもそも僕の中にある音楽に対する理念が“お笑いで救えなかった人たちを救いたい”というもので、ファースト・アルバムは1曲1曲が誰かには刺さるように、全曲が誰かの救いのお守りになるようにと思って、全編“優しさ”で作ったんです。でも今回はちょっと変わりました。12曲全部がお守りというわけではなく……まあ数曲お守り的な曲もありますが、基本的には自分本位に、自分が歌いたい歌、自分が聴いてほしい音、それをわがままに作ったアルバムになりました」
――前作からの意識の変化は、なぜ生まれたのでしょう?
「“自分にしかできない音楽”というのは、僕の今いちばんの目標でもあります。そもそも僕は芸人をやっていて、音楽活動でいうと、ボーカロイドで曲を作ったり、楽曲提供をしたりっていうのはありましたけど、いざ自分で歌うとなった時、最初は革ジャンを着て、髪型もリーゼントみたいな感じにして、ライヴはアイメイクをしていたんです。というのも、僕はロックンロールが好きだから。でも、それってじつはロックンロールを“演じてる”というか、“やりにいってた”んですよね。僕はザ・ブルーハーツが大好きなんですけど、自分の曲を“ブルーハーツっぽい”と言われると、前は嬉しかった。“俺が見ていたロックができてる!”と思って。でも、この1年いろんなアーティストと対バンライヴを重ねて、いろんな音楽に触れる中で、“それって、果たして喜んでいいことなのかな?”と思うようになりました」
――“〇〇っぽい”と言われることは、じつはロックンロールの本質からかけ離れていることなのかもしれない。
「そう、ロックを“やりにいってる”のって、じつはダサいんちゃうか? と思って。そうなったらもう、やっぱり“自分らしい音楽”をやりたい、と。聴いただけで“これ粗品が作った曲だな”と思われるような、自分の個性が詰まった、自分にしかできない音楽ができたら最高だな、と思ったんです。だからライヴも、途中から僕は革ジャンを脱いで、パジャマと寝ぐせ姿でステージに上がるようになりました。ありのままの自分を取り繕う必要はないと思って。“粗品がロックを演じる”んじゃなくて、“粗品が、佐々木直人として、やりたい音楽をやりますよ”っていう、そういうスタンスに変わったんです」
――お話を聞いて思うのは、前作ではあくまでもリスナーの方を向いていた“救い”のベクトルが、今回は“自分自身を救う”というほうにも向いた、ということでもあるのかなと。
「たしかにそんな曲もあります。自分が救われる曲も書いたし、“自分しか共感できないだろうなあ”という曲も恐れず入れました」
――実際、アルバムが完成しての手応えはいかがですか?
「かなり達成感があります。言ってしまえば、“もう3枚目のアルバムは出さんとこかな”と思うくらい良いものができました」
――粗品さんにとっての“自分らしい音楽”とは何なのか。あえて言語化すると、それはどういったものなのでしょうか。
「作詞と作曲でそれぞれあります。まず作詞。“どんな言葉で伝えるか?”なんですけど、やっぱり“粗品が歌っているから説得力ある”というのが、僕にしかできない音楽だよなと思った。今から音楽を始める人って、その人がどんな人か、聴き手はわからないですよね。でも僕は“粗品”という人物像をいろんな人に知っていただいている状態で曲を世に出せる。それって結構なアドバンテージだと思うんです。このチャンスを使わん手はないなと。“粗品みたいな生き様のやつが、こうやって背中を押してくれるのは元気が出るなあ”とか、“粗品みたいな考え方で仕事をしているやつが、こうやってケツ叩いてくれるからストイックになれるな”とか、そうやって“粗品が歌うから説得力が増す言葉を歌う”というのは、今回かなり意識しました」
――作詞における苦労は、前作と変わりましたか?
「前作以上にすんなり書けました。自分が思ったことを、歌詞でも押し通せましたね。たとえば前回のアルバムでは、〈絶対大丈夫の歌〉というタイトルの応援ソングを書きました。好きな人に振られた時も大丈夫だよ、身内が亡くなった時も大丈夫だよ、会社で嫌な思いした時も大丈夫だよ、友達にいじめられた時も大丈夫だよ……そうやって、できるだけ多くの人が、一瞬でも共感できるような歌を書こうと思って、苦労して書いたんです。今回もそうやって書いた曲は2曲ほどありますが、それ以外ほとんどの曲で、自分が経験していないことは書いていないです。自分が経験したことを、自分の範疇で無理せず書きました」
――では、作曲面に関しては?
「作曲に関しては、やっぱり世の中にはいろんな音楽がありますからね。“このメロディはあの曲に似てる”とか、もちろん発生してしまうことだとは思いますが、そんな中でもかなり“自分らしさ”をちりばめられたなと思います。それは大胆な発想の曲構成もそうですし、メロディの動かし方にも自分らしさが見えてきた。具体的には、半音の使い方とか、そういう部分です。あくまで自分調べですけど、まだほかの人がやっているのを見たことないようなことを心がけてやるようにしました。しかも、それを3ピース・バンドに落とし込むめずらしさが、今の自分の中では合点がいくんです」
――今回も前作から引き続き、藤本ひかりさん(b)、岸波藍さん(ds)との3ピース編成となりますが、“3ピース・バンド”という編成が粗品さんにしっくりくるのはなぜなのだと思いますか?
「もともとは“アンチ現代音楽”という旗を立てて、どんどん複雑になっていく今の音楽の逆を行きたいっていう狙いもあったのですが、もっと言うと、言葉がすんなり入ってくるのが3ピース・バンドの強みだなって思いますね。僕の音楽のデータをPC画面上で並べたら、ドラム、ベース、ギター、ヴォーカルで、究極4トラックしかないんですけど、その場合、曲の1/4を占めているのが僕のヴォーカル。それは言葉が入ってくるだろうと。あとはさっきも言いましたけど、気をてらった構成とか、奇抜なアイディアを入れ込むことに関しても、“3ピース・バンドでこれをやるやつはおらんやろう”っていうのが一つ乗っかってるんで、より箔がつくっていうのはあります」
――お笑いのライヴと音楽のライヴでは会場の空気もまったく違うと思います。そこで生まれるお客さんとのコミュニケーションの違いについて、粗品さんはどのように感じられていますか?
「“どんなライヴがいいライヴなのか?”っていう正解や美学があったとして、それがお笑いは決まっているけど、音楽は決まっていない。それがいちばんの違いだと思います。お笑いは、とにかく笑いを取ったらいいんです。ウケる数が多ければ多いほどいい。これはお笑いをやっている人全員の共通の美学で、覆らないと思う。音楽ライヴも同じように“盛り上がったもん勝ち”みたいに思っている人もいるかもしれない。実際、綺麗にお客さんの腕が上がっていて、声が揃っていたら“いいライヴだな”って思われがちなんですけど……正直、ライヴをやってきて、僕は“それってどうなんだろう?”って思ったんです。音楽をやる美学として」
――盛り上がるだけが、音楽の正解ではない?
「もちろん、それは存在してもいい美学のひとつなんですけど、僕はライヴの冒頭で“盛り上がらなくていいんで”とか“地蔵でいいんで、ボーっと聴いてください”ってよく言うんです。音楽はお笑いと違って、目に見えない楽しみ方がもっとできるものだと思うんです。フロアが盛り上がっていないからって、それが悪いライヴだったか? と言うと、そうでもないと思う。感動して静かに胸打たれている人もいるかもしれない。逆にね、演者が“声出せ! 聞こえねーよ!”みたいに煽れば、簡単に盛り上がるんです。客を煽るって、ほとんどのアーティストがしていることだし、それを否定するわけじゃないですけど、“まあ、それをやったら盛り上がるに決まってるだろ”と。それは評価には値しないんじゃないか? と思うんですよね。もちろん美学として“盛り上がったもん勝ちや”という人がいてもいいし、それも認めますが、僕はあくまでも自由に楽しんでもらうべきだと思います。今回、アルバムの1曲目に〈ギャーン!〉という曲があって、この曲はライヴでも1曲目に披露しようと思っているのですが、曲の最後で“ようこそこの場所へ 自由に楽しんで”と歌っていて。僕はライヴのMCでずっと“自由に楽しんでください”って言ってきました。何してもいいんです、人に迷惑かけなければ。一緒に歌ってもいいし、地蔵になってもいい。なんでもいいんで、自由に楽しんでくださいって。まあ傍から見たら“粗品、滑ってたな”みたいなことになるかもしれないけれど、僕は音楽のライヴに正解はないと思うので。それが、僕が音楽をやる上での美学です。あとね、これは言っておきたいのですが、みんながフロアの熱気を追い求めすぎるせいで、未だに男女エリアを分けないんですよ。いや、どんだけ痴漢があんねんって」
――なるほど。
「社会問題寸前ですよ。いろんなアーティストのライヴで、痴漢騒動が発生している。これの対処法でいちばんいいのは、男女でエリアを分けてしまうことだと思うんです。もちろん同性の痴漢もありえますが、可能性としては少なくなるわけで。分けたらいいのになんでやらないのか? っていうと、それをやると集客が減るからなんです。これは自分で実践して気づいたことですが、男女を分けることのデメリットは、集客が減ること。友達を誘いづらくなるし、チケット購入時に性別を入力しなければならないので、“とりあえず4枚取っといて、あとで友達を誘おう”みたいなことがやりづらくなる。あともう一つは、やっぱり盛り上がりづらいんですよ。男女でエリアを分けると、盛り上がりに差が出て一体感が出ない、みたいな。でも、それが嫌だから男女エリアを分けないって、“盛り上がったもん勝ち”の美学に沿っているわけじゃないですか。僕は“いや、ちゃうけどな”って。そんなことよりもお客さんの安全を鑑みて、男女でエリアを分けたい。それは前回のツアーもそうしましたし、少人数のライヴハウスでもそうするし、次のツアーもそうします。盛り上がりにこだわっていないから、それができるんです」
――男女エリアを分けるライヴのやり方にも、確かな手応えを感じられているんですね。
「かなり感じています。男女を分けて、いいことしかない。安心して楽しめるっていう声もありますし、女性は今までよりも身長差を気にしなくてよくなって、見やすくなったという声もあります。ただ、集客だけちょっと渋くなってしまって、会社に申し訳ないっていうのはありますが、そこは興行として僕がもっと頑張らないとなと思っています」
――アルバムのジャケットに使われている写真は、粗品さんにとってどのような写真なのですか?
「これは小学校低学年の時です。たぶん母ちゃんお気に入りの一枚なんです。テレビに出始めた時に、“少年時代の写真を番組に貸してください”って言われたので実家に連絡したら、この写真がいちばんに送られてきました。母ちゃん的にはこれがお勧めみたいです。純粋に音楽を楽しめていた時期の自分だと思うし、“自分らしい音楽したい”っていう今回のアルバムのコンセプトにも合うなと思って、この写真をジャケットにしました」
――この写真に映っている佐々木直人少年がこのアルバムを聴いたら、どんなふうに感じると想像しますか?
「その発想は僕がお笑いも共通して大事にしてるところです。僕、学生時代の自分が見たらファンになるようなことしたいと思っているんです。高校生の時に“こんな芸人おったら、めっちゃ好きなのにな”と思えるようなことをしたいと思っているし、それは音楽でもそう。まさに今回の曲は、自分がちっちゃい時とか学生時代に触れていたら、めっちゃハマってたよなっていう12曲です。なのでこの写真の少年も、このアルバムを聴いたら“かっこいい!”って気に入ると思いますね」
――アルバムの最後を飾る「直人とお母さんの歌」は、とてもパーソナルな歌だと思いますが、この曲はどのようにして生まれた曲ですか?
「前回のアルバムで〈はるばらぱれ〉というお父さんへの曲を作ったので、今回はお母さんの曲を作りたいなと思ったのと、あと歌詞にも出てくるんですけど、父ちゃんが死んだ時に、ほんまに“もっとありがとうと言えばよかった”って後悔したんです。“ありがとう”って言い足りなさすぎた。今も実際、お母さんに“ありがとう”って言い足りてないので、曲にしました。僕はね、世間的に見たら“マザコン”と言われる部類に入ると思うんです。そのくらい、尊敬の念を込めてお母さんのことが好き。たぶん海外やったらマザコンなんて言葉で虐げられることはないと思いますが、日本だと“マザコンやんけ”って茶化すニュアンスで言われるじゃないですか。とくに若い男性が母親に対して素直に愛を伝えるのは恥ずかしいって皆さん思われるかもしれないけど、“いや俺、全然恥ずかしくないよ”って。言わば先陣を切って、母親に向かって“大好き”という言葉を使わせてもらった感覚です」
――この曲が最後に収録されたことは、このアルバムに何をもたらしたと思いますか?
「今回の12曲は、本当にバラバラなので。『星彩と大義のアリア』の時はわりと一本、筋が通っていたと思うんです。“優しさ”とか、“人を救いたい”とか、言葉で形容できる筋が通っていた。でも、今回の曲はあまりにバラバラで、正直、言葉で形容できるような筋が通っていないんです。でも唯一、“佐々木直人”という筋だけが通っている。“これが僕が今いちばん伝えたい12曲やねん”という筋だけは確かにある。そんなアルバムの最後を、もっともパーソナルで、もっとも愛にあふれて、メロディのニュアンス的にも個人的にもっとも気に入っているこの曲にすることで、『佐々木直人』というアルバムでした、ありがとうございました、という締め括りにできたんじゃないかと思います」
――もう1曲、個人的に5曲目「はらぺこジョアンナとマラフーテのたまご」が粗品さんにとってどのような曲なのか、とても気になりました。
「この曲は自殺についての曲です。いろんな自殺の仕方を歌っているんです。かねてより自殺願望がある人からの相談が多くて、“死んだらあかん”って言ってきた。前回のアルバムでも、そういう人のことを頭に浮かべながらストレートに“生き死に”について自分の考えを曲に書きました。“生きているのは素晴らしいことだ”って、音楽で伝えた。それで満足だったんです。反響もいただいたし、“この曲のおかげで生きられています”とも言われた。でも、前回のアルバムから今回のアルバムを作る間に、“自殺失敗しました”みたいなメッセージとか、究極的には“死にました”っていうDMが、そのファンの人の友達から来たことがあって。“生前は粗品さんの楽曲を聴いて元気をもらってたんですけど、じつは線路に飛び込んで死んでしまいました。地名と電車事故で調べたら出てきます”って言われて調べたら、ほんまやった。“救い損ねた”と思ったんです。すごいショックだったし、俺は音楽に無限の可能性を感じていたのに、有限だったんだ、と。そこから“これはアプローチを変えなあかん”と思ったんです。今回、〈朝影の宝石〉という曲も収録していて、そこでは今までどおりストレートに“死んだらあかんで”って諭すように歌っています。でも〈はらぺこジョアンナとマラフーテのたまご〉は、言うたら今にも自殺しようとしている人を、怒って止めているような歌なんです。“何してんねんおまえ、しょうもないな”て」
――なるほど。
「“自殺したいんです”って言う人を見捨てはしませんが、腹も立つんですよ。“なめんなよ”と。命を軽んじすぎだろと。僕は自分の父親を亡くしているんで、そんなやつに“自殺したいんです”なんて言ってくるのって、“どういう神経してんねん”とも思うし。いろんな思いがある。怒りの感情もある。だから、この曲では自殺を生半可に考えている人を怖がらせたかった。歌詞で“さよなら”と歌った後に1小節分無音になるところも、実際のレコーディング現場では手動で止めたんですけど、ミックス段階でパソコンを使ってさらに人工的に、急に機械がバグって止まったみたいに、ほんのりと残っていた余韻すらスパンッと切りました。“自殺したら、こう思われるんだ”と思ってもらいたくて。あと、僕が4、5人分くらいの声色で歌っているのも、自殺を考えている時の精神状態を再現したかったからです」
――“怒り”を表現してでも、粗品さんは人を救いたいと思っているように僕には感じられます。粗品さんにとって、表現と救いとはどのように結びつくものですか?
「表現と救いに関しては、ほかの人ももっとやらなあかんと思います。僕は有名人であり表現者ですけど、SNSで“いじめられてます、どうしたらいいですか?”って相談がくる。これって芸能人あるあるだと思います。いろんな芸能人にそういう相談がきていると思う。それで僕、返事するんですよ。“頑張れ”とか。そしたら、めっちゃ喜んでくれるんです。僕自身は数年後には忘れてしまっているけど、あとから“学生時代に粗品さんからメッセージが来て、その一言だけで高校3年間、泥沼だけど頑張れました。ありがとうございました”って言われたりもしました。ちょっと待て。“頑張れ”って言っただけやで? この費用対効果ってすごくないですか? 正義の味方になれるんですよ、有名人や表現者って。だから、やらないと。有名税って言葉がありますけど、それはパパラッチに追われるとかバッシングされるとかだけじゃなく、人にいいことをせなあかんっていうのも有名税だと思っています。このパワーと影響力は、使わないといけない。その矛先が政治運動に行く人もいますよ。影響力あるから“選挙に行こうぜ”と促す。それももちろんいいけど、それよりもっと人のこと救ってあげたら? とも思うんです。でも、これをやっている人って本当に少ない。だから、使命的なものかもしれない。これができる人って限られているんだから、やるべきだろうと思います」
取材&文/天野史彬
撮影/西田周平

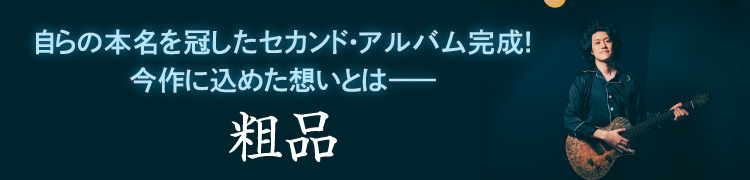






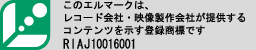
 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。