リサーチ
ルックバック〜7月14日 「ラ・マルセイエーズ」がフランス国歌に制定
2025/07/14掲載
フランス国歌の元ネタがあったらおしえてください。
1795年7月14日は、フランスの国歌に「ラ・マルセイエーズ」が制定された日です。7月14日は、フランスの歴史のなかで重要な事柄が起こった日として知られ、1789年にはパリの民衆がバスティーユ牢獄を襲撃したのをきっかけにフランス革命の勃発した日であり、その翌年にはフランス連盟祭が開催されました。現在のフランスの建国記念日でもあります。
連盟祭が開かれた1790年の5年後にフランス国歌として制定された「ラ・マルセイエーズ」ですが、元をたどると、フランスの軍人で工兵大尉のクロード=ジョゼフ・ルジェ・ド・リールが、出征する部隊を鼓舞するために、ストラスブール市長の邸宅で作詞・作曲した「ライン軍のための軍歌」と題する小品というのが定説となっています。
この「ライン軍のための軍歌」は、当初のアルザス地方から次第にパリへと譜面が行きわたり、多く出版されたほか、マルセイユの連盟兵が歌い始めたことで口伝えに広まって、大きな評判を呼び、パリでも流行しました。今風に言えば、“バイラル”を生み出したというわけです。「ライン軍のための軍歌」という曲名がありながら、「ラ・マルセイエーズ」の名が定着したのは、このマルセイユ連盟兵がパリ入城した際に歌ったことが由来となっています。
当初から口伝えなどで伝わったこともあり、「ラ・マルセイエーズ」には歌あり版、歌なし版ほかさまざまなヴァージョンが存在しています。ナポレオン・ボナパルトが皇帝になった帝政下と王政復古期には、歌詞の内容から原則オフィシャルな場で「ラ・マルセイエーズ」の歌唱は禁止されましたが、1830年の7月革命で再び脚光を浴びると、解禁。ロマン派の作曲家ベルリオーズがオーケストラに編曲しました。
ただし、フランス第三共和政は、1879年に正式な和声付け(メロディに適切なコード=和音を配置すること)を決めずに「ラ・マルセイエーズ」を国歌に制定してしまったため、異なる楽団が集まって演奏すると、混乱に陥ることもしばしばでした。そのため、基準となるヴァージョンが必要となり、1887年にフランス陸軍省が公式版を選定。その後、1944年に国民教育省が学校でラ・マルセイエーズを斉唱することを推奨する通達を出し、1946年と1958年の憲法第2条において、「ラ・マルセイエーズ」が国歌であることが確認されました。
誕生から2世紀以上が経つなかで、オペラやジャズなどにも多大な影響をもたらした「ラ・マルセイエーズ」ですが、演奏の速度も時代によって移り変わりました。1974年から1981年において第20代フランス大統領を務めたヴァレリー・ジスカールデスタンは、原曲よりやや遅めのテンポで演奏させましたが、続く第21代フランス大統領のフランソワ・ミッテランはより速いテンポへ戻して、現在の「ラ・マルセイエーズ」となりました。
また、ときおり物議を醸すのが、その思想的で好戦的な歌詞です。「行こう 祖国の子らよ」で始まるこの歌は、「武器を取れ 市民らよ / 隊列を組め / 進もう 進もう! / 汚れた血が / 我らの畑の畝を満たすまで!」というフレーズを繰り返し、刺激的で挑発的な歌詞が並ぶなど、戦意高揚的として「現代には相応しくない」との意見がありますが、革命の歌であり、自由と民主主義を獲得するために団結の象徴として歌い継がれてきた楽曲として、現在でも受容されています。サッカーのワールドカップのヨーロッパ予選や本戦などのフランス代表の試合では、観客による「ラ・マルセイエーズ」の大合唱も見られます。
(写真は「ラ・マルセイエーズ」を含むドラマティックなメドレーを収録したスタンリー・ブラックのアルバム『アイ・ラヴ・パリ〜魅惑のフランス』)
連盟祭が開かれた1790年の5年後にフランス国歌として制定された「ラ・マルセイエーズ」ですが、元をたどると、フランスの軍人で工兵大尉のクロード=ジョゼフ・ルジェ・ド・リールが、出征する部隊を鼓舞するために、ストラスブール市長の邸宅で作詞・作曲した「ライン軍のための軍歌」と題する小品というのが定説となっています。
この「ライン軍のための軍歌」は、当初のアルザス地方から次第にパリへと譜面が行きわたり、多く出版されたほか、マルセイユの連盟兵が歌い始めたことで口伝えに広まって、大きな評判を呼び、パリでも流行しました。今風に言えば、“バイラル”を生み出したというわけです。「ライン軍のための軍歌」という曲名がありながら、「ラ・マルセイエーズ」の名が定着したのは、このマルセイユ連盟兵がパリ入城した際に歌ったことが由来となっています。
当初から口伝えなどで伝わったこともあり、「ラ・マルセイエーズ」には歌あり版、歌なし版ほかさまざまなヴァージョンが存在しています。ナポレオン・ボナパルトが皇帝になった帝政下と王政復古期には、歌詞の内容から原則オフィシャルな場で「ラ・マルセイエーズ」の歌唱は禁止されましたが、1830年の7月革命で再び脚光を浴びると、解禁。ロマン派の作曲家ベルリオーズがオーケストラに編曲しました。
ただし、フランス第三共和政は、1879年に正式な和声付け(メロディに適切なコード=和音を配置すること)を決めずに「ラ・マルセイエーズ」を国歌に制定してしまったため、異なる楽団が集まって演奏すると、混乱に陥ることもしばしばでした。そのため、基準となるヴァージョンが必要となり、1887年にフランス陸軍省が公式版を選定。その後、1944年に国民教育省が学校でラ・マルセイエーズを斉唱することを推奨する通達を出し、1946年と1958年の憲法第2条において、「ラ・マルセイエーズ」が国歌であることが確認されました。
誕生から2世紀以上が経つなかで、オペラやジャズなどにも多大な影響をもたらした「ラ・マルセイエーズ」ですが、演奏の速度も時代によって移り変わりました。1974年から1981年において第20代フランス大統領を務めたヴァレリー・ジスカールデスタンは、原曲よりやや遅めのテンポで演奏させましたが、続く第21代フランス大統領のフランソワ・ミッテランはより速いテンポへ戻して、現在の「ラ・マルセイエーズ」となりました。
また、ときおり物議を醸すのが、その思想的で好戦的な歌詞です。「行こう 祖国の子らよ」で始まるこの歌は、「武器を取れ 市民らよ / 隊列を組め / 進もう 進もう! / 汚れた血が / 我らの畑の畝を満たすまで!」というフレーズを繰り返し、刺激的で挑発的な歌詞が並ぶなど、戦意高揚的として「現代には相応しくない」との意見がありますが、革命の歌であり、自由と民主主義を獲得するために団結の象徴として歌い継がれてきた楽曲として、現在でも受容されています。サッカーのワールドカップのヨーロッパ予選や本戦などのフランス代表の試合では、観客による「ラ・マルセイエーズ」の大合唱も見られます。
(写真は「ラ・マルセイエーズ」を含むドラマティックなメドレーを収録したスタンリー・ブラックのアルバム『アイ・ラヴ・パリ〜魅惑のフランス』)
最新リサーチ




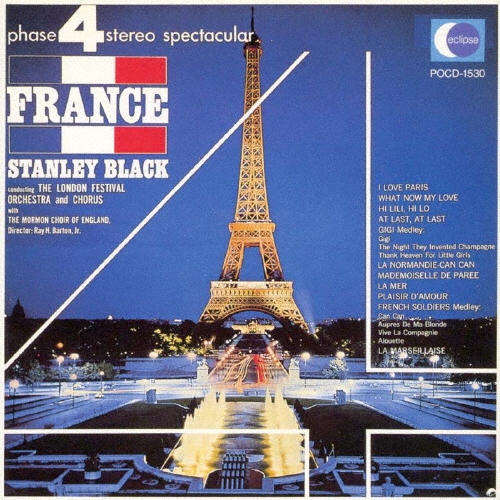
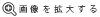

![[CM] Panasonic QualityのCM「あかりはLEDへ」で流れる透き通った歌声の楽曲は? [CM] Panasonic QualityのCM「あかりはLEDへ」で流れる透き通った歌声の楽曲は?](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z348011852.jpg)
![[映画] 映画『センチメンタル・バリュー』の予告編で流れる曲は? [映画] 映画『センチメンタル・バリュー』の予告編で流れる曲は?](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347057167.jpg)
![[その他] さらさ「YOU」とドラマ『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』のコラボMVに出演しているのは? [その他] さらさ「YOU」とドラマ『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』のコラボMVに出演しているのは?](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347057125.jpg)
![[CM] 第一三共ヘルスケア「エージーアレルカット」のCMに出演している女性グループは? [CM] 第一三共ヘルスケア「エージーアレルカット」のCMに出演している女性グループは?](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347057170.jpg)
![[CM] 陸上の桐生祥秀選手や体操の橋本大輝選手らが出演する日本生命のCMで流れる曲は? [CM] 陸上の桐生祥秀選手や体操の橋本大輝選手らが出演する日本生命のCMで流れる曲は?](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/412512/4125121727.jpg)
![[映画] 映画『グランド・イリュージョン/ダイヤモンド・ミッション』の予告編で流れる曲は? [映画] 映画『グランド・イリュージョン/ダイヤモンド・ミッション』の予告編で流れる曲は?](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347056847.jpg)
![[その他] AKASAKI「アクション」MVに出演している女性は? [その他] AKASAKI「アクション」MVに出演している女性は?](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347057113.jpg)
![[CM] 不二家「ルック」と「ケーキ(洋菓子)」のCMに出演している男性グループは? [CM] 不二家「ルック」と「ケーキ(洋菓子)」のCMに出演している男性グループは?](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347057114.jpg)
![[CM] 奥村組の企業広告「建設が、好きだ。」篇で流れるインスト・ロックの楽曲は? [CM] 奥村組の企業広告「建設が、好きだ。」篇で流れるインスト・ロックの楽曲は?](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/412509/4125090024.jpg)
![[その他] 2月9日誕生!~青春ラブコメコミックのマエストロ・あだち充と印象的な主題歌たち [その他] 2月9日誕生!~青春ラブコメコミックのマエストロ・あだち充と印象的な主題歌たち](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/421304/4213040546.jpg)
![[映画] 永瀬廉×吉川愛W主演映画『鬼の花嫁』の予告編で流れる曲は? [映画] 永瀬廉×吉川愛W主演映画『鬼の花嫁』の予告編で流れる曲は?](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/412601/4126012084.jpg)
![[CM] 二宮和也出演、サントリー「こだわり酒場」のCMで流れる曲は? [CM] 二宮和也出演、サントリー「こだわり酒場」のCMで流れる曲は?](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347057018.jpg)


